�C���u�[�����ǂ��݂����낤��
�@( ��P��s�e�[ �}�E�V���^�C�i�[�t�A�P�X�X�R�N�W���V���j
�@
�@�Ă���ɂ������Ƃ�������Ă���B���͎��͋C���t�̃g���[�j���O�̎d����A�^�����̎肩������ �g���[�j���O�@�Ȃǂׂ��������̂����A���ꂪ�ł��Ȃ������̂ŁA�T�ςŏq�ׂ邱�Ƃ����ł��Ȃ��B������A�肩�玡���p���[����˂���Ƃ����_�ŁA�V�� �^�C�i�[�́w�����ɂ��č������E�̔F�����l�����邩�x����A�C�Ƃ̈�i�K�ŃG�[�e�������r���~��Ă����ӏ����Љ�邱�ƂƁA�����ЂƂA�C���t�����҂𗣂ꂽ�n�_���瑀�鎡�Ö@�Ɗ֘A���āA�����������ӎ��ɓ��������邻�̂����̓A�g�����e�B�X����̖��c�ł͂Ȃ����Ƃ����^�O����邱�Ƃ����ł��Ȃ��B��������c���o���_�Ƃ��ĎQ���҂ƍ����̃e�[�}�ɂ��ċc�_�ł���Ǝv���Ă���B
�@
�@�@�A�X�g�����̂̈�A�̕ӂɂ���P�U�ق̘@�i�`���N���j�A�S���̕ӂɂ���P�Q�ق̘@�A�`�� �ӂɂ���P�O�ق̘@�A�B���̕ӂɂ���U�ق̘@�Ƃ����ӂ��ɘ@�i�`���N���j���������i��]���n�߁j�����Ă����C�s�҂́A�̓��̃G�[�e�������R���g���[���ł���悤�ɂȂ��Ă���B�����ăG�[�e���S�������Ƃ����G�[�e�������A�X�g�����̑S�̂ɑ���o���A���̃G�[�e�����ɂ���ăA�X�g�����̂̊e�@�̉�]�𐧌䂷��B�����Ă��̗���͂���ɁA�@�̐�[����̊O�֏o�Ă����B���̋y�Ԕ͈͂́A���̐l����I�ɐi������قǂɍL�����Ă����B�V���^�C�i�[�͈ȏ�̂悤�ɕ\�����邪�A��I�ɂ����ꂽ�l�͊e�@����G�[�e�����o�����A���͂̐l�����ɂ��̗�I�g���݂𐁂��t���Ă���Ƃ��A���̐l����芪���I�[�����傫���Ȃ��Ă����ƌ����ς����邩������Ȃ��B
�@�G�[�e���S�����G�[�e�����̌��ɂ���O�ɁA�v�l�̏W���ɂ���ē����ɉ��̒��S�_�������K�v���� ��B�����Ȃ��Ƃ��̐l�͗�I���E�Ɗ��o���E�̊W�𐳂������@�ł��Ȃ����z�ƂɂȂ鋰�ꂪ����ƃV���^�C�i�[�͌����B
�@�ȉ��A����ɉ����ė����G�[�e�����Ɍ��y������ӏ������p���悤�B
�@
�u�����̒��S�_���\���m�ł�����̂ɂȂ�����A����͉����ɁA�܂�A�����̕ӂ�Ɉڂ����B�� �̈ڍs�͏W���̍s���X�ɐςނ��Ƃɂ���Đ�����B���̌�A��ɏq�ׂ��G�[�e���̓��̗��ꂪ���̕���������o�����B���̗���͐l�Ԃ̎��͂̐S���I��Ԃ��Ƃ炵�����B
�@�X�ɕʂ̍s�����邱�ƂŁA�C�s�҂̓G�[�e���̂̎p���������߂���悤�ɂȂ�B����܂ł��̎p���͊O�E���痈�鏔�͂Ɠ��̂ɗR�����鏔�͂ɂ���Č��߂��Ă����B����������Ȃ�i����ςނ��Ƃɂ���āA�C�s�҂̓G�[�e���̂�����������Ɍ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B���̔\�͈͂��闬��̔����ɂ���Đ�����B����͂قڗ���ɉ����Đi�ޗ���ł���A����̕ӂ�ɂ���Q�ق̘@�ɂ��̒��S�_��������ł���B�A��������o�Ă��闬�ꂪ�ۂ��`����Ȃ��A���̊ۂ��`����������̂��������A�Q�ق̘@�Ɍ������A��������g����Ȃ�������ƂȂ��ė���ɉ����������Ƃ�Ƃ����̂����̃v���Z�X�ł���B�v�iTaschenbuch,Nr.600�CWie erlangt man Erkenntnisse der H��heren Welten ?�g S.143�144 )
�@
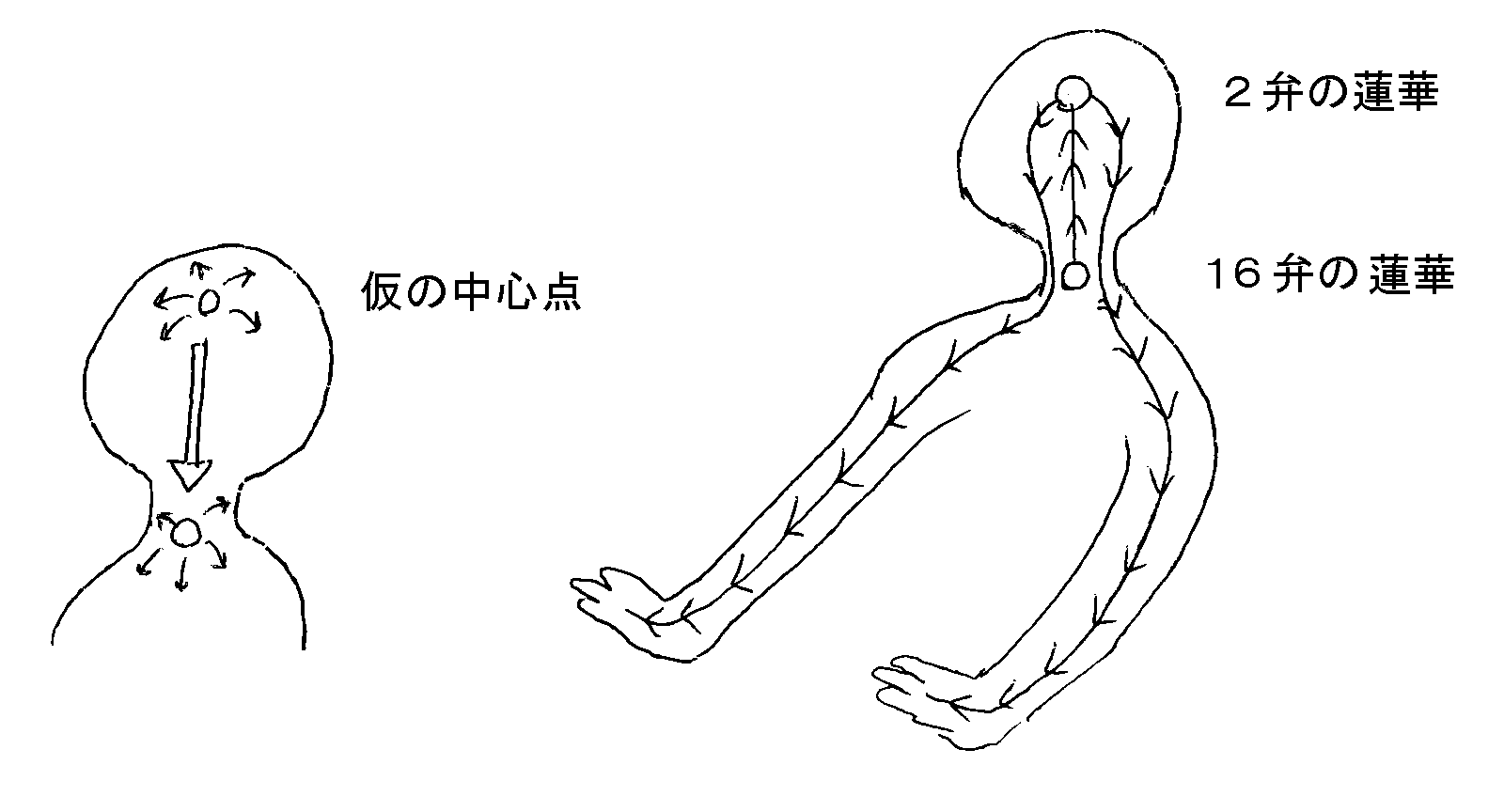
�A�@���Ď��ɁA�C�����ÂŊ��҂̑̂������������A�C��p���镐�|�ʼn����Ăɂ���đ�������d �g�݂��l�@���Ă݂悤�B�C�����ÂŊ��҂��}���I�l�b�g�̂悤�ɗx�点��l�q�̓r�f�I�Ō������Ƃ�����i����l�ԉȊw���ōs�Ȃ�ꂽ���m��w�u���Łj�B�Q�l�̋C���t���傫�ȕ����i���ꂩ�j�̊p�ɂ��ꂼ�ꗣ��ė����A�^�Ɋ��҂�����B�Q�l�̋C���t�͂��̊��҂߂����Ď���������A�C���Ă���B�C���t�̘r�̓��������҂̑̂̓����ƘA�����Ă��邩�Ɍ�����B���҂͖��ӎ���ԂɂȂ��Ċ�����@������A�ӂ������̓������J��Ԃ��B���ɂ͕s�p�ӂɓ|��ĕ��̊p�ɂԂ��ĉ�������邱�Ƃ�����̂Œ����ł͋֎~����Ă���Ƃ����i���[�V�������ʔ��������B�Ȃ����Ò��̗l�q�ȊO�ɋ����[�������̂́A�C���t�������ɂȂ�A��̂�O�ɂ����߁A����˂��o���āA���̓����u�����u�����ƐU���āA�C�����Ɣ��d�����ʂ������B
�@�Q�N�قǑO�A���̐��E�ɂ���āA�����r�ܐ��̂a�w�߂��̒����C�����̉@�ɍs�������q�w�������Ă��ꂽ�Ƃ���ɂ��ƁA���̏��q�w���̓x�b�h�ɐQ�����ꂽ��A���搶�����ꂽ�Ƃ��납�����������ƁA�r�Ȃǂ�����ɓ������Ƃ����B���҂̑̂������Ƃɂ���đ̓��̃o�����X�̕�����킯�����A���̏��q�w���́A�O�ȂĂ��̂悤�Ȃ��Ƃ�����ƌ����Ă����Ȃ������̂ŁA���������炵���B
�@�ȏ�͎��ÂƊ֘A���Ă��邪�A�����łȂ��ꍇ�Ɉڂ낤�B
�@�Ñ�_���A�哹�A���Ɍ��A���K�Ȃǂ��ɂ߂����\�͎҂Ǝ��̂��鍑�ۃ��K�A���̉���f�����X�g ���[�V�����Œ�q��������������A������肵���b�͂��łɉ��x���Љ�����A����͋ɒ[�ȗ�ł��낤�B���̒j�̔�����C�ɂ���āA���������l�Ԃ����̂܂܂̎p�Ń_�_���A�_�_���Ɛ��������o���Ȃ���O�i�������ɂ͉䂪�ڂ��^�������̂��B
�@���G��Ȃ��ő�����̂����点����A�|�����肷�鉓���Ă̏p�͍L���C��p���镐�|�ōs�Ȃ�� �Ă���B���̏ꍇ�A�C�����������鑤�Ƃ������鑤�̊ԂɎq��W������A�C��������������҂��C�s��ς�ł���ꍇ�A�悭��ԁB���K�A���̉�̃f�����X�g���[�V�����ł��A��q�����͉��ɍ������藧�����肵�ĉ�̘b���A������������Ă������A���Ƃ��u���\�́v�Ƃ������t��������ꂽ�����Ńr�O�[���z�����鏗����������A���Ɍ��̈��铮�������āA���ꂩ��n�܂邱�Ƃɋ��|���ăL���[�Ƃ����ߖ�����������A�ˑR����ǂ�łj��������A�̑呛���ł������B�l�_�̂����납��J�������\���Č���I�ȏu�Ԃ��B�낤�Ƃ��Ă����V�哪�̒�q�́A�肪�r�N�r�N�����ăJ��������܂炸�A�u����Ⴞ�߂��v�ƎB�e����߂Ă����B���̉�����߂Č������́A�̂������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B
�@�@�@�@�@ �a�͋C�Œ����@���̓_����l����ƁA�C�s��ςނ��Ƃɂ���āA�t�̋C�̗�������m���A����ɔ�������d�g�݂� ��q�̑̓��ɂł��Ă���̂��낤�Ǝv�����A����Ȃ�C���t�̂��Ƃ����߂ĖK�ꂽ���҂̑̂������Ă��܂����̂́A�ǂ����Ă��낤���B����͂Ƃ������A�C�s�ɂ���ĊO����̃G�[�e�����̗���i�C�̗���j�𑨂���悤�ɂȂ邱�Ƃɂ��ẮA�V���^�C�i�[���q�ׂĂ���B�ȉ��͂����قǂ̈��p�̑����ł���B
�@�u�@�\ ���Ɍ�����ʂ̌��ۂ�������ƁA���̃G�[�e���̗��ꂪ�A���̏�Ȃ������Ȏd���Ŏ��X�Ǝ}�����ꂵ�A�ו������Ă����A���ɂ͂����̐D���ɕς���B���� �͖ԍH�i�ԏ�̕����j�Ɏ��Ă��āA�G�[�e���̑S�̂��O���Ƌ�ʂ��鋫�E�ɂȂ�B����ȑO�G�[�e���̂̊O���͕��Ă��炸�A�F���ɕ݂��鐶���͂̊C�Ɍ������A�����̗͂���̖��������ɒ��ڂ��炳��Ă����A����O�E����̏���p�͂��̔疌��ʂ蔲���˂Ȃ�Ȃ��B���̌��ʏC�s�҂͊O����̃G�[�e���̗���������Ƃ�悤�ɂȂ�B���̗��ꂪ�ނɂ͒m�o�\�ƂȂ�̂ł���B�v(S.144)
�@�������V���^�C�i�[�̌����u�G�[�e���̗���v��P���Ɂu�C�̗���v�ɒu��������̂ɂ͖����� ��B�u�G�[�e���̗���v�ɂ́A�����ς琳�����s�ɂ���ď������ꂽ����̋���������A���N�I�A���ÓI�A�P�I�Ȑ��������т��Ă���B����A�u�C�v�ɂ́u�E�C�v�܂ł����܂܂��L���肪����B���ہA�C���t�͑���ɒɂ݂�^����悤�Ȏ�ނ̋C���邱�Ƃ��ł���i�ʍ���103�u�C�͒��킷��v�A�u�C�Ƃ̑����A�n�[�o�[�h�̈�w�҂̋C���̌��������s�̋L�v�c.�A�C�[���o�[�O�A�X�V�y�[�W�j�B�܂��咰�ۂɁA����B�����悤�Ƃ����u�C�v�������邩�A���ł����悤�Ƃ����u�C�v�������邩�ŁA���ہA�ۂ̐����傫�����������Ƃ����B��̓I������������ƁA�O�҂͋ۂ̐����Q�[�V�{�ɂȂ�A��҂͂T�O�[�X�O�p�[�Z���g�����ł����B�O�C�Ǝ˂͂P���B�P�X�W�P�N�A�����Ɖu�w�������S�̗��������炪�����B�i�w�C�̒���x�A���� ���B���A�Ώ��[�u�C���Ŋ����Â��e�[�}�ɂ���v�S�U�[�S�V�y�[�W�j
�@�Ƃ���ŁA�C�s��ς��|�҂͈Â���ɉB��Ď�����_���h�q�́u�E�C�v������������Ƃ��� ���A�V�̓��̒B�l�A�؍G�V�͔w�ォ��s�ӂɏP���Ă��K���P����������O�ɂ��̑���������ĂŔ���Ă��܂��Ƃ����̂ŁA���̗l�q��]�g�g�|�O���t�B�[�Œ��ׂ�������s�Ȃ�ꂽ�B�n�������C���t�═�|�҂͈��Ï�ԂŔ]�g���v��ƁA�]���̐l�ɋ߂����R�Ȕ]�g�ɂȂ邻�������A�Җڂ��[������؎��̔]�g�������Ȃ����B���̏�Ԃ͖��O���z�A���݈ӎ������ɂȂ��Ă����ԂƂ�����B���āA�؎��̔w��ɗ�����̔]�g�ɁA���ꂪ�o�����A�t�̔]�g�ɂ������ɗ��ꂪ�o���B���̎��؎��͎E�C���������Ƃ����B�؎��̔����͒��ϔ]�̉E�]�ɋ����o�Ă���B���ŁA�v�l���i�鍶�]�̊��������܂�A�C���悤�ƈӎ����A�C�����u�Ԃɂ͉E�]����S�̂ւ����g���L����A�����鍂��̔]�����g�������o�Ă���B���g�͍��T���ґz��Ԃ̎��ɏo�₷�����A�X�v�[���Ȃ��ŔO��������u�Ԃɂ������ł�]�g�ł���B���̒���A�؎��̔]�g�͂܂������Ȃ������悤�Ɍ��̕��R���ɂ��ǂ邪�A����ꂽ����̔]�g�͏Ռ����痧���ꂸ�A�傫������Ă���B�i�w�C�Ƃ͉����x�A����חY���A�m�g�j�u�b�N�X�j
�@���Ă������A���͒����ɉ���N���̗��j������ƌ����Ă���C��p�������N�@�═�|�́A���̕� �����A�g�����e�B�X����i���ɃA�g�����e�B�X�Ō�̑�V���l�탂���S���l�̎���j�ɂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�������A����̒��t�܂ł͕a�C�Ƃ������̂͑��݂��Ȃ������B�G�[�e���̂����܂��P�Ȃ�͈ȊO�̗͂ɐG��Ă��Ȃ���������ł���B���̌�A�G�[�e���́A�A�X�g�����̂����S���������āA�������A�a�C���Ăԉ\�����o�Ă���B���̂悤�Ȏ��A�ނ�͎��Ît�Ƃ��čs��ς҂���A�C�̎��Â��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ��낤���B�ނ炪�����͂Ƃ��Ă� �u�G�[�e�����C�v���߂�������Ȃ����Ƃ͎��̃V���^�C�i�[�̋L�q������f����B
�@
�u��V���l��A�����S���l�̊Ԃł��v�Ҕ\�͔͂��B�����B�������ނ�̒��ɂ́A��܁A��Z���l��� ����y���ɍ��������ŁA��葁���̈��l��́A���ɑ�l���l��̏��������c�����Ă����B�ނ�͋L���ɑ��銴��ɒ����Ȃ܂܂ɂ������B�����Ă��̂��ߔނ�́A�ł��Â����̂��܂��ł������Ȃ��̂ł���A�܂��v�Ҕ\�͂ɑ��čł��悭�������肤��Ƃ̊m�M�ɓ��B�����B�ނ�������͂ւ̎x�z�������Ă����͎̂����ł��邪�A�������ނ�̓��Ɏv�Ҕ\�͂Ƃ��Ĕ��B�������̂͂܂��A���̐����͂̎��R�I�͂̊�������ۗL���Ă����B�m���ɔނ�͐����ւ̗͂������Ă͂������A�����������͂ɑ��闦���ȐM�S���������Ƃ͌����ĂȂ������̂ł���B���̗͔͂ނ�̐_�ƂȂ�A���ׂ̈ɔނ�͎��琳�����ƍl�������Ƃ͉��ł��s�Ȃ����B���̂��ߗאڂ������l��ɂ́A�ނ�͂��̔閧�̗͂ɜ߈˂��ꂽ���̂��Ƃ������A�܂��ނ�͖ӖړI�M���̂����ɁA���̒��ɐg��C���Ă��܂����B�A�W�A��[���b�p�̏��X�Ɍ�����ނ�̌���́A���̓����̑��������Ď����A�܂������ł������Ă���B�v�i�w�A�[�J�[�V���N��L���x�A��R�͖����A�[�� �p����j
�@
�@���̃A�g�����e�B�X�Ō�̎���̃����S���l���������S���������͂Ƃ́A�C�̌`�Ō������鐶���� �̗���A�G�[�e���̗���ł͂Ȃ��������B�������A�C�ɂ��e���Ƃ������Ƃł́A���̉e���W�͎��ÓI�Ȃ��̂���ł��Ȃ������낤�B���݂ɂ�������悤�ȁA���������������e���W�����̍��ɂ��������ɈႢ�Ȃ��B�ȉ��ɂ��̗l�q��`����V���^�C�i�[�̕`�ʂ��Љ�āA����c���I���ɂ���B
�@
�u�����̎d�������Ă͑S���قȂ���̂������ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B����̔��f�͂ɑi����悤 �Ȉӎv�`�B�̎d���́A�A�g�����e�B�X����̐l�Ԃɂ͑S���Ȃ������̂ł��B�ڂ��肵���쎋�\�͂��c���������̎���ł́A�ӎv�̓`�B�͈ӎ����̉e����l����l�֓`����Ƃ�����������{�������̂ł��B����ɂ��ڂɂ���̂́A���܂��܂ɘc�߂�������ꂽ��Y�Ƃ������`�ł����Ȃ��̂ł����A�����͂܂����ꂪ����ɍs�Ȃ��Ă����̂ł��B�����A����͂����̈Î��A�l����l�Ɉӎ����œ���������e���ł��āA����͑���̍��̎^�������߂�悤�Ȏd���ł͂܂��Ȃ������̂ł��B�A�g�����e�B�X�����`���Č��܂��ƁA��X�́A�����̐l�Ԃ̐S�Ɉ���C���[�W�A���銴�o���N���N����A����Ɏ���̈ӎu���s�g���悤�Ǝv�����Ƃ���A������p���A���̑���̐S�ɋy�ڂ��ꂽ�l�q��������܂��B���̎�̉e���͂͂��ׂċ��͂������̂ł��B�����āA���̂悤�ȉe���͂��Ƃ߂悤�Ƃ����ӎu�����������̂ł��B����ɂ��F�߂���̂́A���̂ق�̖��c�ł�������܂���B
�@�����̈���l�Ԃ��A�ʂ̐l�Ԃ����߂���ʂ肩����A�������̓���̓����������Ƃ��l�����������B���̓�����������ꂽ�l�Ԃ̕����ق�̏����ォ���������ŁA�����ɂ��̂��ׂĂ�^���������Ȃ�悤�ȍ�p���A���̓������琶�����̂ł��B����ɂ��ł́A���̍�p�����c���́A����l�������т�����ƁA����������ʂ̐l�������т��������Ȃ�Ƃ����悤�Ȍ`�ł����c���Ă��܂��B��i�S�W112 Das Johannes-Evangelium�S.102�103�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�W�̖`���ɖ߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�͋C �Œ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڎ��y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@ �@