�V���^�C�i�[����̔w�i�W��ځ@��@
�~�q���G���E�G���f�ƌ�
�i�t�F���^�����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�X�W�V�N�U���Q�T���j
�~�q���G���E �G���f�ƌ��@�@
���^����
�@
�@�G���f�����Ɖ����[�����ƂɊւ��ẮA�������̈Î�������܂��B�G���f�̊G�{�Ɂw�X�̌��҃q �_�G�����x������܂��ˁB���̒��ŁA��l���̏ۃq�_�G�����́A�S�̒��Łu���I�v�Ƌ��т܂��B��Ɍ��̂��Ƃ��l���܂��B
�@
�@�u�d�d�߂��ꂽ�悤�ɍl���Â���̂������B�����I���ƁB�ق��̂��Ƃ͉����l���Ȃ��B�����I�� �������ꂾ�����B����͂���́A�s��Ȏv����������B�v�i��쐟�q��j
�@
�@���ꂩ��A�w�����x�̑�͂ŁA�W�W�����[���q�F����b���܂��ˁB���̒��Ń����P�����E�ɑ��� �o�������@�̋����o�Ă��܂��B���ƂŃ����P���A�s���̏�Ԃ�����̂āA���E�ɍ~��܂��B���̉��E�̃����P�����グ��ƁA��ɕ���ł����F�̋��A����͂� �͂�A���̃C���[�W�ł��ˁB�ߋ��̃C���[�W�Ƃ������܂��B�����āA�q������́w�G���f�ƌ��x�̒��ŁA�G���f�͂����q�ׂĂ��܂��B
�@
�@�u���́A���Ƃ����l�ԂɂƂ��ďd�v�Ȃ̂ł��B�������̉e�����ƂĂ������Ă���Ɗ����邩�� �ł��B���Ƃ��Ζ����̖�A���͖���Ȃ����Ƃ������B����ǂ��V���̂���́A���������ɂ����Ē��q��������܂���v�B
�@
�@���̖{�̒��ł́A�G���f�����̖���������\�����鎞�v�������Ă���G�s�\�[�h���o�Ă��܂��B�G ���f�����Ɖ����[�����ƂɊւ��ė��������̂͂���ŏ\���ł��傤�B
�@�Ƃ���ŁA�A���g���|�]�t�B�[�͑O�\���グ�܂����悤�ɁA�����z�I�Ȃ��́������̖{���Ƃ��Ă� �܂��B����ɑ�����̂Ƃ��āA�����I�Ȃ��́����l���邱�Ƃ��ł��܂��B�ȉ��\���グ�邱�Ƃ́A�V���^�C�i�[��A�A���g���|�]�t�B�[���q�ׂĂ��邱�Ƃł� �Ȃ��A�����g�̓��@�Ɋ�Â��Ă��邱�Ƃ����f��肵�Ă����܂��B
�@�G���f�ɂ͂������A�����z�I���ȗv�f������̂ł����A�����Ł����I���ȗv�f���������Ƃ�\�� �グ�Ă��������Ǝv���̂ł��B�Ȃ��A�����ŁA�����z�I�Ȃ��́��Ƃ������I�Ȃ��́��Ƃ����Ă�����̂́A��ɏo����ۂ̑��z�⌎�Ƃ��֘A�����čl���Ă��� ���B�������A�����I�ȓV�̂Ƃ��Ă̑��z�⌎�ł͂Ȃ��A����炪�C���[�W��ے��Ƃ��ĕ\�킵�Ă��鐸�_�I�ȓ����S�̂��L����Ƃ��āA�����Ă��܂��B���Ƃ� �A�����z�I�Ȃ��́��̓����ɂ́A��ʂ���Ɠ����܂��B��͖��邳�A�������A�����đ��z�̋K�̗͂͂ɐg���䂾�˂�f�����A�f�p���Ƃ��������̂ł��B ��߂́A���������͂�����Ƃ炵�o���āA���߂��߂������C��Â��_���r����Ɩ��͂ł��B���m�ȔF���́A���̗͂Ɗ֘A���܂��B�A���g���|�]�t�B�[�́A�� �̓�̖ʂ������z�I�Ȃ��́��Ƃ��Ĕ����Ă��܂��B�A���g���|�]�t�B�[�́A���邳�������Ă��܂��B�܂��A�����I�Ȃ��́��́A���z�I�ȑf�p���ɂ͂Ȃ����܂� �����Ă��܂��B��Ȃ�ł͂����Ȃ��̂ł��B���������͂̉e�����ɂ���l�́A���z�I�ȋK�͂�������R�ɂȂ낤�Ƃ���Փ��������܂��B���̍s����ɂ́A���z �̖��邳�A�������͂Ȃ��B����ŁA�ꍇ�ɂ���ẮA���Ȃ̗͂����ɗ�������������܂ꂽ��A�t�ɋ����ɗ����������肷��킯�ł��B
�@
�@�����I�Ȃ��́��B�@�|�@�ŁA�B�����A�����I�`�ہA���܁A�����A�����@�@�@
�i���j
�@���́����I�Ȃ��́��ƁA�����z�I�Ȃ��́��̓�̗v�f�w�̐��E�������Ă��܂��B����̐��E �ł���A�����ł��B�i���Ă�͑��z�I�A�����܂Ђł��͌��I�ƌ������Ƃ��邪�A�~�߂�j�������A����́A�F����䑶�m�Ȃ������ł��ˁB�����P��u���� �V����A���g�[�ȂǁA���㕶�w�ɂ́����I�Ȃ��́��������ł��B�}�������̂悤�ȃV���{���Y���̎���ǂ܂ꂽ���Ƃ́A������ł����B�ے����Ƃ�������̂� ���B���T�������͕̂���ɂ����ł����H�@���ꂪ���銴�o�́A�����I���Ȃ��̂ł��B�����I�����o�̎�����́A���ڂ댎�̂悤�ɁA�����̂܂��ɂ���A���� ��̑�C�������Ă��܂��B�ے��I�Ȏ���́A���̔ނɌ������Ĕ�э���ŗ���ƁA��C�ɐg�����₷���ꐯ�̂悤�ɁA���̑�C��ʉ߂����u�A���F��F�ʂ� ���܂��B���̎�ϓI�ȉ��F��F�ʂ��A�ނɂƂ��ĉ��l�ƂȂ�̂ł��B
�@
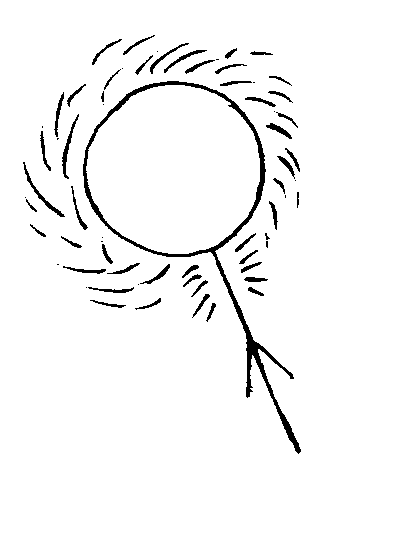
�@
�@
�@
�@
�@���ꂪ�A�����z�I���Ȋ��o�̎����傾�ƁA�����ł��B
�@
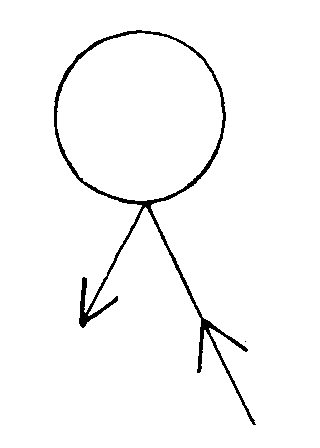
�@
�@
�@�ނ͒�ӂ��Ȃ��A�������肵���l�ł����A��C���Ȃ��B�V���{���b�N�Ȏ���́A���m�̂悤�ɁA�| ���ƂԂ����Ă͂˕Ԃ�A�Ӗ��s���ƂȂ�܂��B��������z�I���Ȑ��E�ɂ��A�t�@���^�W�[�͂���܂����A������́A�����I�E���R�I�ȃt�@���^�W�[�ł��B �ȑO�\���グ�����z���́��ł��B���z���́��̍L����ɂ͂Ђ�������Ȃ����w���A����̂ł��B�A���g�i���E�A���g�[�Ȃǂ́A�a�I�Ȃ��̂��킴�ƚn�D����悤 �ȑޔp�I�ȕ��w���A���z���́��̊O�ɂ��遃���I���ȕ��w�ł��B
�@�G���f�̏ꍇ�́A���́A�����I���Ȋ��o�Ɓ����z�I���Ȋ��o�̗���������Ǝv���܂��B�ނ̍�i�� ���Ɍ��������镶���ᔻ�I�Ȋ፷���́A�������E����ڂ����ނ��܂��Ƃ���A�����z�I���ȔF���̕�������ттĂ��܂��B�܂��A�Љ�O�w����A�ݕ��_�ւ̊� �S���A�Љ��o�ςƂ����������E�̍L���������Ɏ��߂悤�Ƃ���_�Ł����z�I���ȕ����������Ă��܂��B����������ŃG���f�́A�w�͂Ă��Ȃ�����x�ɏo�Ă� �遃�t�@���^�[�W�F�������̂悤�ȕʐ��E�A���\���E�ɋ��������������Ă��܂��B�G���f�̊G�{�w�������E�������E�o�����x�̘b�́A���������Ή������������� ���ɓW�J���Ă����܂��B���̃t�@���^�W�[�̓������́A�����̂�����ɉ������Ƃ��遃�z���́��I�Ȃ��̂Ƃ͂����܂���B����͂�͂�A����z�͓I���ȒE���� ��ƂȂ��Ă��܂��B����z�́��́A���z�I�ȋK�͂����E���悤�Ƃ���͂ł�����܂��B����́����I���ȗ͂̉��ɂ���܂��B�G���f�ɂ́����I���ȗv�f������ ����̂ł��B�������A�w�͂Ă��Ȃ�����x�ŁA��l���̃o�X�`�A���͌������E�֖߂��Ă��܂��B�G���f�́A���Ȃ̓��ɁA�����I�E��z�I���Ȃ��̂������Ȃ���A �������A�������E�։�A����Ƃ��錒�S�Ȋ��o�A�����z�I���Ȋ��o�����A���킹�����Ă���킯�ł��B
�@���āA�G���f�͖����������ɉe������Əq�ׂĂ��܂����A��́A�����l�Ԃɉe����^����ȂǂƂ� �����Ƃ��A���肦��ł��傤���B�����̎�����ʂɊ�����Ƃ����ƁA�̂���т������Ă���T�j�Ȃǂ�A�z���܂��ˁi���O�A���j�B����͏�k�ł����A���͍� �߂̉Ȋw�ł��A���̖����������l�Ԃ̔]�ɉe����^���Ă��邱�Ƃ��ؖ����ꂽ�̂ł��B
�@���ꂩ�炢�����܂����b�́A�w���E ���{�l�̔]�x�A�p�c���M���A��C�����X���ɏo�Ă�����̂ł��i���j�B�p�c���́A������Ȏ��ȑ�w�̓�����������A���o�@�\�������勳���ŁA��w���m�ł��B
�@���āA�l�Ԃ̔]�́A�قƂ�ǂ̐l���E�]�Ŕꉹ���A���]�Ō��ꉹ���Ă��܂��B
�@
![�E�]�ƍ��]�̋@�\����](../../../gif/kyoikunohaikei8-2-3.gif)
�@�@�@�@�@
�@
�@
�@
�@���Ƃ��A���y�͉E�]�A���t�͍��]�ŕ����Ă���킯�ł��B�t�̐l�����܂����A���̏ꍇ�́A���� ����̘b�����E�t�ɍl������������ł��B���ꉹ�Ɣꉹ���A�]�̕ʁX�̔����ŕ���������Ƃ����������̂ɂ́A�ς�肠��܂���B�ȉ��̘b�ł́A�E�]�� �ꉹ�A���]�Ō��ꉹ���Ƃ����A�ł���ʓI�ȏꍇ�Ƃ��čl���܂��傤�B
�@���̔]�̖������S�̋@�\�𗘗p���āA���X�Ɛ������Ƃ��������Ă����̂ł��B���Ȃ�ŋ߂̂��Ƃ� ���B���̖{���́A��㔪�ܔN�\���ł��B
�@�܂��A���{���ꍑ��Ƃ���l�Ɍ����锽���ł����A���Ƃ����]��g�߂�ƁA�ꉹ�� �̈悪�E���獶�ֈڂ�܂��B
![�E�]���獶�]�ֈړ�](../../../gif/kyoikunohaikei8-2-4.gif)
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
�@�^�o�R���i���Ă��A�����Ȃ�܂��B�v����ɁA���炩�̎h���ŁA���̕ω����N����킯�ł��B�Ƃ� �낪�A���̂悤�Ȏh������ؒf���Ď������Ă��A�K���I�ɓ����ω��̋N���鎞����������܂����B���ꂪ�Ȃ�ƁA�����A�V���A�㌷�A�����̌��̎��������̂� ���B���̌��ۂ́A���{���ꍑ��Ƃ��Ȃ��l�ł������ł����B�������āA���̖����������A�]�ɉ��炩�̎h����^���Ă��邱�Ƃ����������̂ł��B���̔����͈� �㔪�l�N�̂��Ƃł��B�������Ԃ́A�����ŘZ�E�܁`�\�ꎞ�ԋ��B�V���ŎO�E�܁`�l�E�����ԁB�㌷�̌��œ�`�O�E�O���ԁA�����̌��ň�E�O�`��E�Z���Ԃł��� �������ł��B�G���f�������̎����ʂȊ���������Ƃ����Ă���̂��A���Ȃ����r�����m�ł͂Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�@�V���^�C�i�[�́A���̖��������̉e���Ɋւ��ẮA�ǂ������Ă���ł��傤���B�ނ́A���̖����� ���̉e���́A���ړI�Ȍ`�ł͂��͂�A����ɂ͂Ȃ��Əq�ׂĂ��܂��B���̓_�A�܂��H���Ⴂ�܂��ˁi���O�̒��ɁA�����j�B�ł��A�ӂ��̐l�̏ꍇ�A���ʂ� ���ו������Ȃ��Ɖe����������Ȃ��킯�ł����A�ӎ��ɏ��Ȃ��̂ł�����A�V���^�C�i�[�̏q�ׂĂ��邱�Ƃ́A���̌���Ő������̂�������܂���B���o���x ���A�V���^�C�i�[�̑z�肵�Ă������̂�肸���Ɛi��ł��܂����A�Ƃ������Ƃł��傤���B
�@���Ƃ̊֘A�͂Ȃ��ł����A��قǐ\���グ�܂����A���{���ꍑ��Ƃ���l�̓��ꐫ�ɂ��A�����[ ���_�����X���������܂��B����͂����A�\�N�قǑO�A�������҂��w���{�l�̔]�x�i��㎵���N���j�Œ����̌`�ɂȂ��Ă��܂����A�V���Ȃǂł� �Љ��܂����̂ŁA�䑶�m�̕�������ł��傤���A�L���Ȃ̂́A�R�I���M�̖������ǂ��������ł��B���{�ꂪ�ꍑ��̐l�́A�R�I���M�̃��[���[���[�Ƃ��� �������A�ꉹ�Ƃ��ĉE�]�ŕ����̂ł͂Ȃ��ɁA���ꉹ�Ƃ��č��]�ŕ����Ă���Ƃ��������ł��ˁB���Ƃ��A���Đl�͓����R�I���M�̖������A���y��G ���Ɠ����悤�ɁA�E�]�ŕ����Ă���̂ł��B���̉��A�g�̉��A���̉����A�R�I���M�̖����Ɠ����悤�ɕ����Ă��邱�Ƃ�������܂����B�ł�����A���R�̉� ���A���{���ꍑ��Ƃ���l�ɂƂ��ẮA�����łȂ��l�����A���Ƃ��Ή��Đl�����Ƃ́A��������G��^���Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��B����ΐl�̌��t���悤 �ɕ����Ă���킯�ł�����A�N�����Ȃ��ǓƂ̒��ŁA���̐���A�g�̉�����A���̊��G�Ƃ������C�z�́A���{���ꍑ��Ƃ���l�ƁA���Ȃ��l�Ƃł́A�� ��������Ă���ł��傤�B
�@�܂��A�M�y����������������܂��B���Ƃ��A�Ղ�A�O������A�ڔ��̉����ƁA������� �]�ŕ����Ă��܂��B�t���[�g�Ȃ�E�]�Ȃ̂ł����A�ڔ����ƍ��]�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���Đl���ƁA�����S���A�E�]�ŕ����킯�ł��B�y�킪���Ȃ̂ł��B�� �ʼn��t�������B���@���f�B�́u�l�G�v�́A��͂荶�]�ŕ����Ă��܂��̂ł��B�܂��A�O����w�K�҂ɂƂ��Ă̓V���b�L���O�Ȃ��Ƃł����A�O�����ǂ�A�� ������A�b������A�������肵�����ƁA�ꉹ�����]�ŕ����Ă��܂��t�]���ۂ������ԁA�c���Ă��܂������ł��B�O���Œ����ԉ߂����Ă�����Ȃǂ́A������ ���Ƃ����܂��B��w�̋�������ȂǁA����ɉ��x���O����ɐڂ���l�́A�قƂ�ǂ����Ƌt�]���������Ȃ킯�ł��B�Ƃ��낪�A�O����Ɛڂ��Ȃ���A�m�y�� �����ƁA���̋t�]���N����Ȃ��B�M�y���ƁA���߂������ł��B�M�y�͌��ꉹ�̑��ŕ����Ă��܂����߁A�t�]���ۂ����߂����Ȃ̂ł��傤�B
�@�������A���{���ꍑ��Ƃ���Ƃ����Ă��A�ǂ������ꍇ�A���{�ꂪ�ꍑ��ƂȂ��Ă���Ƃ����� �̂ł��傤���B���{�ɐ��܂�ē��{�������ׂ��Ă����̂��A���N����A�A�����J�ɍs���āA�p������S�ɂ���ׂ���悤�ɂȂ�����A�ǂ��ł��傤���B���� ���͋t�ɁA�A�����J�ɐ��܂�āA���{�ɗ��āA�p������{��������ɂ���ׂꂽ��A�ǂ��ł��傤���B�p�c���́A���������o�C�����K�����A�O��I�ɒ��ׂ܂� ���B����ƁA�o�C�����K���̏ꍇ�A�l�ɂ���āA���{��^�A����{��^�ɕ�����Ă��܂��܂����B�����Ŋe�l�̐������ׂĂ݂܂����B���̌��ʁA���̐l���� �{��̊��ɂ������N�߂��A����I�v���ł��邱�Ƃ����������̂ł��B���Ȃ킿�A�Z�ˍ����甪�ˑ�̊ԂɁA���{��̊��ɂ������ꍇ�ɁA��́A���{���ꍑ ��Ƃ���l���L�̔������N�����悤�ɂȂ邱�Ƃ����������̂ł��B�O���ɐ��܂����Ă��A���̊��Ԃ������{�ɗ��Ă���A��̔������N�����悤�ɂȂ�킯�� ���B�t�ɁA���̊��Ԃ����O���ɍs���Ă���A�����Ȃ�Ȃ��ŁA�O���l�^�ɂȂ�킯�ł��B�V���^�C�i�[����������ł��m���Ă���l�́A���̘Z�ˍ����甪�ˑ� �܂ł̊��Ԃ��A�d�v�Ȏ����֊��ł��邱�ƂɋC�t���܂��ˁB�G�[�e���̂��A�G�[�e����킩�琶�܂�o�鎞�ł��B�G�[�e���̂����܂�o�Ă������̌���� ���A����ʂŌ���I�Ȃ��̂ɂȂ�Ƃ������Ƃ́A���������͂������Ă���̂ł����A�����ŃV���^�C�i�[�̐��Ƃ̔�r�ɐ[���肷�邱�Ƃ͎~�߂܂��傤�B
�@���āA���̉��̕�����肩��A���ɂ������ׂ����Ƃ��������Ă��܂����B���x�̘b�́A�w���E ���{�l�̔]�x�̕��ł��B
�@�܂��A�������̉�b�̐��́@100�w���c�ȏ�̐U�����������Ă���Ƃ����Ƃ��납��n �߂܂��傤�B�w���c�Ƃ����̂́A��b�Ԃ̐U�����ł��B100�w���c�́A��b�Ԃ�100��U�����Ă��鉹�ł��B�w���c���������Ȃ�ƁA�������ɂȂ��Ă����� ���B�l�Ԃ̉�b����100 �w���c�ȏ�ł́A����͍��]�A��͉E�]�ƁA��ʓI�ȕ����������Ă��܂��B�Ƃ��낪�A99�w���c�ȉ��̔ꉹ�́A�t�ɁA������i�鍶�]�ŕ����Ă��邱 �Ƃ��A�܂�������܂����B���̌��ۂ́A���{�l�Ɍ���܂���B�Ƃ��낪40�w���c�A60�w���c�A80�w���c�̂Ƃ���ŁA���]����E�]�t�]���邱�Ƃ������� �ꂽ�̂ł��B���Ƃ��A40�փ��c�̏ꍇ�A39�ł�41�ł����߂ŁA���傤��40�w���c�ŁA�����Ȃ�̂ł��B100�w���c�ȏ�ł��A40��60 �̔{���̂Ƃ���ŁA�E�]���獶�]�t�]���܂����B
�@
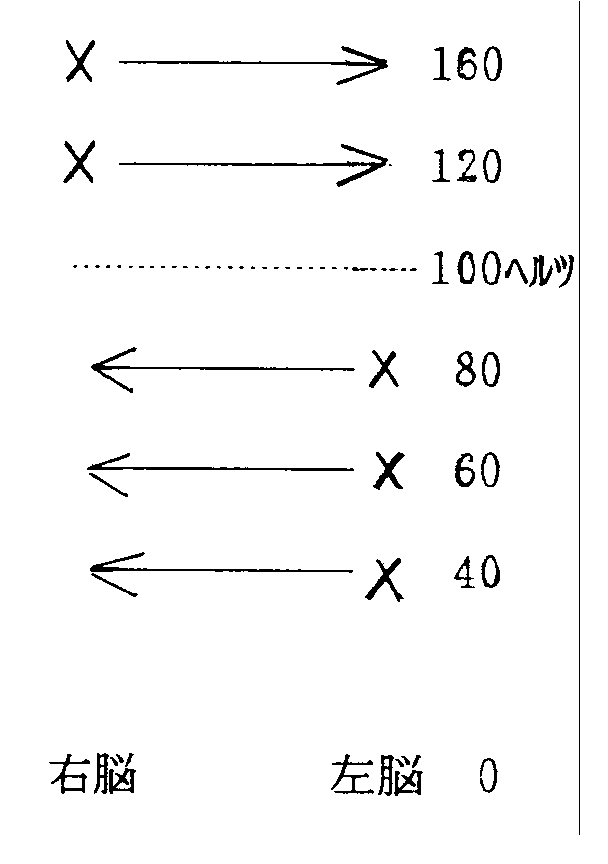
�@
�@
�@
�@�����܂ł́A�Ӂ[��A�������ˁA�Ƃ����Ƃ���ł��傤���A���̂��Ƃ��s�v�c�Ȃ̂ł��B���́A 40�A60�Ƃ������A�����Ă��̔{���́A��ԓI�ɂ��Ӗ����������̂ł��B���Ƃ��A40�R�̌�����Ȃ���A�����ƁA�������Ă��܂��B40�R�Ƃ��A 60�R�Ƃ��̌�����Ȃ���A1010�w���c�̎��������ƁA�E���獶�ցA�����Ă���]���ڂ��Ă��܂��̂ł��B
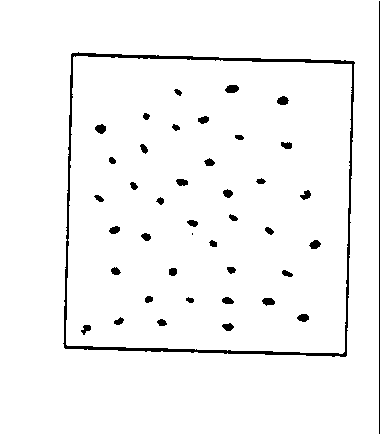
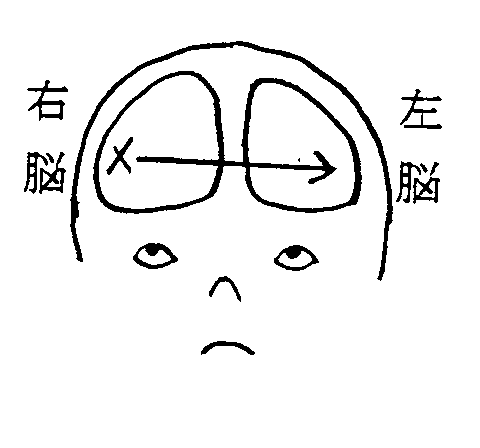
�@�@
�@
�@
�@����͋����ׂ����Ƃł��B39�R�ł�41�R�ł����߂ŁA���傤��40�R�Ŕ������Ă��܂��̂� ���B��u���邾���ł�����A�����������Ȃ��̂ł��B�������A40�Ƃ�������F�����A�]�ɓ��ʂȎh�����Ă���̂ł��B
�@�����őz���������܂������܂��ƁA���Ƃ��Ό�̑ǂŁA�Տ��40�̌�����Ȃ���A41�� �ڂ��l���Ă���l�̓��̒��́A�����Ԃ�ł͂Ȃ����ƂɂȂ�܂��B61��ڂ������ł��B��ł�����A���ł��ˁB���͂��Ƃ��ƗL���ł�����A����� ���������ł��傤���B�܂��A���Ƃ��Ύ���40�l�̃N���X�Ŏ��������Ă���Ƃ��܂��B�����p����z��A��ĂɊ��̏�ɂ����݂���ŁA�����������d�̏�ɂ��� ���̎����40�Ȃ�ԂƁ@�|�@�@���̓��̒��ł͔������N�����Ă��܂��B������39�l���ƈ��S���Ă�����A�����̉��̕ǂɋ��Ȃ����܂��܂����āA�Ђ傢 �ƌ������q�Ɏ������f���Ă��܂��A39�{�P��40�ƂȂ�A�����b�ƂȂ�����i���O�A���j�B�܂��A����͔�����k�ł����A�����͖{���̂��Ƃł�����̂� ���B
�@�����āA����ɂ����ƁA��������͐M�����Ȃ����炢�̂��ƂȂ̂ł����A���q��40��A60�� ���������ʁA���Ɋ܂�ŁA��������������ƁA��͂蔽�����Ă��܂��̂ł��B���̕����̉��w�I�����ɂ͊W����܂���B���̕����̈ꕪ�q���̗z�q�ƒ��� �q�̑��a�ł��镪�q�ʂ��A40��60�̎��ɔ�������̂ł��i���O�A�����̐��j�B�ʏ�̊��o�ł́A���q���̗z�q�{�����q�̐��̔F���Ȃ�Ă��Ƃ́A��Εs�\ �ł�����A����͂ق�Ƃ��ɕs�v�c�Ő����I���o�ŔF�����Ă���Ƃ��������悤������܂���B���̂悤��40��60�Ƃ������́A�����l�Ԃ̕����I���݂̂��� ���Ɛ[���֘A���Ă����{�I�Ȑ��炵���̂ł��B
�@���āA�������Ȃ��炱���܂ł͂���ΑO�u���̘b�Ȃ̂ł��B���́A���w���c���Ƃǂ��Ȃ�Ƃ����� �̎�������A��ςȂ��Ƃ����������̂ł��B��́A���̖��������̉e���̔����ɂ�����Ƃ����Ȃ������ł��B
�@���傤��40�A60�A80�w���c�̉������A�����Ă���]���A�ʏ�̏ꍇ�Ƃ͋t�]���Ă���� �������Ƃ́A�\���グ�܂����ˁB�Ƃ��낪�A����ȊO�ɂ���������w���c�����������̂ł��B�������A���ꂪ���̃w���c�ł͂Ȃ��A�l�ɂ���Ă܂��܂��� �����B���̗�O�I�Ȕ����ɋK���������o���̂ɂ͓�N�������������ł��B�����āA��㔪�O�N�̏H�A���̗�O�I�ȃw���c�����A���m�ɂ��̐l�̖��N�߂̔{���� �Ȃ��Ă��邱�ƂɋC�t�����̂ł��B���Ƃ���21�˂̐l�́A21�w���c�A42�w���c�A63�w���c�A84�w���c�Ŕ������܂��B����ł́A�����l��21�˂��� 22�˂ɕς��ƁA�ǂ��Ȃ邩�ƁA���ׂĂ�������A���傤�ǒa�����ɁA��������w���c����21����22�A42����44�A63����66�ւƕς�����̂ł� �i���O�A�����̐��j�B��̌덷�����Ă��A�a�����������甼���ȓ��Ɏ��܂�Ƃ����܂��B����ɒa�������ꎞ�ԍ��݂ŏW���I�ɒ��ׂ����ʁA���̕ω����A���\ ���Ԃ̂����ɋN�����Ă���炵�����Ƃ܂ŕ�����܂����B
�@�����A����͂ǂ��������Ƃ��Ƃ����܂��ƁA�l�Ԃ̔]�́A�n�������z�̂܂��������ƈ������ ���]�𐳊m�Ɋ��m���Ă���A�Ƃ������ƂȂ̂ł��B������A�����̈���ł͂Ȃ��A���܂ꂽ���̑��z�̈ʒu�𐳊m�Ɋo���Ă��āA���̈ʒu�ɑ��z���߂��Ă��� �ƁA�w���c�̍��݂��ς��킯�ł��B���z�̈ʒu�ƈ���Ɍ����܂����A�ڂ����́A���z�̉�����̈ʒu�Ƃ������Ƃł��B����͒n�w�̒m�����K�v�ɂȂ��Ă��܂� �ˁB�������A����Ȃɓ�����Ƃł͂���܂���B���z���V��������������Ƃ����̂ł����A�����\��{�Ƃ����̂̓V���w�̕\���̎d����p����A��̓I �ŕ�����₷���Ȃ�܂��B�P�v���[��n���[�Ȃǂ̎���ɂ́A�V���w�Ő��̌o�x��\�����́A�����\��{�̉����̉��x�ł��������̂ł��B���Ƃ��A���̐}���� �ĉ������B
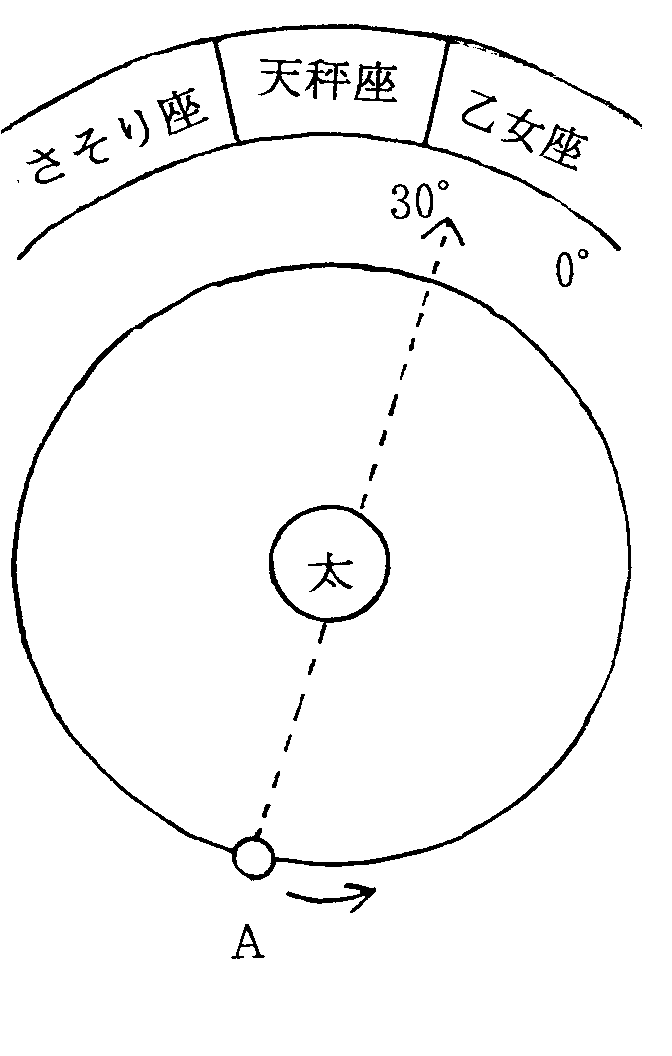
�@
�@
�@
�@�n���͑��z�̂܂������邮��܂���Ă��܂����A���z�ƍP������́A�قƂ�Ǔ����Ȃ����̂� ���Ȃ����Ƃ��ł��܂��B�n�����`�̈ʒu�ɂ��鎞�A�������܂ꂽ�Ƃ��܂��B���̎��A���z�͂`�̒n�����猩��ƁA���Ƃ��Ή�������w�i�ɂ��Ă��܂��B���z���� �鉩���ɂ��鐯����12�ɓ��������A���̈���������ł�����A�����30�x�܂ł���܂��B360 ����12��30�ł��ˁB���̉�������29�x�Ƃ��܂��傤�B���̔]�́A���̉����\��{�̈�A��������29�x�a�Ɠ����ɁA���z�̈ʒu�Ƃ��č��ݍ���ł� ��̂ł��B�����Ė��N�A���z�����̈ʒu�ɗ���a�����ɁA��������w���c���̕ω����N�����킯�ł��B����Δ]�́A�ʐ^�̂悤�ɁA���a���̑��z�̓V����ł̈� �u���ʂ��Ƃ��Ă���̂ł��B����͎��̍l���ł����A���̇��ʐ^���ɂ́A���z�̑��ɂ��A���z�n�̏��f�����ʂ��Ă��Ă��A���������Ȃ��Ǝv���܂��B���z�̏ꍇ �̂悤�Ɍ��o�����i���J������Ă��Ȃ������ŁB
�@���ہA�V���^�C�i�[���A�S�W��15���̒��ŁA���̂悤�Ɍ����Ă��܂��B
�@
�@�u�]�̍\���S�̂��A�����̎p�Ŏʐ^�ɎB�邱�Ƃ��ł��A�����ɂ��ׂĂ̍ו���������Ƃ���ƁA�� �̎ʐ^�́A�l�ɂ���Ă��ׂĈقȂ������̂ɂȂ�܂��B�����āA����l�Ԃ����܂ꂽ�u�ԂɁA���̔]���ʐ^�ɎB��A���ɂ��̐l�Ԃ̐��a�n�̐^��ɂ���V������ �B�e�����Ƃ���ƁA���̓V���̎ʐ^�́A���̐l�Ԃ̔]�ƑS���������̂ƂȂ�܂��v�B
�@
�@����́A�܂��ɐ萯�w�̃z���X�R�[�v�̍l�����݂����ł��ˁB�ł��A�͂����茾���Ă����ׂ����� �́A�V���^�C�i�[�́A�萯�w�̂悤�Ȍ���_�I�ȍl�����ɂ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�V���^�C�i�[�́A�l�Ԃ̍s�ׂ����̐��ɍ��ݍ��ނ��Ƃ̕����d�����܂��B �Ɨ������ӎu�ɂ��s�ׂ����邩�炱���A�l�Ԃ͐i�����邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł��B
�@�ȏ�ׂ̂����Ƃŏd�v�Ȃ̂́A�F���Ɛl�ԑ��݂Ƃ����ĉ����Ă���Ƃ����_�ł��B�l���Ă݂�A �l�Ԃ͉��\���N���̐i������ɁA���̑��z�n�̒��ōs�Ȃ��Ă����킯�ł�����A�F���̃��Y�����̂̑g�D�̒��ɑg�ݍ��܂�Ă��Ă��A���̕s�v�c������܂��� �ˁB�l�Ԃ͉F���Ɩ��W�ɑ��݂��Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��B�l�Ԃ͉F���S�̂̉c�݂���Ǘ��������݂ł͂Ȃ��̂ł��B
�@����l�̐����́A�l�H�̖�����̉��Ŗ�x���܂ŋN���Ă��āA���Ɩ邪�t�]���Ă��܂��Ă���A�� �z�̃��Y����n���̃��Y������͂���Ă��܂��Ă��܂��ˁB����A���̑��݂ֈˑ����邱�Ƃ��~�߁A�Ɨ����Ă������Ǝ��̂́A�V���^�C�i�[���l�Ԃ̐i���̃v ���Z�X�ƌ��Ȃ��Ă�����̂ł��B�������A�����A���̌���̐�������A�s���S�Ȃ��̂����܂�Ă���Ȃ�A����x�A�l�ԑ��݂ƉF���Ƃ̑Ή��W�ɖڂ��������� ���Ƃɂ��A�Ӗ����o�Ă��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
�@���āA����Ŏ��̘b�͏I���ɂ��悤�Ǝv���܂��B
�@
�@
�`�F�h�C�c�ŃV���^�C�i�[�w�Z�̋����ɂȂ�ɂ́A�u�F���̏����v�̂悤�Ȃ��Ƃ��C�߂�̂ł����B
���F�s�����āA���_���E������Ƃ����Ӗ���������A���Ȃ��ł��B�����A�V���^�C�i�[���q�ׂĂ� �鎖���̕��́A����͂��ł��B
�`�F�u�F���̏����v�̂悤�ȍs��ς�ŁA���ۂɐ��_���E�������l�������ł��傤���B���F����� ������ł��B���������l�́A�T����͕�����Ȃ��̂ł��B���ۂɌ����l������ɂ��Ă��A����Ȃ��Ƃ��������ƐG��܂�����肵�Ȃ����Ƃ��s�̂����ł��� �Łi���O�A���j�B���[�[�t�E�{�C�X���A����C���^�r���[�ŁA�������Ƃ���A���̂悤�ɓ����܂����B
�a�F���l�b�T���X���ւāA����̂悤�ȕ����Љ�ɂȂ����킯�ł����A�A���g���|�]�t�B�[�̍l���� ������ɁA�ǂ̂悤�ɍL�߂邱�Ƃ��ł���ł��傤���B
���F���ꂪ�A�Ȃ��Ȃ��ɓ���̂ł��B�܂��A�l�ɍl�����������Ă͂����Ȃ��B�e���̎���̓��� ���狤���N�����Ă���̂�҂��Ƃ��K�v�ł��B����́A���Ȃ̐��E��������藣����Ă��܂��Ă���悤�Ɋ������鎞��ł����A�A���g���|�]�t�B�[ �ł́A�l�ԂƉF���̑Ή��W�����Ă���̂ł��B�l�Ԃ����F���A�܂�~�N���R�X���X�Ƃ����ꍇ�A����́A��F���A�}�N���R�X���X�ƁA���݂ɊW�������Ă� ��ƍl����̂ł��B
�`�F���R�Ƃ́A�ǂ��ł����B
���F���R�Ƃ��Ή����Ă��܂��B�������A���Ă̂悤�ɁA�������������������Ɏ��R�ɗn������� ���܂��̂ł͂Ȃ��A�Ɨ����������ۂ����R�Ƌ�������̂ł��B���a�̍l����������܂��ˁB
�a�F�t�H�������Ȃǂ́A�ƂĂ������[���āA���E�̍L������������悤�Ɏv���܂������A���������� �ʂ���A���g���|�]�t�B�[���L���Ă����̂́A�ǂ��Ȃ�ł��傤���B
���F����͗��z�I�ł��ˁB����œ����Ă�����Ȃ�A��������̍L���肪��Ԃ����Ǝv���܂��B�� �́A���߂́w�A�[�J�[�V���N��L���x����V���^�C�i�[�ɓ����Ă����܂����B���Ɂw�_��w�T�_�x���ɂƂ������ɓǂݐi�߂Ă������킯�ł��āA���ɂƂ��� �́A�_��I�ȓ��e����R�Ȃ������̂ł����B
�b�F����̂��Ƃ����o�Ă��邩�A���o�Ă��邩�Ƒ҂��Ă����̂ł����A���̐_�q�w�ƁA�V���^�C �i�[����́A�ǂ��Ȃ���̂ł����B
���F�l�q�w�ł��ˁB
�b�F�����A�l�q�w�B
���F�V���^�C�i�[������{���l�́A���̃A���g���|�]�t�B�[�A�l�q�w�̍l���������Ă���킯�ł��B
�b�F����ƁA�V���^�C�i�[����́A�A���g���|�]�t�B�[�̍l���ɓ����Ƃ������Ƃł����B���F�����A ����͑S���Ⴂ�܂��B�w�Z�́A�A���g���|�]�t�B�[�������鏊�ł͂Ȃ��̂ł��B��������Ă͂����Ȃ��ƁA�V���^�C�i�[�������Ă��܂��B�V���^�C�i�[�w�Z�́A �q���̐S�g�̌��S�Ȕ����ڎw���Ă���̂ł��B���炻�̂��̘̂b�͈���ɂ��܂������A����́A����̎��ۂ͏��c�����A�q������ɂ������肨�C���� �āA���͔w�i�̃A���g���|�]�t�C�[�̏Љ�ɂƂ߂�����ł��B�V���^�C�i�[����̎��ۓI�ȓ��e��w�j�́A�w����|�p�x�̂悤�Ȗ{�ɏo�Ă���킯�ł��B���� ���A��������̂܂܁A���̂悤�ɓ`����͍̂l�����̂ł��B���j��A�l�Ԃ̍\���v�f�̂悤�ȁA�F���I���ʂ̋������̂́A��l�̎���ɂȂ�A���Ȃ蒼�ړI�� �i���Ă����Ǝv���܂����A�q����O��ɂ���������e�̏ꍇ�͌|�p�I���ʂ������A�u�`�̂悤�Ȍ`���ł��`�����Ă������̂��A�ǂ����^��ł��B��������u�� ��v���A�g���������ƍl���āA�����̂�����Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�������ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ������A�Ǝv���܂��B
�c�F�C���̂��Ƃł����A��l�̏ꍇ�A���Ƃ��Β_�`���͎��䂪��������ǁA�q�����ƃA�X�g�����̂� �����Ƃ������ɂȂ��Ă��܂����A���̕ӂ��悭������Ȃ��̂ł����B
���F�����A���̗��R�̓V���^�C�i�[���q�ׂĂ���ĂȂ��̂ł��B��l�̏ꍇ�́A���̑O�̐����ňꉞ ������܂���ˁi�c����A���ȂÂ��j�B�q���̏ꍇ�́A���������������������A�Ƃ��������Ă���Ȃ��B�V���^�C�i�[�̐������Ȃ��ƕ�����Ȃ����Ƃ�����̂� ���B�q���̏ꍇ�́A�w����|�p�x�̉��K�̕��ɂ��ꂪ�o�Ă���̂ŁA�Ƃ�Ⴆ�Ȃ��悤�t���������܂łł��B
�a�F���Â̎���ɂ́A���������Ă������Ȃ��āA�ʂ̐��E�������Ă��āA�܂�����A����ɂ��̐��_ ���E�������Ă���悤�Ȏ��オ����Ă���B����������ŁA�����Ă�����������Ƃ������Ƃł����A�l�Ԃ̃A�X�g�����̂⎩��̔��B�ɂ��l��������Ǝv�� �܂��B���̕ӂ́A����̓W�J�̒��ŁA�ǂ��Ȃ̂ł��傤���B
���F�����A�l�ޑS�̂̐i���̗���ɏ��̂ɂ��A����̔��B�x�����Ōl���������ł��B�����āA �v�l�͂��������Ă��Ȃ��ƁA���ۂ̃C���[�W�ƌ��z�̋�ʂ����Ȃ��Ȃ�Ƃ��V���^�C�i�[�͌����Ă��܂��B�����܂Ŏv�l�͂���ׂ��Ȃ̂ł��B�����̐i���� ���R�ɂ���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B����͌��݂̎������ɂ������Ă���̂��ƌ����܂��B��������l��l���w�����Ă���̂ł��B�������̊ԂŁA�l������ �ĕ��C�ł���悤�ȏ�Ԃ��x�z�I�ł���A�����̐i���͋N����Ȃ��̂�������܂���B�V���^�C�i�[�͂��̊댯���������Ă��܂��B
�`�F�V���^�C�i�[���������̂́A�X�E�F�[�f���{���N�������Ƃ������̂Ɠ����悤�Ȃ��̂Ȃ�ł� ���B
���F����ɂ͏��������������܂��āA��ς��ǂ��܂Ŏ�蕥���Ă��邩���|�C���g�ƂȂ�� ���B���_���E�ł́A�u����v�l�Ɏ�ϓI�Ȃ��̂��c���Ă���ꍇ�ɂ́A�u���v�Ă�����̂��ω����Ă��܂��̂ł��B�X�E�F�[�f���{���N�́̕A�ނ̎�ς��� ���������̂ł��B�V���^�C�i�[���X�E�F�[�f���{���N�ɂ��ďq�ׂĂ���u��������܂��B�V���^�C�i�[�̏ꍇ�́A���̒���Ȃǂ����ǂ݂ɂȂ�Ε�����悤 �ɁA�Ƃ߂Ċ�����C����}�����A���w�I�ȓ������������̂�����������l�ł��B�ꍇ�ɂ���Ă͖��C�Ȃ��Ɗ������鎞��������قǂł��B���̋q�ϓI �Ȏp�����琶�܂ꂽ�ώ@�́A�ɂ߂Đ��m�ɑΏۂ����Ă���Ƃ����M�������悱���܂��B
�a�F����̏�ɂ������A������A��l�Ƃ������̂����ЂƂA�悭������܂���B������������ �́A���̒N�������Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂����B
���F���m�ł͌Ñォ��̉p�q���A�������̂��}�i�X�A�u�b�f�B�[�A�A�[�g�}���Ƃ����Ăі��ő����� ���܂����A���̎��̂��C���[�W����̂́A�������ɓ���ł��ˁB����̂�����̗��ł�����A���Ƃ�������ł��傤���B����͊���̔g���������肨���܂� �����Ɍ����Ă�����́A�Ƃ����܂��傤�B�ӂ���ł��������́A�����f���鎞�ɁA�l�I�Ȋ����A�D���E�������z�����������n�̑��݂��_�Ԍ��邱�Ƃ� ����܂����A���������Ə����ɂ��āA�������O��I�ɑP�Ȃ���̂Ɋт��ꂽ���̂��C���[�W�Ȃ���ƁA�߂���������܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u�V���^�C�i�[����̔w�i�����v�����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@