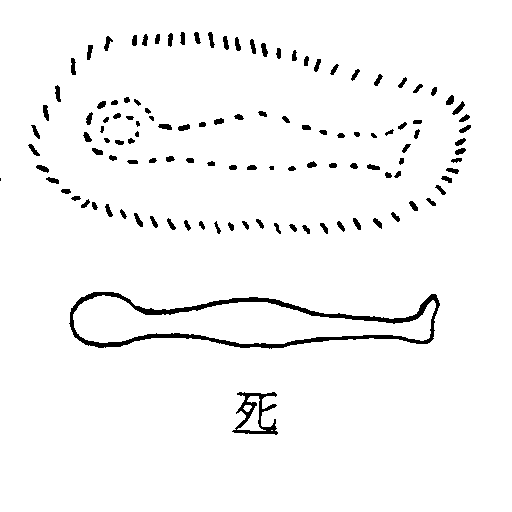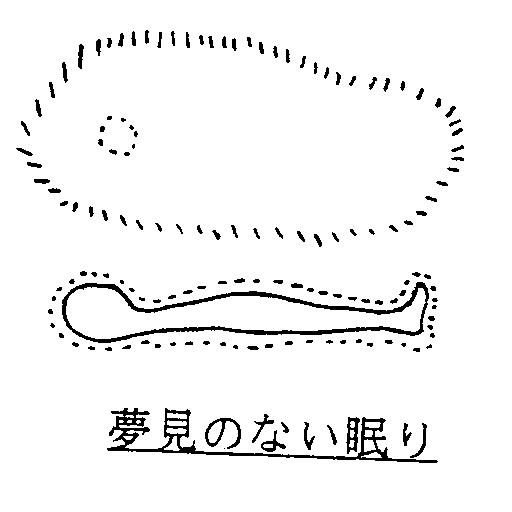(1987年6月4日)
今回は「生・死・再生」(板書)のテーマでお話しいたします。
以前、シュタイナーの述べていることが正しいことなのだろうか、すべて正しいことなのだろうか と問い直す時が必ずくるだろうと、申し上げたことがありました。今日の話は、まさにその時だろうと思います。これは、大変に大きなテーマです。
私は、この「シュタイナー教育の実際」という講座の中で、アントロポゾフィーというシュタイ ナーの思想を紹介する立場にあります。そして今日のテーマは、アントロポゾフィー思想の基本であるといえます。それは、精神世界の問題を扱っています。
私は、最初にした話で、アントロポゾフィーの三つの柱を挙げました。それは、善へ向かう意志、 明確な認識、芸術の三つでした。その三つの柱の基礎には、この精神世界という考え方があるのです。精神世界といっても、何か言葉の意味が曖昧かもしれませ ん。精神世界の原語は何でしょうか。ドイツ語では Geistige Welt あるいは Geistwelt とい います(板書)。ガイストの世界ということです。Weltは世界の意味です。ガイストを「精神」と訳した場合、「精神世界」となるのです。
今日これから私が紹介します精神世界の話を受け容れるかどうかは、全く皆さんの御判断におまか せします。考えを強制するようなことは、絶対にいけないことです。
さて、子供の発達の話をしました時、アントロポゾフィーでは、子供が生まれ出てくる前の世界も 考えるのだ、と申し上げました。それが、精神世界です。また、人が一生を終えた後の世界も考えると申し上げました。それも、精神世界です。ですから、人間 は精神世界からやってきて、この地上世界に暫くいた後、再び精神世界へ旅立つ存在であるという風に考えられているのです。
しかし、この地上にあって、精神世界、つまり彼岸の世界ばかりに目を向け続けることは、シュタ イナーの勧めるところではありません。このことは、はっきり申し上げておくべきだと思います。物質的なことばかりに目を向けることが片寄った態度であるの と同様、精神世界ばかりに目を奪われることも、間違っているわけです。人間が地上で過ごすことは、大変重要なことなのです。地上ですごす時は大切な時なの です。ただ、それが、いかに重要であるかは、精神世界にも目を配らないと、十分には分らないとシュタイナーは考えるのです。
さて、睡眠中の人間のあり方をシュタイナーがどのように考えているかは、前回紹介いたしました ね。それをごく抽象的に図示し直すと、こうなります。
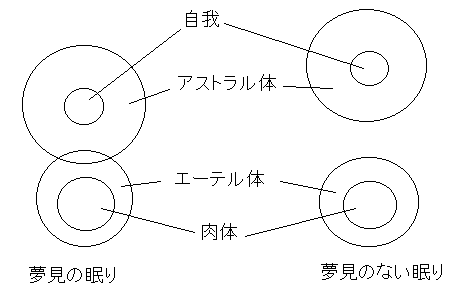
(板書)
ところが、死は、シュタイナーによれば、エーテル体までが肉体から離れてしまう現象です。同じ ように描くと、こうなります。
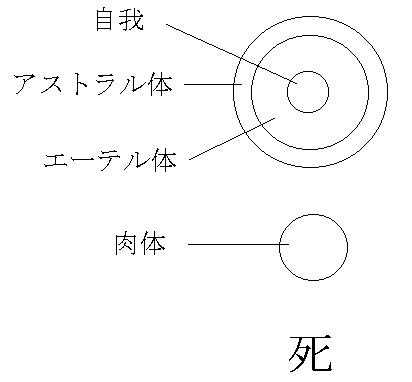
(板書)
昨今、死の定義の問題が、医学で盛んにとり上げられていますね。物質である肉体だけを見ている 現代医学は、死の定義を「脳死」というところまで詰めています。しかし、感覚には捉えられない三重の存在が肉体の外に出た時が死である、というシュタイ ナーの考えは、それなりに明解ではないでしょうか。脳死状態で、脳が崩壊し始めれば、もう自我が戻れない、という風にも言えますし。
シュタイナーの考える死の状態を、前回のような描き方をすると、こうなります。夢見のない眠り の状態も、並べてみましょう。
(板書)
エーテル体は肉体に生命を与え、形を与えていた体でした。人が死ぬと、このエーテル体が離脱す るため、肉体は単なる物質として、物質の世界の法則にゆだねられます。もはやそれは、崩壊するしかありません。しかし、意識の主体は、図のように、肉体か ら抜け出ているわけです。自我は消え去ってはいない、と考えられているのです。昔から、睡眠と死は、似たようなものだという考えがありました。ギリシャ神 話でも、眠りの神ヒプノスと、死神タナトスは、兄弟です。シュタイナーの考えに沿って、こうして図で見ると、確かに大変似ていると言えますね。
シュタイナーのような考え方をしなくても、私たちは、死というものは要するに、夢を見ないで 眠っている状態がずっと続く、という風に理解することもありますね(聴衆にうなづく顔あり)。しかし、もし意識が消えたまま、永遠の闇の中に入り込んでい るのが死だとしたら、生きている者にとって、死は大変忌まわしい、考えたくもない事柄となります。私も少年時代、自分が無くなってしまう死のことを、とて も恐ろしく思ったものでした。自分の意識が無くなってしまえば、意識を通して存在しているこの世界も、無くなってしまうと。その永遠の無、永遠の闇のイ メージは、大変怖いものでした。たしかに私以外の人は、私が死んだら、その私の死を見届けます。その人にとっての世界は、私の死後も続くことでしょう。図 にすると、こういうことです。なお、今から描く図は、写さなくて結構です。
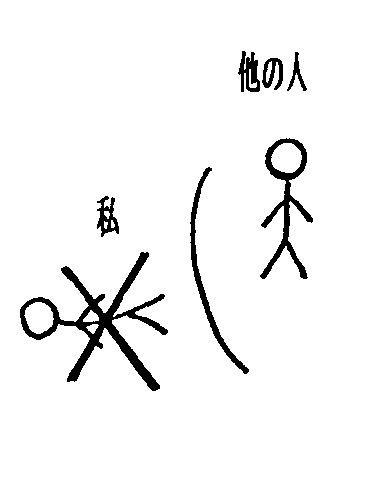
でも、その人の世界に、私はいないわけです。ですから、私にとっては、その世界はもう無縁でありま す。消えてしまった私にとって、その世界は、もう無いに等しいということになります。
素朴に考えると、自分の死後も、地球はそのままあるし、その地球の上には、生き残った人たちがいて、 その人たちが世界をあらしめているわけです。あらしめている、ということは、その人たちの意識を介して、世界が現われているということです。しかし、この ことを厳密に考えてみますと、私と共に消えてしまった私の意識の方は、何も映していない。つまり、死んだ私にとっては、世界は無くなってしまうということ になります。順番に考えてみましょう。私が夢もなく眠っている間、世界は消えています。あるいは、麻酔をされた場合も、世界は消えている。朝、目覚めた り、麻酔が切れて意識が戻ると、まわりの世界も現われてくる。
しかし、そのまま意識が戻らなかったら? ふつう考える死は、その状態です。そうすると、世界は闇の まま永劫に続きます。これは少年時代の私には、とても耐えることのできない恐ろしいイメージでした。そして現代の唯物的な世界観のもとでは、事情は全く変 わりません。ただ、大人の場合は、生きている間は、つとめて厳密に考えないようにしているだけです。唯物的な世界観のもとで、「私」という存在を厳密につ き詰めて考えると、必ずこうした結論になるはずです。「私」というものが存在しなかった、生まれる前の世界も、考えてみれば、逆方向に、過去に向かって永 遠の闇があったことになります。そのような闇が、死後も続くことになります。生まれる前の永遠の闇と、死後の永遠の闇の間に、ぽっかりと浮かんだ小さな明 かりのようなものが、生きている期間だということになります。その明かりが、死と共に消えてしまう。死の恐怖が人間の最大の恐怖であり続けるのも、この考 え方が根底に潜んでいるからです。日中は忘れていても、夜中そのような考えが少年の私を襲います。あるいは、大人になってから、ずーっと忘れていても、本 当の死の直前に、その考えが襲ってきたら? 全く耐え難いことです。本当に耐えられないことです。しかしこの考え方は、どこかおかしくはないでしょうか。恐怖を呼び起こすしかないこの考え方 は。私が生まれる前に、父や母の生きている世界が、ちゃんと存在していたことは、疑いえないのではないでしょうか。そう考える方が、自然な考えです。私が 生まれる前からこの世にいた人が、今、私と一緒の時空にいます。私が死んだあとは、今私と一緒にいる子供たちの世界が続いていくでしょう。こう考えるのが 自然ですね。
すると、問題は、死と共に私の意識が消えてしまうというあたりに、あるのではないでしょうか。 意識が消滅し、存在が消滅した「私」に視点をおいてみる、なんてことをするから、世界までが消えてしまうのではないでしょうか。
ここで、シュタイナーの考え方に移ってみましょう。夢もなく眠っている時に、肉体の外に出てい る自我+アストラル体は、意識を失っています。しかし、自我+アストラル体+エーテル体が肉体の外に出た死の状態では、自我は意識を持ち続けているとシュ タイナーは考えます。睡眠と死の二つは、似ているようでいて、やはり決定的な違いがあると考えるわけです。睡眠の状態では、再び肉体にもどってこれます が、死の状態では、もはや肉体には戻りません。後に、死の状態も変化が起こって、人間はエーテル体をぬぎ捨てて、自我+アストラル体だけになる時期があり ます。その状態と、睡眠中の自我+アストラル体の状態も、違うのです。
さて、シュタイナーの考えを、もう少し追ってみましょう。死の直後、人間は自我+アストラル体 +エーテル体の状態にあります。図を見て下さい。シュタイナーによれば、人間はこの時、意識をもっています。ところでエーテル体は、記憶を刻み込んだ体で したね。そして、この、人生の記憶を刻んだエーテル体がまだ重なって存在している間、ある特別なことが起こるといいます。それは、生前の人生の一コマ一コ マを、細大洩らさず回顧する時期であるといいます。まるでパノラマのように、一度に人生を見渡すのです。そして、その精神的な意味を同時に洞察します。こ の時期は、どのくらいの長さ続くのでしょうか。それは『神秘学概論』によると、こうです。ちょっと複雑に聞こえますが、それは、生前、その人が眠らないで 頑張っていられる期間に相当すると。つまり、これはどういうことかと言いますと、眠ってしまうということは、肉体+エーテル体から、自我+アストラルが離 れることです。
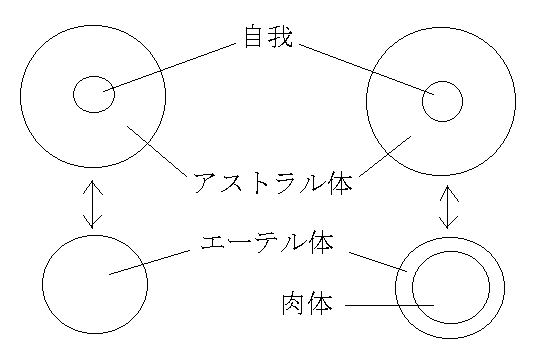
肉体を別にして考えれば、エーテル体から自我+アストラル体が離れることです(右図)。これは、死 後、自我+アストラル体が、エーテル体をぬぎ捨てることと、ある意味では同じプロセスなわけですね(左図)。今考えている期間は、左図で、自我+アストラ ル体が、エーテル体と、重なっていられる期間です。ですから、それは、右図で、自我+アストラル体がエーテル体+肉体と重なっていられる期間に相当しま す。つまり、眠たくて、自我+アストラル体が離れよう離れようとしているのに、眠らないで頑張っていられる期間に相当します。ですから、これは数日続きま すが、個人差もあるわけです。不眠症の人は長いでしょうね(聴衆、笑い)。私などは、いつもすぐ、布団に入ると、ことっと眠ってしまうので、短いかもしれ ません。しかし、これは、本質的なことではありません。要は、この時期に人生のおさらいをし、大切な洞察を得るということです。しかし、この日々は、過去の回想だけではなく、地上ではなかった新しい経験の時だといいます。 常に死の瞬間を振り返り、その時を最も崇高な時として思い出すといいます。そのことによって、ある種の、高次の意味での自我意識が継続するのだといいま す。もし、それをしないと、地上において眠っているのと同じ状態に陥るといいます(全集168番 )。そして、この時期の後、人間は、エーテル体をぬぎ捨て、自我+アストラル体だけとなって、さらに別の体験を始めます。
しかし、ここでちょっと、一息ついてみましょう。死後も意識が続くということや、人生のパノラ マを見るというような話に、ウッと、たじろがれた人もおられるのではないかと思います。私も、この考えを無理矢理押しつけようとは、決して思いません。物 理学が好きだった高校生の頃の私だったら、まず、受けつけなかったでしょう。また、大学時代の私は、現実の世界に生きていることが苦痛で、小説の世界にひ たって、かろうじて生きながらえていたのですが、その頃の私も、こんなことを言われたって、受けつけなかったでしょう。その頃の私にとって、死は何もかも 消し去ってくれる、オールマイティでした。ですから、こういうことを言われても、虚無としての死という考え方のほうが、魅力的だったと思います。ですか ら、シュタイナーのこのような考えに入り込めない方がおられるとしても、ちっとも不思議に思いません。
ただ、ここでひとつ、つけ加えたいことがあります。ここまでの人間の状態、それからこれより少 し先の事柄まで含みますが、ここまでの状態は、ほとんど死にかかって、心臓も止まったけれど生き返ったという人たちから、似たような証言を得ている、とい うことです。ただし、その種のものは、実にけばけばしい表紙の本であることも多くて(聴衆、笑い)、良識のある人は、手を出すのをためらうでしょう。私 も、そんなに沢山目を通したわけではありませんが、ちゃんとした医者や科学者が、病院を中心にデータを集めて記録し、考察した本としては、次の二冊が挙げ られます。これも邦訳の題は、人目をひくようなものになっていますが。
「かいまみた死後の世界」、レイモンド・A・ムーディ・Jr著、評論社刊。「いまわのきわに見 る死の世界」、ケネス・リング著、講談社刊。
ともに原題は、LIFE AFTER LIFE と、LIFE AT DEATH でして、この邦訳の題ほど、けばけばしいものではありません。前者が一九七五年、後者が一九八〇年の刊行でして翻訳も、それからさして時をへずに出まし た。
ムーディは、バージニア大学で哲学博士と医学博士をとった人です。多くの死にかかった人と面接し て、記録をとっています。死にかかった体験を、ニア・デス体験といいます。ニア・デスとは、死の近く、臨死、という意味ですね。アメリカでは、医学者たち の一つの研究分野になっています。ムーディは、この体験に現われる要素を次の11挙げています。
1、表現のしようがないこと。面接しても、とても言葉では言い表わせないと、多くの人が言うの です。2、(自分の死の)知らせを聞いていること。医者などが、自分の死を他の人に告げているのを、自分が聞いている、ということです。3、安らぎと静け さ。4、騒音。これは3と矛盾しているみたいですが、次の5の場合に付随して、風のような音が聞こえることがあるということです。5、暗いトンネル。狭い トンネルをすり抜けていくような体験です。6、身体からの脱出。肉体から離脱しているという体験です。7、他者との出会い。他者がその世界にいて、その他 者と出会う体験ということです。8、光の精。光が見える。9、生涯の回顧。これが先ほど述べたことと一致してますね。10、生と死の境界。それ以上いくと 死の領域だという、境界が現われることがあります。11、生還。最後の「生還」を除けば、あとは、順序通りに起こるというわけではありません。このムー ディの本は科学的なものですが、読み物としても、うまく書けています。
それに比べると、ケネス・リングのほうは、厳密な統計的手続きをとっている分だけ、やや堅い感 じがするでしょう。しかし、信頼度は、さらに増します。ムーディの本を意識していて、厳密にしているのです。ケネス・リングは、ニアデス体験の中で、頻度 の順番で、次の五つを挙げています。
安らぎ(60%)、身体の分離(37%)、暗闇に入る(23%)、光を見る(16%)、光の世 界に入る(10%)。
彼の集めた証言のうち、先ほどシュタイナーが述べた人生の回顧に相当するものを、一つ挙げてみ ましょう。ボートの事故で溺死しそうになった若者の体験です。(訳書の150 ページから引用。( )内は質問者の言葉)
「…それは驚きでした。ぼくの頭のうしろにずらりと並んで見えたんです。数え切れないほどもの すごい数の、考えや思い出やぼくが夢見たことがです。だいたいは、そう、いろんな考えや過去の記憶です。それが、三〇秒たらずのうちに、どんどんぼくの前 に走ってきたんです。ぼくの母のことや祖母のことや兄弟のことやぼくが夢見たことなんかも全部です。それは一コマ一コマになっている感じでした。だから、 何百万ていうコマです。それが、ほんとにひらめくように通っていったんです。(それは、どういう感じですか?)いろんな人についての考えや映像だったんで す。ものすごい数の考えが、一瞬のうちに走り過ぎていったんです。(彼は指を何回も鳴らす)ぼくは、水の中で目を閉じていたんです。でも、そういうものは 見えていたんです。(そういう映像や考えが見えていたとき、あなたは幸せな感じでしたか?)全くそうです。全くです。(それらの記憶をどう感じたか説明し てもらえませんか?)いろんなことが、すごく感動的でした。(彼は、二年前に母が死んだときの記憶や母と一緒にしたいろいろなことの記憶を話す。彼は、母 とまた会うかもしれないと思ったという。彼はまた、祖母のことも考えた。この祖母はまだ生きていて、彼は非常になついていた)ぼくは、彼女(祖母)が死な ないようにっていってるのを見たんです。ぼくは、ぼくが溺れ死んだら、彼女がどう思うか、わかったんです。全く‥‥馬鹿々々しいことです − ぼくが忘れ てしまったと思っていた全くつまんないあら探しみたいなことです。ほんとに(指を鳴らす)サーッと通り過ぎていったんです。ぼくのほうがそういう記憶の間 を通り過ぎているみたいでした。ああ、そうです。ぼくの一生の記憶をテープで再生してるみたいだったんです。ただし、逆にです。すべて、同じ道を引き返し ていたんです。だから、ぼくはテープ・レコーダーのように繰り返した感じがしたんです。でも、これは連続してはいませんでした。(よせ集めみたいだったん ですか?)そうです。そうです。」
こういう事例は、他にもいくつか載っています。こういう時、シュタイナーの考えでいくと、 ショックでエーテル体が、一時的に肉体の外へ飛び出して、あの自我+アストラル体+エーテル体の状態になったといえます。
さて、それでは、シュタイナーの考え方に戻りまして、自我+アストラル体が、エーテル体をぬぎ 捨てた後の世界の話に、移りましょう。ぬぎ捨てたといっても、エーテル体のエッセンスはもっていきます。地上体験は無駄ではないわけです。アストラル体 は、どういう体でしたでしょうか。感情や欲望の担い手でしたね(聴衆に、うなづく顔あり)。しかし、欲望を満たしてくれる肉体は、すでにありません。感覚 的な満足を得たいという欲求が起こっても、それを満たす手段がないわけです。ですから欲望を抑制できない人は、この時期に、その欲望と戦わなくてはならな いといいます。この時期は、アストラル体に付属した様々な欲求を、いわば浄化する時です。また、これはもし、受容できれば驚くべきことですが、この時期 は、人生で体験したことをすべて、時間を逆に再体験するといいます。先ほどのパノラマ的に見る再体験とは、また違います。この時期には、すべてが逆になっ ているといいます。人に苦しみを与えたところにさしかかると、自分が、その人の苦しみを体験するという風に。人生をさかのぼっているのですから、そうした 場面も、逐一のがさないわけです。この世界は、アストラル界(魂界)といいます(板書)。アストラル界は、物質界をすべて裏返したような世 界です。
アストラル界というのがあるならエーテル界もありそうですね。実際、エーテル界というものも考 えられています。これは、物質世界と重なって存在していて、物質界よりも一次元繊細な世界です。いわば、人間のエーテル体の故郷です。そして、エーテル界 は、地球のエーテル体のようなものです。地球を一つの生命と見なした場合、人間がエーテル体をもつように、地球はエーテル界をもっているという風に考えら れるのです。この世界を、地上にあって垣間見るためには、イマギナツィオーンという認識状態になる必要があります。一方、アルトラル界を認識するために は、イマギナツィオーンの他に、インスピラツィオーンも必要になってくるといいます。
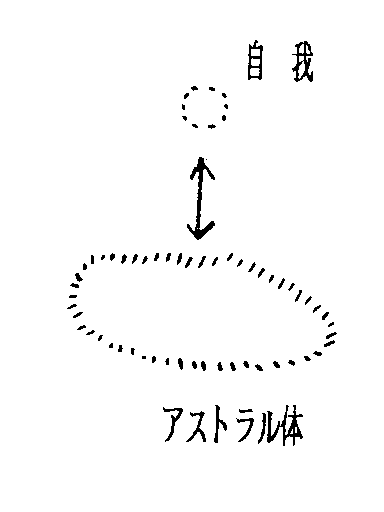
さて、このアストラル界を抜け出る時、自我はアストラル体も、ぬぎすてます。この時も、アスト ラル体のエッセンスはもっていきます。そして、いわば高次の精神世界に入っていきます。この世界は、アストラル界より、さらに高次の世界です。ここが、い わば本当の精神世界、ガイストの世界です。この世界でも、ガイストの側面から、人生をもう一度体験し直すといいます。こうした再体験は、すべて、より完全 な人間を目指して行なわれるのだ、ということが大切です。この世界も、様々な段階があります。段階といっても、物質界の空間的な上下の関係にあるのではあ りませんが。
その、ある段階に達しますと、人間は、物質界やアストラル界での反省に基づいて、今度の生涯は こうあるべきだという意図を成熟させていくといいます。そして、もし欠けているものがあれば、次の生涯にそれを獲得するための試練を課すことも、この時に 決めるのだといいます。つまり、次の生涯というものが考えられているわけです。シュタイナーによれば、次の生涯のあり方の決定には、自分の意志も関与して いるということなのです。今の人生に何か障害となるものがあるとすれば、それは自分が、それを克服するために置いたのかもしれないわけです。人間は、こう して何度も生まれ変わりをして、より完全な人間に向かっていくと考えられています。
このガイストの世界を垣間見るには、インスピラツィオーンの認識を必要とするのですが、反復さ れる地上の生に関するある種の事柄は、イントゥイツィオーンの認識にまで達していないと、捉えられないといいます。人間は、このガイスト界で長いこと善な る意志に貫かれ、浄らかな時期をすごした後、再び地上にやってきます。より完全な人間となるために、地上での体験が必要になるのです。こうして再び新しい アストラル体やエーテル体を身につけると、受胎後の母親の胎内に降りてきます。かくして、前の人生のことをすっかり忘れた、新しい人生が始まるのです。
さて、ここまで一気に話してしまいましたが、どうでしょうか。こうした考え方は、いわばふつう の知識のように、情報として提供することはできないものです。シュタイナーが特別な認識状態、つまりイマギナツィオーン、インスピラツィオーン、イントゥ イツィオーンの状態になって確かめたことだということを信じ、それをいわば足がかりとして耳を傾けたとしても、その内容を受け容れるには、ものの考え方の 大転換を迫られますね。そして私は、その転換を要求することは、いたしません。真実というものは、自分で見出すものです。人から強制されたものは、決して 真実にはなりません。真実はどこにでもころがっているのかもしれません。しかし、自分が拾い上げない限り、その真実は、ただの路傍の石です。そして誰もそ れを拾えとは言えないのです。強いられてとり上げたものなどは、そのことだけで、もう真実ではなくなっています。ただ、人間存在をシュタイナーが、以上の ように考えているのだということは、お伝えできたと思います。
シュタイナーは、精神世界には、人間以上の存在がいることも述べています。人間の高次の構成要 素として、霊我や、生命霊や、霊人の兆しを挙げましたね。精神世界には、すでに現在、霊我を完成し、肉体をもっていない存在とか、生命霊を完成していて、 エーテル体も肉体もない存在とかも、考えられているのです。こう申し上げると、大変な世界が開かれてしまったとお思いになるかもしれませんが、そういった 高次の存在も、シュタイナーが真剣に考えているものです。
こうした世界観は、仏教やキリスト教などなどの、宗教の世界と重なる部分もあります。再生の考 えも、仏教の輪廻の考えと重なっていますね。しかし、シュタイナーに言わせると、彼は仏教やキリスト教の文献から、こうした考えを取り出したのではないの です。太古の時代 − うんと大昔のことですが − 、その時代には、人間が当たり前の実在の世界として精神世界と接していたと、シュタイナーは言いま す。宗教は、その精神世界を一般の人間が見失ってしまったために、生まれたものだそうです。いわば失った精神世界に対する憧れとして、宗教が興ったのだ と。シュタイナーは、その源泉の精神世界を、直接自分で洞察して、以上のような認識を得たと言っているのです。また、シュタイナーの考えでは、地上の生活 は決して無意味ではないのです。次の生涯とのつながりからいっても、そうですが、この地上世界にも、精神世界の光が反映しているということからも、そうい えます。我々が他人と向かい合い、その目を覗き込み、その人の眼差しが我々に返ってくる時、実はその眼差しの中に、高次の存在の力も働いているのだといい ます。この地上でのプロセスには、全宇宙の高次存在が作用しているのだと。こうした考え方は、もし受容できたら、大変に崇高なことですね。
今日のテーマでの話は、これぐらいにしますが、最後に、私自身の経験を述べようと思います。輪 廻のような考えを、怪奇的なものに歪めてしまう夢想家たちもいますね。また、常識の世界から見れば、夢想家でなくても、生まれ変わりは、何か尋常ならざる 事柄に思えるかもしれません。私自身は、この事柄を受容していますが、そのあとで、自分に子供が生まれました。自分の子供が生まれた時には、やはり、ふつ うの子供をもつ父親とは違った感慨をもったことは、事実です。しかしそれは、ふつう親となった者がもつ責任の感情を、特に強くしたようなものだともいえま す。自分の子供であることは確かですが、精神は別ものであると。子供の精神をいたずらに親に従属させずに、一個の独立した人格として考えることは、再生の 考えをもっていなくても、必要なことですね(聴衆にうなづく顔あり)。その考えが、強められました。子供を自分の所有物のように見なす考えは、捨てる他あ りません。ただ、子供の存在形態は、大人のものとは違いますから、それぞれの時期に合ったやり方で接しなくてはなりません。そのあたりが、シュタイナー教 育であるわけです。
しかし、実をいえば、特別な感慨をもったのは、子供が生まれた直後ぐらいのものでして、生後二 週間ぐらいに、子供の目がしっかりしてきて、自分の視線と、子供の視線とがぴったり合った時から、もう、ただの子煩悩な父親と区別がつかない状態となった (聴衆、爆笑)ことを、白状しておきます。精神の問題とは別に、魂の、つまり心のレベルの結びつきは、一緒にすごす日常生活から育っていくものですね。そ れは地上の事柄にしかすぎない面もあるのかもしれませんが、そのあたりを欠いたまま、高次の精神世界へ目を向けっ放しにするようなことは、おかしいと思い ます。可愛がるだけでなく、怒ることも、しょっちゅうです。揺れ動く心の世界から得るべきものまだまだ沢山あるというのが、私の現状です。
さて、次回は、「第五文化期の課題(歴史的展望)」のテーマでお話しします。