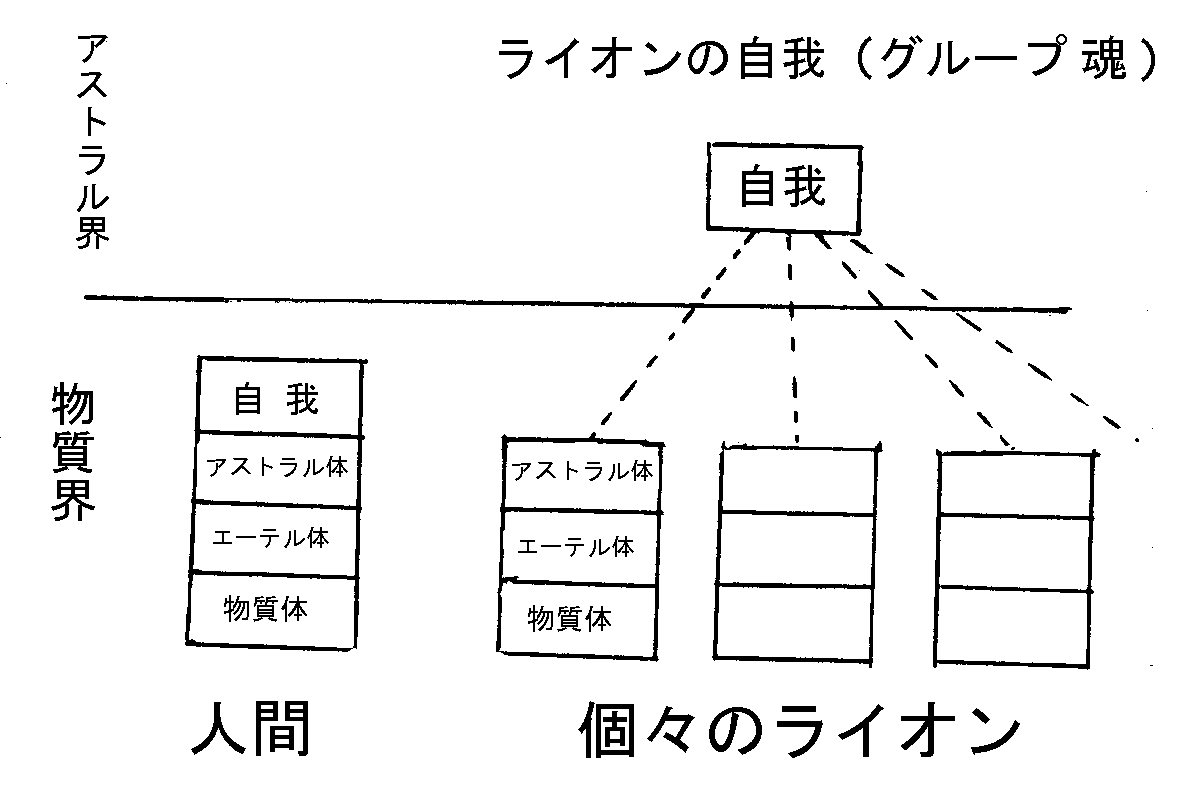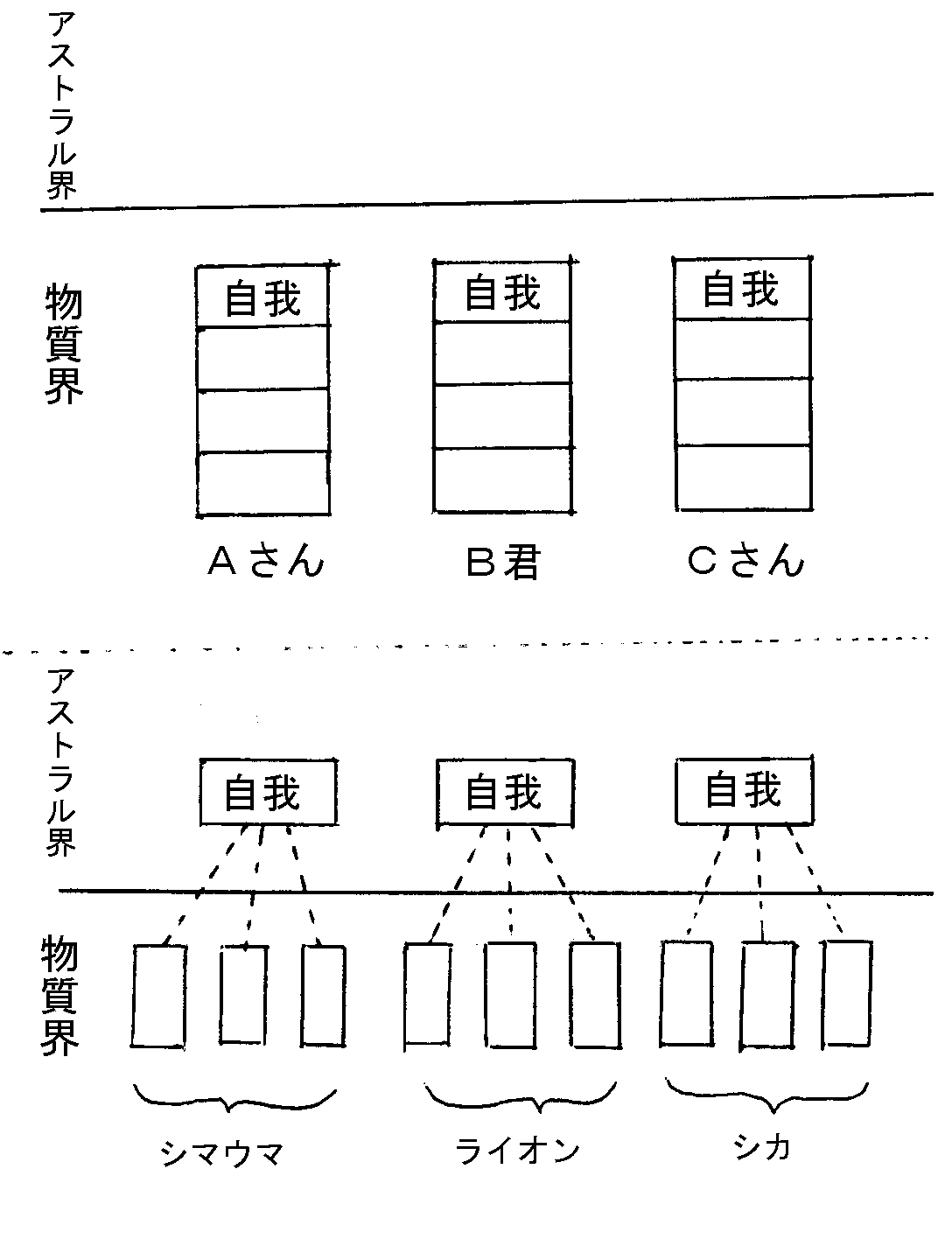シュタイナーの世界 5妖 精 Ⅱ
火の精(サラマンダ-)
人 間界と動物界の境界に現れる火の精
植物の受精に力を 貸す火の精
火の 精はどうやって生まれるか
人間につくグルー プ魂
アス トラル界に出るとライオンの自我に会える
猿のグループ魂が分霊して火の精となる
グループ魂は何から生まれたか
古代人はみな 自然霊が見えた
アマゾン川流域の住人は自然霊を見 ている?
今後、自然霊を見る人がふえてくる
前回は地の精(グノーム、コーボルト)、水の精(ウンディーネ、ニンフ)、風の精(シルフ)と 話を進めました。今回はその続きで火の精(サラマンダー)の話から始めます。
まず断っておかなければならないのですが、火の精についてシュタイナーが1908年に述べたこ とと、1923年に述べたことの間に、矛盾があるのです。前号で風の精は群を成す蜂のオーラの中に入り込んでいると述べましたが、これは全集102番『霊 的諸存在が人間に及ぼす影響』第11章1908年6月1日講演)によるものです。しかし、全集230番『創造し、形象を生み、造形する宇宙言語に共鳴する 人間』第8章)1923年11月3日講演)では、それが火の精になっています。シュタイナーは36年間に5965回の講演を行いましたが、私が調べた限り では、このような明白な矛盾は他にありません。ですから、本当はむしろ6000回近い講演をこなしながら、ほとんど矛盾した話がないことの方に注目すべき なのでしょう。
しかし私は、シュタイナーの考えを始めから疑ってかかっている人の、その疑いを増す恐れをおか しても、この事実を明かしておこうと思います。なぜなら、霊的世界観を拒否している人は、シュタイナーを読みませんから、この事実に気づくことはないで しょうし、シュタイナーを「導師」として崇めたり、シュタイナーの考えに基づく人智学運動にのめり込んでいる人たちは、たとえ気づいたにしても、こうした 「都合の悪い」事実をことさらとり上げることはしないと思われるからです。このような事実の存在を伝えるのは、シュタイナーの世界観にひかれ、彼の述べる ことを信頼し、その内容を人に紹介しながらも、彼の著作・講演集をテキスト(文献)として批判的に読むことを心がけている私のような者の役目だと思われる からです。
それでは、読者が自分で判断できるように蜜蜂と妖精の関わりについてシュタイナーが述べている ことを二つの講演から抜き出して並べてみましょう。
「たとえば教育を受けた人が、こう言ったとします。『シルフとかいう名の自然霊のことが話題に なっているが、そんなものは存在するわけがない!』 こういうことを言う人に対しては、次のような逆説的な響きをもった返答をするほかないでしよう。『君 に自然霊が見えないのは、その存在を分からせてくれる器官の開発に対して君が心を閉ざしているからだ。ちょっと蜜蜂自身に聞いてごらん。それでなければ蜂 の巣の魂にでも聞いてみるといい。蜜蜂なら、シルフの存在に対して心を閉ざすことはしないから(中略)』。花の蜜を吸っている蜜蜂は小さなオーラを出して います。そこに霊的存在が近づいてきます。特に木に群がり、ぶらさがっていた蜂の群が、体内に蜜の味わいのようなものを秘めて飛び立つような時がそうで す。そんな時、蜂の群全体が、このエーテルのオーラに包まれていますが、この群には、シルフと呼ばれる霊的存在が入り込んでいるのです。」(1908年6 月1日講演)
「風の精(シルフ)は鳥たちが飛ぶのを見ると、自己を、自分の自我を感じます。火の精はこの自我 感情をもっと強い形で、蝶の世界、そして昆虫界全体に対して感じます。植物の雌しべに熱を伝達するために、昆虫が飛ぶ跡を追うことが大好きなのは、この火 の精なのです(中略)。花から花へ飛びまわる昆虫はたいてい彼らの追跡をうけています。花から花へと飛びまわる昆虫をよく見ると、その昆虫のどれも、昆虫 自体がもっているものとしては説明のつかない特別なオーラを発しているような感じがします。特に花の間を飛び回わる蜜蜂は、明るくきらめく、素晴らしい輝 きをもった綺麗なオーラをもっていますが、このオーラを説明するのは大変難しいことです。なぜなら、その蜜蜂はいつも火の精と一緒にいるからです。火の精 はいつも蜜蜂を身近に感じていたいほど、蜜蜂と親しく感じているからです。霊視すると蜜蜂は一種のオーラの中に、本来は火の精であるこのオーラの中に包ま れているからです。蜜蜂は大気の中を花から花へ、枝から枝へと飛びまわっている時、元々火の精によって与えられたオーラを伴って飛んでいるのです。火の精 は昆虫の存在に自分の自我を感ずるだけでなくて、その昆虫とすっかり結合してしまおうとするのです。」(1923年11月3日講演)。
なお、1908年の講演は第一次世界大戦前と大戦中にシュタイナーの講演の多くを速記したヴァ ルター・ヴェグェラーンが記録しました。1923年のものは専属の速記者ヘレーネ・フィンクによります。
講演集の記録は、ほとんどのものがシュタイナー自身の校閲を受けていません。ですから誤りがあ ることも考えられ、シュタイナーも自伝の中でその可能ム性について触れていて、各講演集の冒頭にその部分が引用されているほどです。しかし、妖精が境界に 現れるという1908年の講演の説明では、地の精はふつうの岩石と鉱物の境界、水の精は植物と岩石プラス水、風の精が動物(昆虫も含む)と植物、火の精が 人間と動物がそれぞれ接触する境界に現れることになっていて、蜂と花が接触するさい現れるのが風の精であると、この時シュタイナーが考えていたことは間違 いなさそうにも思えます。また、二つめの1923年の説明では、地の精はかえるになるのを恐れ、水の精は魚の姿になるのを厭がり、風の精は鳥に親しいとい うふうに話が進んだ後に、火の精は蝶の世界・昆虫の世界と親しいといっているわけで、話がしっかり有機的になっていて、速記者が間違いをおかす可能性は少 ないように思われます。
繰り返しますが、このような著しい矛盾はシュタイナーには極めて珍しいことです。しかし矛盾は 矛盾です。はっきりここで指摘しておこうと思います。私は科学者の冷静さで霊視するシュタイナーの言うことは、他のどんな霊能者よりも信頼していますが、 しかしそのシュタイナーのいうことでも無批判にうのみにしようとは思いません。さまざまな予言・霊言のたぐいが押し寄せる世紀末にあっては、こうした姿勢 を心のどこかで堅持しておくことも大切ではないかと思います。
さて、それではシュタイナーは火の精の現れ方や役割について他にどのようなことを述べているの でしょうか。以下、まず1908年の講演に基づいて紹介します。
火の精の構成要素は前回述べたように、未完成な自我十アストラル体十エーテル体十物質体です。 彼らは進化の歩みが違うため人間の姿はとれませんでした。火の精は他の妖精と比べて、一番後に生まれたものでして、実に多くの種類があります。その大部分 は、あとで述べる動物のグループ魂から分霊しました。
[戻る]
火の精は人間界と動物界が、ある意味で普通でない関係にある時に現れます。たとえば騎手と馬の 間の、家族的な関わりにひかれて現れます。これは善い種類の火の精です。火の精は人間と動物の心の通い合いによって生まれる感情や気持ちを養分としている のです。とくに羊飼いと羊の群れが一緒に暮らしているような場合、近づいてきて、その場にとどまります。この妖精は非常に賢い存在でして、自然の知恵を もっています。羊飼いが羊たちと一緒にいる所で、この火の精が自分のもっている知恵を羊飼いにそっと教えるようなこともあるそうです。このような妖精に取 り囲まれている人間は、小利口な現代人たちが夢にも思いつかないようなことを知ることができるというわけなのです。
[戻る]
1923年の講演では、植物が実を結ぶ時、火の精がどのように働くかが述べられています。まず 火の精は熱エーテルを集めて、それを花の中に運び入れます。そのさい花粉は火の精に与えられた超小型の飛行船のような役目を果たします。シュタイナーによ れば真の受精は、花粉が雌しべにつく時ではなく、火の精が花粉に乗せて雌しべに運んだ宇宙の熱エーテルを、地の精が地中で受け取る時に生ずるのだそうで す。ここで前回から述べている植物の成長をまとめると次のようになります。
まず火の精から受け取った宇宙の熱エーテルを用いて、地の精が地中で植物に活力を与えます。地 の精はその時、自分がその中で生きている生命エーテルを植物の根に与えるのです。こうして植物は成長し出しますが、地の精の大地に対する反感から上へ上へ と伸びることになります。次に水の精が化学エーテルで枝葉を成長させ、風の精が光エーテルを用いて植物の原型をこしらえます。この原型(母性的なもの)が 滴となって地面に落ち、地の精がそれを受けとめます。一方、火の精は熱エーテルを宇宙から集めて雌しべに運び入れます。その力が種子に移り、その種子(男 性的なもの)が地中に落ち、これまた地の精が受けとめ、ここに受精が生じます。真の受精は、冬の間、地中で生ずるのだとシュタイナーは言います。
大部分の火の精はアストラル界にある動物のグループ魂が分霊することによって生まれたと、先ほ ど述べましたが、これを詳しく説明することにします。
これまでの話しで、動物には自我がないと言ってきましたが、実はアストラル界にはあるのです。 動物の自我はアストラル界にとどまっていて、物質界まで降りてきていないといえます。たとえばその動物をライオンとすると、物質界に存在するすべてのライ オンの共通の自我(グループ魂)がアストラル界にあるのです。人間の場合との違いを図で示すと次のようになります(なおシュタイナーはグループ魂のあり方 については、多くの講演で繰り返し矛盾なく述べています)。
人間一人一人の違いは、種類の異なる動物の違いと同じようなものです。
なお人間にも様々なグループ魂が関わってくることがあります。祖霊とみなされるグループ魂など はその一種ですが、これらは一つの家系が呼び寄せた高次の存在です。祖霊に限らず、一つのグループが共通の傾向をもつことで、ある種の存在がグループ魂と して引き寄せられます。このような人間以上の高次のグループ魂もいるわけです。これらは、正規の霊的進化の歩みのうちにある天使や大天使などの高次存在と は別のものです。
古代の人間は、部族や家系や血縁関係の共同体に従属していて、その共同体の中で助け合って暮ら していたわけですが、こうした共同体も、ある種のグループ魂をもっていました。祖先霊は古代人が夢うつつの意識状態になった時現れ、忠告を与えてくれたり しました。しかし、こうした関係の中では、個人は強制的に共同体に従属していて、個人の自由は拘束されていたわけです。自我の発達とともに、精神の自由が 求められていきますが、シュタイナーは、これからは個人の自由を互いに尊重し合い、自由な意志のもとで集まる共同体が作られていくことが望ましいと考えて います。そうした共同体には古代のグループ魂とは別のグループ魂が引き寄せられ、人類の霊的進化を早めてくれるそうです(全集102番、11章)。
霊能者がアストラル界に出ると、物質界で自我をもった人間に出会うのと同じように、ライオンの 自我に会うことができるとシュタイナーは言います。他の動物や昆虫の自我にも会えるわけです。こうした自我がグループ魂として、物質界にいる個々の動物や 昆虫の上位にいるのです。動物や昆虫の信じられないような本能的な知恵の源は、アストラル界にいるグループ魂にあるのです。スズメバチが紙と同じ成分の巣 を巧みに作るのも、グループ魂の知恵のおかげです。スズメバチの自我は、人間よりも遥か以前に紙を発明したといえます。ニューサイエンスのリーダーの一 人、ライアル・ワトソンは『スーパー・ネイチュァ』(訳本289ページ)で、グループ魂に似た考えに行き着いています。彼はある種のアリが、通り道に障害 物を置かれると、そのことをテレパシーのようにすぐ直感して迂回路を作りに来るという報告に基づいて、そう考えました。そのようなテレパシーの交信が、同 じ種に属するすべての固体に行きわたるのではなかろうかと考え、さらに、それぞれの種が一種の霊的な源をもっているようだとしているのです。
[戻る]
さて、一匹の昆虫が死んだとします。でも、それはその昆虫のグループ魂にとっては、人間の場合 にたとえると髪が抜け落ちたり、ツメを切ったりするのと同じようなことです。昆虫の一匹一匹はグループ魂から魂を分け与えられ、交代で物質界に降りては、 また死んでいっているわけです。昆虫の場合、グループ魂から与えられたものは死後、すべてグループ魂に戻ります。しかし、これが高等な動物になると事情は 違ってきます。猿の場合は、その知恵を見れば分かるように、昆虫よりも多くのものを、自分のグループ魂から分け与えられています。それがあまりに多すぎる ため、死後、そのすべてがグループ魂に戻ることはできないのです。一部は物質界に残ってしまいます。これはグループ魂から分離した自我状の分霊存在です。 自然霊の中では最高の種です。これが火の精と呼ばれる妖精なのです。火の精は今でも生まれつつあります。猿の魂が死後、グループ魂に戻れなくなって物質界 にとどまり、火の精となっているといえます。
人間の死と猿の死には大きな違いがあります。人間の場合は、物質界にある自我が死後、霊的世界 を訪れ、それが再び物質界に戻ってくるという形で輪廻がありますが、猿には輪廻がありません。猿の魂は、死後グループ魂に戻れませんが、かといって新たに 受肉することもできずに、物質界に火の精としてとどまるのです。
火の精はそのほとんどが猿のグループ魂から生まれたわけですが、それではグループ魂自体はどう やって生まれたのでしょうか。全集136番『天体と自然界の霊的存在』第4章によると、動物や植物のグループ魂は、能天使、力天使、主天使という高次存在 が分霊して生まれたものだといいます。分霊して生じた動物のグループ魂の間でも、高次なものと、それほど高次でないものがあるそうです。全集110番『霊 的ヒエラルキーと物質界におけるその反映』巻末の質疑応答によると、蜜蜂のグループ魂は、人間が金星進化期(今の地球進化期の次の次)にようやく達するレ ベルに既にあるそうです(ということは、生命霊まで備えた大天使級の霊ということです)。これは宇宙的に早熟だということです。また、珊瑚のグループ魂は 牛のグループ魂より高次だそうですが、こうした話はシュタイナーの霊能力をどこまで信ずるかで受けとめ方が異なってくるでしょう。
自然霊(エレメンタルガイスト)は古代人にとっては日常的な存在でした。古代人は、自然界の住 人として動物や植物以外に、自然霊の存在も知っていたのです。アトランティス時代の2/3の時点までは、すべての人間はエーテル界が見えていましたから、 自然霊の存在は自明のものでした。アトランティス人のエーテル体は額の所で物質体から著しく突出していて、直接霊的世界に接していました。そのエーテル体 は物質体に拘束されていないわけです。そのため、記憶の担い手としてのエーテル体の力も超人的に働いて、無限の記憶力を可能にしていました。そして何の修 行もすることなしにイマギナチオーンを用いてエーテル界を霊視できたのです。しかし、この分離したエーテル部分を用いて、高次霊と交信できたのはアトラン ティス人の中でも秘儀参入者だけでした。このあたりの話は『神秘学概論』第四章「宇宙進化と人間」に詳しいです。
ワトソンによると、アマゾン川流域のヤノマモ族が現在も用いている薬草の作り方は非常に複雑 で、12、3の手順があると言います。アマゾンに人間が住みついてから1万年から1万5千年がたっていると思われますが、試行錯誤だけの方法では何十万種 もある植物から特定のものだけを選び出して、しかもそれを一つ抜かしてもだめになる複雑な手順で調合するやり方を発見できたとはとても思えないそうです。 彼らにたずねると「森が私たちになすべきことを教えてくれた」と答えるそうですが、私はこうした話を読むと、火の精に囲まれて、素晴らしい知恵を授けられ る素朴な羊飼いのことをどうしても思い浮かべてしまいます。
また、アマゾンのコニボ族と生活した人類学者のマイケル・ハーナーはコニボ族が「魂の蔓」と呼 ぶ神聖な飲物を飲んでみました。するとワニの姿をした悪魔や、魂の舟や、鳥頭人などが現れる「幻覚」が見えました。彼はこれらの幻はアメリカ人である自分 が潜在的にもっていたイメージだと思いましたが、なんと土地の呪術師はその怪物たちを全部知っていて、言い当てたのです。つまり、あらかじめ何も知らない 人でも、その土地では土地の人が見る幻と同じものを見てしまうわけです。私はこの現象は、薬の助けを借りてエーテル体が分離した時に、土地に棲みつく自然 霊が見えるのではないかと思います(以上『スーパーネイチャーⅡ』318ー319ページ)。シュタイナーによれば、昔の秘儀参入の儀式は、司祭が参入者を 三日三晩昏睡状態にする間に、エーテル体を一部分離して、霊的世界の有様を見せるのだそうです。
アトランティス人は、そのような方法をとらなくとも、エーテル体が初めから一部分離していて、 エーテル界とその住人を見ていたわけです。このようなエーテル体と物質体の分離はその後はなくなり、古代ギリシャ・ローマの時代にいたって、肉体と魂は すっかり一致します。その後ルネッサンス以降、再びこの結合がゆるみ出してきました。エーテル体が物質体から分離し出したのです。そのため、その隙間に他 の存在が入り込む危険もあります。しかし一方で、エーテル界が見える人がふえてきます。自然霊が見える人も多くなるでしょうが、見えている本人や、周囲の 人も、それを幻覚と思ってしまうかもしれません。
シュタイナーに言わせると、エーテル界に見えてくるもので、もっと重要なものはキリストの姿だ そうです(全集118『エーテル界におけるキリスト出現の事象』)。シュタイナー思想の一つの柱であるキリスト観についてはまた別の機会に述べようと思い ます。
なお異星人=妖精説を唱える人が一部にいますが、この考えには混同があると思います。妖精は地 球のエーテル界に住んでいる存在で、最高の種でも、不完全な自我までしかもっていません。異星人は、私の考えでは地球以外の惑星で、霊我以上の要素を発達 させつつある存在だと思います。異星人についてもいつか述べるつもりです。(「妖精」おわり)