�d���_
�@�@�@�@�@���[�h���t�E�V���^�C�i�[�̐��E����i�P�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@��z�Ƒz���@�\�@�V���^�C�i�[�̗d���_�����̂��߂��@�\
�{�_
��
�p���P���X�X�̕���
���Ƃ���
���Ƃ����i�z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���ɓ������āj
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@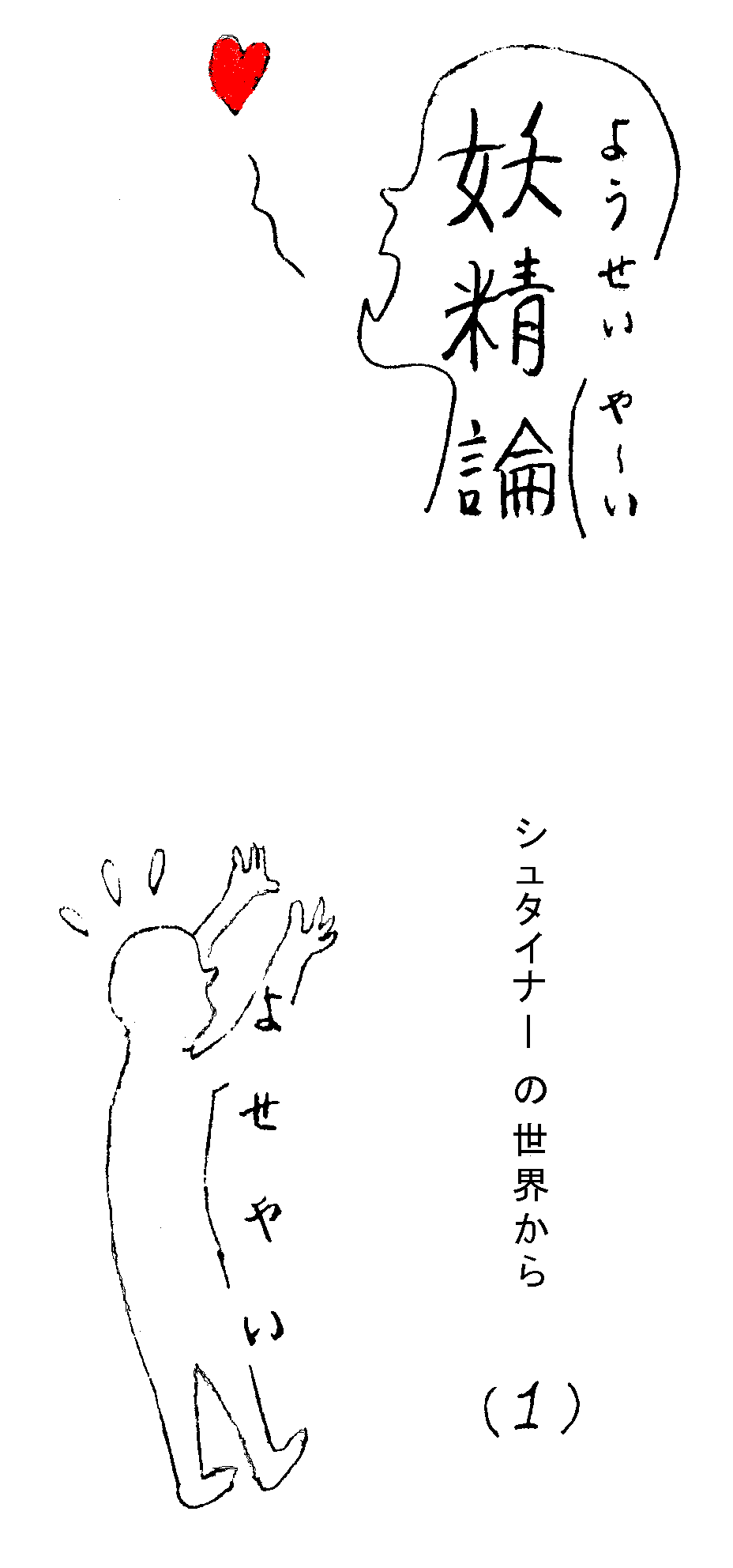
�@�d�����o�ė��镨���A���̑��݂��߂���v���ɂ́A�l�̋����Ƃ��߂������̂�����B
���̎�̎����Ɉ��������l�́A����ɂ����������낤�B���̎p�́A�d�����݂����̂łȂ��A�w�s�[�^�[�E�p���x�k�W�F�C���Y�E�o���[(�p�A�P�W�U�O�|
�P�X�R�V�N)��B�P�X�O�S�N�㉉�B�P�X�P�P�N�A�o���[���g���������l�ɏo�ė���e�B���J�[�E�x���̂悤�ȁA���Ɏ����@�ׂŔ��������̂ł���̂������B���R�z���ł��鎞�̈��炵�����A�܂��ƂȂ�������̂Ɋ���������悤�ȁA�C�����ԂȔ��ʂ��ق����B��@���߂Ȏ��͖����A������Ȃ��߂������J�͂́A���̌�̕S�{�̈��炵���ŕ����̂��ƁB
�@�������d���͂܂��A���̎�ŕ߂��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����݂ł�����B�C�M���X�̓��b���������ɁA�c���ɂ͓V�䗠�ň������Ƃ̂ł����d���������A�q���̐����ɂ�Č����Ȃ��Ȃ��Ă���悤�Șb���������B�e���Ȍ����̓��ɂ��������̎�̈��炵�����݂̑r���A������̐��E�̑r���́A�������玸���Ɏ��Ă���Ƃ����邩������Ȃ��B
�@�������͂܂荞��ł��鐢�E���甲���o�āA�ʂ̐��E�֍s�����Ƃ��邠����ɂ����ẮA������̏ꍇ�ɂ��A�����̐��E���A�����Ɏ������Ƃǂ߂����ɏ\���Ȃقǂ̉��l�������Ă��Ȃ����Ƃ���������B����ɂ́A�傫�������āA��̏ꍇ�����邾�낤�B���̈�́A�����̐��E�����|�I�ȍR����͂Ŏ����̐����������Ԃ����Ƃ��Ă�����A��������l�ڂ����Ŏ₵���A����Δ����݂Ƃ����������Ȃ��ɂ����Ă����肷��A����ɂ����̂ł���B����Δ������̓���ł���B������́A�����̐��E���̂��̂͂������ʂł���A���}�ł����Ă��A��z�͂��ߏ�Ȃ��߁A�ڂ��������E�Ɍ�����Ȃ��f�����ɂ����̂ł���B�ߏ�Ƃ����قǂł͂Ȃ����A���ψȏ�̋�z�͂��A����ɐG������ĕʐ��E�������w������Ƃ����A�o���̗v���̂܂��荇�����P�[�X�����肤�邾�낤�B��������z�͂����܂�ɉߏ�ȏꍇ�ɂ́A�������o���̂��̂��ł���A�����̕s�@�ӊ����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ��l������B�����Đ푈���N����A�ڂ���ƘȂ�ł��鎞�ɒe�������Đ^��Ɏ���ł��܂����낤���A�H�����Ȃ��Ȃ������ɂ́A�������ɓ���錻���I�ȎZ�i�Ɏ��s���A�ނ��낤�܂�����H�ׂĂ��邱�Ƃ���z���Ȃ��玀��ł����\�����������낤�B���l�����Ȃ���A��������𔒒����Ō��邾�낤�B
�@�����ŁA�{�_�ŗp�����z�͂Ƒz���͂̊T�O����ʂ��Ă��������B��z�͂́A���݁A���������͂ތ������E�Ƃ́A�قƂ�ǁA�Ȃ����S�����W�ɑ�����������̂Ƃ���B�Â܂肩�����������ɐ搶�̐������������킽���Ă���悤�Ȏ��ɁA�F���D�ɏ���ăz�I�L���ɐڋߒ��̐��k���x�z����͂�����ł���B�ڂ͂ڂ��蒆��ɂ������A�����������Ă��邻�̎q�ɂ͋�z�͂������Ă���B��z�͂͐l����̋�ɂ�����̂ł���B���̒��ŕ����W�J���Ȃ���A�s�p�ӂɊp���Ȃ����ĎԂɂ͂˂��邱�Ƃ����邾�낤�B�������X�[�p�[�}���ł���Ǝv������ō��w�r���̑����畗�C�~�̃}���g��|�����Ĕ�э~��鏭�N�����邾�낤�B���Ȃ킿�A��z�͖͂{���A�����̈ێ���琬�ƒ������Ȃ��͂ł���A���ɂ͔������I�Ƃ����Ȃ�B
�@����ɑ��A�z���͂͐����ɑ��������̂ł���B���ŗh���傫�ȃ��c�f�̗t�ɓ��ł��Ȃ����̎���v������A�d�M���ɂ����݂��ċ�𗬂��_�����グ�Ȃ���A�t�ɓd�M���������o�����o�̒��ŁA�D�̃}�X�g�ɓo���Ă���C�ɂȂ����肷�鎞�A�����Ă���̂͑z���͂ł���B�āA�J�������Ă��܂�̂Ȃ����B����A�v�X�v�X�Ǝv�O�̃K�X�������Ă��܂��悤�Ɏv�����A���邢�͂܂��A�H���Ƌ��ɗ֊s�m�ɂ��Ă����v�O���A����C�̒��ŔZ��
�Ȃ������̉e�ƑΔ䂵�����Ȃ鎞�A�����Ă���̂͑z���͂ł���B�z���͂́A�����݂̌����ƑΉ����Ă���A���̏�ʂ��C���[�W�ʼn���邱�Ƃɂ���āA�������E�����������Ă݂�����̂ł���B�z���͎͂��R�ɑ����A�s���ɐ������ē������_��p�ł����āA�����͂��ە�����͂ł��� (��) �B
�@��������z�͂��A�ڂ̑O�ɂ�����̂��o���_�Ƃ��邱�Ƃ����肤��_�ł́A�����Ƃ̑Ή��������A����͏��߂̂��������ł���B�}���ق̉{�����̊��̏���L��Ɍ����Ă������ȏ��l�����������̐�ǂ��悶�o������A���̐�[�̏�ɏW�܂��ċ����ł݂���A���ɂ͐험�i�̏����S����S���ň����g���悤�Ƃ��Ă���̂����āA���܂��ܗאȂɍ����Ă������_�Ȃ̈�҂����̉��Ōӗ��Ȗڂ����Ď������ώ@���Ă���̂��C�Â����ɁA���̗��D�𐧎~
���鐺��グ����A����͂����A�z���͂Ƃ������͐q��Ȃ炴���z�͂ł���B
�@���āA��قǂ̏���ɂ�铲��́A�����̕s�@�ӂɑ��锽���Ƃ����`�ŁA�͂����茻���Ƃ̑Ή��������Ă���B��l�ڂ����̕����̒��� �����Ɏv�����Ă���ِ��̖ʉe��䍂��Ȃ���A���̑���Ƌ��L������͂��ł���[���������E���A�������Ɍ��@���Ă��邽�߂Ɋ�����ꂵ�݂́A���̌����ɑ��݂��鑊�肩��̉�����������Ή������鐫���̂��̂ł���B��l�ڂ����̌��@�̐��E����A���ِ̈��Ƌ��L�����銮���������E�Ɍ���������́A���̐��̃_�C�i�~�Y���ł���B�܂��A�͂���҂̐U������s���ł���Ɗ�����҂��A�����̎Љ�ʎЉ�ƌ��Ȃ����̔ے�̋C���́A���z�Љ�̃C���[�W�̗��ł��ƂȂ��āA���̃C���[�W�ɖL���ȓ����t�^���邱�Ƃ��낤�B�����̌����Љ�A�����̌����̂��ܖ������𖡂킨���Ƃ���A�z���͂��������҂����̐H�����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�Љ�̐��̕ʂ��Ԃ킸�A�������邱�Ƃł���B�z���͂������A����������ɓ��h��^������͂ł���B���̗͂́A�����Ƃ̃_�C�i�~�Y���������Ă���B
�@��z�́A���̐��̃_�C�i�~�Y���������Ă���A�ꍇ�ɂ���Ă͌����̐������������āA���̐��E����������u�����v�Ɏd���ďグ���ϑz�ƂȂ邱�Ƃ��炠�肤��̂ł���B�������A��������u�₵���w�閧�̉ԉ��x�k�t�����V�X�E�o�[�l�b�g(�āA�P�W�S�X�|�P�X�Q�S�N�j�A�P�W�X�Q�N�̍�l�̐S�x��y������m��҂́A��z�������炷�Z���ȏ[�����ⓩ���̖��͂��A���|��i�̒��ɕ������߂��邱�Ƃ��m���Ă��邱�Ƃ��낤�B���̍�i�̓o��l�������́A
���\�̕�����A���ɐ��������Ɖ����Ă����̂ł���B�����Ƃ��A��Ƃ̋�z�͂����邢��i�Ƃ��ď������ꍇ����ł͂Ȃ��B�W�����A���E�O���[�� �i���A�P�X�O�O�|�P�X�X�H�N�j�̂悤�ɁA�����ƗZ�a���ʋ�z�͂������̂܂܁A��Ƃ����l���Ɉڂ萦�݁A��z�Ɏ��߂��ꂽ��l���̂܂��̌����́A�����̐F��Z�����A���ɕ���S�̂��A�ߌ��̊��v�ւƗ�������ł����̂ł���B�������E���Ւf����������F�[���̓����ł̂݉\�ł������낤�A���C�ő@�ׂȓo��l���������D�萬������w�^�钆�x(�P�X�R�U�N��)�̖����A�����G���U�x�b�g���A�����̐S���䂫������̏��N�̌��ǂ��ĒJ�֒ė������ʂ�N��ɕ`����҂̕M�́A���炩�ɂ��̔ߌ��ɐ����Ă���B�����Ƃ��A�ނ̍�i�̗���́A��z���̂̐����ł���Y�R�Ƃ����A�ɖ��ȗ��ꂪ���̂܂ܓW�J����Ă��邽�߁A
���I�Ȍ����𐫋}�ɋ��߂�ǎ҂ɂ͏ł�������������邾�낤�B���ꂪ�A�����悤�Ȍ����V���I�ȋ�z�̐l�A�R�����[�g�E�t�F���f�B�i���g�E�}�C�A�[(�X�C�X�A�P�W�Q�T�|�P�W�X�W�N)�̏ꍇ�ɂ́A�{�����I�ȗ��j��f�ނƂ��Ă��邽�߂��A�قƂ�ǂ̍�i���ɖ�����悳���A�o��l�������̈قȂ���̂Ԃ��荇���������ɓ������ꂽ�A�h�X�g�G�t�X�L�[�̖���ɂ����Ȃ��w�����N�E���i�b�`���x(�P�W�V�U�N��)��A�Z�Ɩ��̗d�����ȋߐe���I�G���X���Y���w���ٔ����x(�P�W�W�T�N��)�ȂǁA�����̍�i�̂ǂ̉ӏ��ɂ����Ă��A�ǎ҂͋��\���E�̉ʎ��𖡂킢����i�߁A�I�k�ȍ\���̍Ō�̌����ł܂����\����̂ł���B���̃}�C�A�[���A���͂��̐��U��ʂ��Č����Љ�̉c�݂ɉ���邱�Ƃ̂ł��Ȃ������A���̎Љ�I�Ȕp�l�ł������̂ł���B���_�a�@����������Ă����S�O�ォ��U�O��܂ł̖�Q�O�N�ԂɎc�������Ɨ��j�����Ƃ��A���҂̐��E�Ɍ��o�����ނ̑��݂̂��ׂĂł������B����Δނ́A�قƂ�Ǒ��̌����ɂ̂ݐ����Ă���A�ꍇ�ɂ���Ă͑S�����Ղ��c���Ȃ��܂܂ɏ������邱�Ƃ����肦���ނ̋�z���E(���̌����j�́A���܂��܂��̓��قȕ\���͂ɂ���ĕ��|�Ɍ��������A�����ꂽ���E�̓����́A���̗d�����ȓ����̂���悤���A���̐��̐l�Ɋ_�Ԍ����Ă��ꂽ�̂ł���B
�@�����������\���E���y���߂�Ƃ������Ƃ́A���������ǂ��������ƂȂ̂ł��낤���B���̋��\�����킵�Č����鐢�E�ɓ��荞��ł��鎞�A��X�͈̏�̂ǂ̂悤�ɐ����ł���̂ł��낤���B��X�̓��̒����щ���d�������́A����Ӗ��ł͌������E�̑��݂𗽉킵�Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���̂悤�ȋ^��ɂƂ荇��Ȃ��l������͂��ł���B���������l�̗���ɂ͓�l������B���̈�́A��z�̃��A���e�B�ɐe�����Ȃ��B���I�Ȃ��̂̍l����������l�����̂��̂ł���B�ނ�͌������낤�B�Ǐ����̔]�̊������ӎ��̓��ɉf���o���Ă������݂������݂łȂ����Ƃ����߂���m���Ă��邭���ɁA����������݂Ɠ���ɘ_������悤�ȍ��o���ӎ��I�ɘM��ł���c�_�ɂ͕t����������Ȃ��B�v����ɗd���͔]���̐_�o�̓����������������e�ł�
��ƁB
�@������̗���́A�d���̎��݂������F���Ƃ��Ď咣����_��w�̂��̂ł���B���̐_��w���A��I�����̋q�ϓI�F���������Ƃ����ނ̂��̂ł������A���w�I�ȋ�z�͐������F����W���霓�ӓI�s�ׂƂȂ�̂ł���B
�@�����Ŕ����ȈႢ���w�E����K�v���o�Ă���B����́A�O�����猩�Ď�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��]���̃C���[�W�̑��݂ƁA�������A�O���̌����̓��ɂ͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ���I���݂Ƃ́A���݂̎d���̈Ⴂ�ł���B�]���̃C���[�W�����̐l�ɂƂ��āA��g�ł͂Ȃ��^�̌����ƂȂ������ɂ́A�ނƔވȊO�̐��E�Ƃ́A�ϑz�̋��E�́A���ƊO�Ƃɕ��f����邱�ƂɂȂ�B�����ނ��^���̓��ɂ���Ƃ����̂Ȃ�A�O�̐��E�����ƂȂ�B�ǂ݂̂��A�����܂œ��ƊO�Ƃ͔w���I�ł���B���ꂪ��I���݂̏ꍇ�A���̎��̂́A����ɂ͎ʂ�Ȃ�����������Ă��邽�߁A���I�C���[�W�ƍ�������₷�����A�l�̎�̂̊O�ɑ��݂��邠����������Ă���B���̑��݂��^���ł���Ǝ��ꂽ�ꍇ�A��ʂɂ́A��z�����݂Ǝ��Ⴆ��ϑz�̗ނƍ������ꂪ���ł��邪�A���̐^���́A�O�̐��E�̎��݂̐^���Ƌ���������̂ł���B�_��w�ɂ��A��I���E�ƕ������E�͋��ɁA���������ɑ�������́A�قȂ錰���ɂ����Ȃ�����ł���B
�@�d���̑��݂���ے肷��l�́A���̋�ʂƖ����ł����āA�p���ĒP�������ł��邪�A�d���̑��݂�~����Q���I�Ȑl�̏ꍇ�������������̂ɂȂ�B
�@���w�I�ȋ�z�͂̑n��������������l���A�d���͂���A�Ƃ������Ƃ����邩������Ȃ��B�������A���̍ہA�u��X�̔]���Ɂv�Ƃ����A�ނɂƂ��ĎU���I�Ȍ��t���A�B�g�̌`�ŏȂ���Ă���ɂ����Ȃ��B���w�I�ȋ�z�͂ɂ��e�����A���A���̒m���Ƃ������Ƃ��A���̂ق����팻�ۂƂ��������鎖���ΐM���Ă���l�̏ꍇ����Ԕ����ƂȂ�B���̏ꍇ�A��I���݂̐��E�́A���ɕs�����Ȍ����ɑ��Ή��̍�p���ʂ�����C�f�A�̐��E�ł�������A���Ɏ����̎����݂����������ށA�S�x����W�]����p�ӂ�����̂ł������肵�ėh�ꓮ���B���w�I�ȋ�z���֗^���鎞�ɂ́A������̏ꍇ���A��I���E�́A����̑ΏۂƂ��ẮA�O��Ȑ��E�ł���ɂƂǂ܂�A���̐��E����������A���邢�́A�킭�킭�������̂Ƃ��߂������`�ł���B�����ČȂ�̔]���̐��E���������E���ǂ̂悤�Ȍ`�ŗ��킵����̂��Ƃ������Ƃɂ͊S��������̂́A��I���E�������̊O�ɂ��邩�ۂ��̊m�F�́A���������ċً}��v���Ȃ������Ȃ̂ł���B
�@�����āA���ꂪ���i�ȗ�I�����̔F����ڎw���A�����������[�h���t�E�V���^�C�i�[(�P�W�U�P�|�P�X�Q�T�N)�̏ꍇ�ɂ́A��I���E�͓���̑Ώۂł͂Ȃ��A�z����A���̑g��������������A�l�̂̍\����Љ�̎d�g�݂���������̂Ɠ����A�Ȋw�I�ȔF���ΏۂƂȂ�̂ł���B�����āA���ӓI�Ȍ����A��ϓI�Ȕ��f���Ȋw�ɂ����ċւ�����悤�ɁA���̐��_(��)�Ȋw Geisteswissenschaft �ɂ����Ă��A��z��B���ȗ��`���͔r������̂ł���B�V���^�C�i�[���J�������I�������A���ɂ��܂�ɋ��b�I�ł��邽�߁A�Q���I�Ȑl���A���w�I�C���[�W��^���Ă������̂Ƃ��āA����ɐڂ��邱�Ƃ������B�~�q���G���E�G���f(�ƁA1929-1995�N)�����̈�l�ł���B�������A�V���^�C�i�[���g�́A�l�ɋ�z�̎��^�������͂Ȃ��̂ł���B�V���^�C�i�[�ɂ͖{�_�Œ�`�����Ӗ��ł̋�z�͂͂قƂ�ǂȂ��B�ނ̏q�ׂ鎖�����A�펯���猩��Ƌ�z�I�ł���Ƃ����ɂ����Ȃ��B�������A�F���̐ۗ��̂��Ƃɑ��݂��鐶�́A�L���Ȏ����𖾂炩�ɂ��遃�z���́��̓V���^�C�i�[�̏d��Ƃ���ł���B���̎�̑z���̗͂{���́A�V���^�C�i�[���n�n�������@���h���t�w�Z����ł����ɏd������Ă���B�����āA����͌|�p�F���_�I�Ȍ`�ŃV���^�C�i�[�̖剺�������ɓ`�����A
���@���h���t�w�Z�ł́A�F���I�^�����瓱���o���ꂽ���̑S���̊����ׂ��A�V���^�C�i�[�̕҂ݏo�����I�C�����g�~�[���炪�p������Ă���̂ł���B�����������I�ȑz���͂̎�����ł���Q�[�e���A���l�E��ƂƂ��čŗǂ̖͔͂Ƃ��Ă���V���^�C�i�[���g�A���邢�͔ނ��ݗ����ނ̎���������𑱂��Ă���l�q�w����́A���ɋ�z�͂ɑ���ᔻ�I���������ɂ���̂ł���B
�@����l�q�w������́A�~�q���G���E�G���f�����̂悤�ɕ]���Ă���B
�u�G���f�̃t�@���^�W�[(����͖{�_�ł͋�z�͂ƌĂԂׂ����́F�_��)�́A�Q�[�e�́w���m�Ȋ����I�t�@���^�W�[(����͂����ނˁA�z���́F�_��)�x�ƑS�R��v���Ă��Ȃ��v�B�u���̐����������(�G���f�̂��ƁF�_��)�̃t�@���^�W�[�́A�|�p�F���_�I�E�|�p�S���w�I�w�K�������A���g���|�]�[ �t(�l�q�w�k)�̑����ɂƂ��ẮA�^�킵�����̂ł���v�B
�@�����̐S�g�̌��S�Ȕ����ڎw�������A���S�Ȗ�������_�Ƃ̐��i��A�a���A���_(��)�Ȋw�I�ϓ_�Ɋ�Â���w�ȂǁA�V���^�C�i�[������̂�������͑����ʂł��������A���ׂāA���̍m�肪���̊���Ȃ��Ă�����̂���ł���B����́A��I�i������b�Ƃ��A�S���S�^�̃L���X�g�̔�Ղ��A���̐i���̏d�v�Ȓʉ߃|�C���g�ƌ��Ȃ��V���^�C�i�[�́A�P�̕������������p���ƊW���Ă���B������_���`�����܁A�����I�Ȃ��̂ɋ߂Â����Ƃ�����Ƃ���A�V���^�C�i�[�̐��_(��)�Ȋw�̓L���X�g�I�Ȃ��̂Ƃ�����B�����āA��z�̎��R��Ԃ̒��ł́A����������������ꂤ��̂ɔ�ׂ�
�ƁA�V���^�C�i�[�̔F�������I���E�ł́A��ɑP�ƈ��Ƃ������A�ϗ��I�z���͂��v������A�����ȋ�z����������邽�߁A��z�̎��R�͍S������������Ȃ��B
�@���́A����������z�̓L���X�g�ƑΗ������I���݂ł��郋�V�t�F���̉e�����ɂ��錻�ۂƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B�u���V�t�F���Ƃ́A�l�Ԃ̓��ɁA������M���I�ȋ����A�������_���`�I�X�������N����悤�ȗ͂̂��Ƃł���B���̎����N�����̂́A�l�ԂɎ������ď㏸����悤������������́A����ΐ����w�I�ɐl�Ԃ̌���N���������A�l�Ԃɉ��Y�ꂳ������̂̂��ׂĂł���B�v(�V���^�C�i�[�S�W�P�X�R�ԁw�Љ�̓����I�Ɍ���x�A�P�U�S �y�[�W�j
�@�G���f�́w�͂Ă��Ȃ�����x�̃t�@���^�[�W�G�����̕P�N�ł���A��z�͂̏ے��ł���q�c�Ȃ�����̌N�r�����V�t�F���̉��g�ł���Ƃ���w�E���h�C�c�ł͂Ȃ���Ă��邪�A���߂��邱�Ǝ��̂̐����ʂƂ���A����͊Ԉ�����w�E�ł͂Ȃ��B�V���^�C�i�[�͔F���I�Ƀ��V�t�F���𑨂�������̂́A����͂������z�͂Ƃ��Ė��키�قǂɂ́A���̉e���ɐ��܂��Ă��Ȃ������B�ނ���z�I�v�f�ɑ��A�������Ƃ��v����悤�ȑԓx���Ƃ邱�Ƃ̈���͂����ɂ���B���������ʁA������o�ς���̐��_�̎��R��A�l��I�Ό�����̎��R�Ȃǂ́A�ނ̉F���I��I���삩��ϋɓI�ɓ����o�����Ƃ���ł���B
�@���㕶�w�̋�z���Ɋ��ꂽ�҂ɂƂ��āA��ΓI�P��_�I���݂�^���ʂ���m�肵�Ă݂����邱�Ƃ́A���܂�ɂ��ʉf�䂢�B���������p�̕��ɁA���̍���̗ǂ��������錻��l�́A�V���^�C�i�[���猻�㕶�w�����܂ꂦ�Ȃ����Ƃ������Ƃ邱�Ƃ��낤�B�V�[�^�C�i�[�Ȃ�тɐl�q�w������ɂ́A�A�C�U�b�N�E�V���K�[(�P�X�O�S�|�P�X�V�W�N�x�m�[�x�����w���)�́w���̖��H�x�̉��l���A�Ƃ��Ă��F�ߓ���Ƃ��낤�B���́A����̐��E����o�Ă����悤�ȃ��_���l��Ƃ́A�������ɂ߂Č���I�ȋ����������p�I���I���o�Ɏh���I�ȋ������o����l�́A��z�͂̌����ɂ���B��ȓo��l���̈�l�A�O�d���̈���������}�[�V���́A�܂��ɔ������C����u�d���v�ł���B�܂��A���̃I�J���g�I�v�f�̂����i���A�����̋C�z�̕Y����z�I�Ȃ��̂ł���B
�@���āA�ȏ�ŁA�V���^�C�i�[���d���̑��݂ɂ��Č��̂��ۂɍl�����ׂ��_�͑�̏q�ׂ��B�V���^�C�i�[���q�ׂ�d��(���R��)�̏ڍׂ��A��z�̗Ƃɂ���l�����邾�낤���A�̌n�I�ϑz�̏Ǘ�Ƃ��ĎQ�l�ɂ���l�����邾�낤�B�������A�V���^�C�i�[�́A�l�Ԃ��̂�ׂ��i���̓��Ɗ֘A���āA
��̗�I�������q�ׂĂ���̂ł����āA���̍u���̒��O�ł������_�q�w��������A�����̐��́A���ނׂ����������̂��z�����邱�Ƃ��A�����Ŗ]�܂�Ă����̂ł���B
�i���̂��Ƃ̓����_�[���C�t�ɘA�ڂ����V���^�C�i�[�̐��E �S
�C�T �̗d���_�Ƃقړ������e�ƂȂ�̂ŁA�ȗ�����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��
�@�z���Ƌ�z�̋@�\���ŏ��ɋ�ʂ����Ə̂��Ă���̂́A�C�M���X�̎��l�E��]�ƃT�~���G���E�A�C���[�E�R�[�����b�W(�P�V�V�Q�| �P�W�R�S�N)�ł���B�������R�[�����b�W�̋�ʂł́A�q��z�r�͖����qFancy�r�ł����āA�q�z��(Imagination�r�̕����]������Ă���B�_�҂̂����q��z�r�̗L����v�f���A�R�[�����b�W�ɂ����ẮA�啪�q�z��(Imagination�r�̒��ɂ܂��荞��ł���B�ނ͂����q�ׂĂ���B
�@���́u�z���́v(Imagination)����Ƒ��Ƃɕ����čl����B���̑z���͂͂�����l�Ԃ̐�����͂ł���A�܂����̒m�o�̈�ԍŏ��̍쓭�҂ł���Ǝ��͎咣���邪�A����͂܂��A�����́u�_�v(I am)�ɂ�����i���Ȃ�n����p���A�L���̐S�̒��Ŕ���������̂ł�����B���̑z���͂͑O�҂̂����܂ł���A�ӎ��I�Ȉӎu�Ƌ���������̂ł��邪�A���������̍�p�̎�ނɂ����Ă͑��Ɠ��l�ł����āA�������̊����̓x�����Ɨl���ɂ����ĈقȂ���̂ƍl����B����͍đn�����邽�߂ɗn�����A�g�[���A�g�U���A���邢�͂��̉ߒ����s�\�ȏꍇ�ɂ����Ă��A�Ȃ���ɗ��z���ƒ��a����ƂɌ������ē����B���ׂċq�̂�(�q�̂Ƃ���)�Œ肵�������ł���̂ɔ����āA����͂܂��ɖ{���I�ɐ��������̂ł���B
�@����ɔ����u��z�v(Fancy�j�͌Œ�I���邢�͌���I�Ȃ��̈ȊO�ɁA���炻�̑���������Ȃ��B���ہA��z�́A���Ԃ���ы�Ԃ̒������������ꂽ�L���̈�l���ɉ߂��Ȃ��B��������́A����ꂪ�I���ƌĂ�ł���ӎu�̌o���I���ۂƌ������A������ɂ���Đ����B��������z�͕��ʂ̋L���Ɠ��l�A�A���̖@���ɂ���Ċ����i�Ƃ��Ă��̂��ׂĂ̑f�ނ���e���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(�w���w�]�`�A�T�~���G���E�e�C���[�E�R�[�����b�W���A�j�c���g��A��Ԃ�肠�I���A�@����w�o�ŋǁA�P�X�S�y�[�W)
�@����J�ER�ER�E�g�[�L��(�P�W�X�Q�|�P�X�V�R�N)���w�t�@���^�W�[�̐��E�@�\�@�d������ɂ��ā@�\�@�x(���F�t�q��A������)�́u��z�v�̍��ŁAFancy���u�Â��t�@���^�W�[�Ƃ������t���k������A���l�����������t�v�Ƃ��Ȃ���A�t�@���^�W�[�ƃC�}�W�l�C�V�����ɂ��ďq �ׂĂ���B�������A���x�͋t�ɁA�t�@���^�W�[���ߑ�]������A�C�}�W�l�C�V�����̓t�@���^�W�[�̋@�\�̈ꕔ�ɂ���Ă���B���́q�t�@���^�W�[�r�͘_�҂̂����q��z�r�̕K�v���������Ă��邪�A�q�z���r����������\����������Ă��Ȃ����݂��c��B
�@�Ȃ��A�d�����l�ɕ��ނ��邱�Ƃ͊��Ƀp���P���X�X(�P�S�X�R�|�P�T�S�P�N) ���A���R�̎l�匳�f�A�A���A���A�y�Ƃ̑Ή��ōs�Ȃ��Ă���A���̗d�����̏q��������ł���A�����̕�������g�ň�v���Ă���B�����V���^�C�i�[�̏ꍇ�A���̐����͋ɂ߂ĉ�U�I�ƂȂ��Ă���B
�@�p���P���X�X�́w�d���̏��x�ɂ��Ă̕����FTHEOPHRASTUS
PARACELSUS WERKE,besorgt von Will-Erich Peuckert. Basel, Schwabe & CO.Verlag, BAND�V,Liber de nymphis
���̑��A�S�W�͊e�킠��B���̓��e���Ă��Ƃ葁���m�肽���ꍇ�́w�閧�̔������x(�ے��N�w���n�M�A�}�����[�EP�E�z�[�����A������O�� ��A�l�����@)�A�u�l�匳�f�Ƃ��̏Z���v(�Q�R�T�|�Q�T�U�y�[�W)�E�w�p���P���X�X�̐��U�Ǝv�z�x(�勴���i���A�v���m)�A����͂P�O�A�w�d���� ���x(�P�W�O�|�P�W�S�y�[�W)�B
�@���̑��A�V���^�C�i�[�����y���Ă��Ȃ��d���������ɂ���R����B����Ɋւ��Ắw�d���̐��E�x(�t�����X�E�h���b�g�����A�䑺�N�]��A������)�̊����ɂ���u�d�������T�v���Q�Ƃł���B�V���^�C�i�[�̕��ނ��d���̗ނ��Ă���Ƃ���A�e�ނɑ�R�̎킪���邱�Ƃ��z�������B�Ȃ��A�h���b�g���̓`���[�g���n�̃G���t�ƃP���g�n�̃t�F�A���[�Ƃ���ʂ��Ă���A�����ɂ���ėd���̕\�����Ⴄ���Ƃ������Ă��苻���[���B
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂�
���Ƃ���
�u�V���^�C�i�[�̐��E����v�V���[�Y��V���Ɏn�߂邱�Ƃɂ����B���������ɂȂ��ēǂ����[�����̂ł��A�|��ɂ͎��Ԃ������邵�A���̂܂ܔ]���ɂƂǂ߂Ă������肾�������A�l�ɘb���Ă݂�ƁA�����Əڂ����m�肽����l������̂ŁA����A�ȒP�Ȍ`�ł������A�������Љ�Ă������Ƃɂ����B
�@�����͓lj�͂̒b�B�ɂȂ�悤�Ș_�q�̎d�������X�Ƒ����Ă���A������₷���܂Ƃߏグ���Ƃ́A������ʂ�ǂ����ł͌����Ƃ��Ă���A�ւɋC�Â����Ă���A�����g�̂��߂ɂ��Ȃ����B���̖ډ��̖��ӎ��ł���A�z���́i�{�_�̒�`�ł́A�ނ����z�́j�ƔF���̑����Ƃ��ւ�肪����
�āA�S���Ԃ̏o�Z�������݂Ȃ���P�O���������Ă��܂������A�܂�Ȃ���Ƃł͂Ȃ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�X�W�S�N�X���P�O��
���Ƃ����i�z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���ɂ������āj
�@
�@�{�_�͂P�T�N�߂��O�ɏ��������̂ł��B����Ɋ�Â��āA���̂T�N��u �V���^�C�i�[�̐��E�v�i�S
�C�T�j �����܂�܂����B�{�_�ł͕��w�I�ȃt�@���^�W�[�ƁA�V���^�C�i�[�̗�I���E�F���Ƃ̈Ⴂ�ɏœ_�ĂĂ��܂��B���w�I�t�@���^�W�[�́A���퐢�E�Ɛ_��w�̐��E�Ƃ���茋�Ԕ}��ɂȂ�͂��Ȃ��ł��傤���B�����Ƃ��A���͈ꎞ���w�̐��E�Ƃ͑a���ɂȂ��Ă��܂����B���\�̐��E���A�������E�̕����f�R�ʔ����Ȃ�������ł��B���̌����Ƃ����̂́A���������̌����ł͂Ȃ��A�萯�p�ȂǂʼnB�ꂽ�A������������錻�����E�ł��B�s�v�c�ȘA�ւ����X�ɖ�����������̘A���ł����B�������A����̍u�`�ŕ��w��_����悤�ɂȂ��Ă���A�܂����w�̐��E���ӎ�����悤�ɂȂ�܂����B�����āA���w�I�t�@���^�W�[�Ɛ_��w�I�����Ƃ̈Ⴂ���ӎ��ɏ���Ă��܂����B�w���ɒ��ځA�_��w�I�u�����v��`���邱�Ƃ͓�����A����Ȃ��Ƃ����Ă������ǂ��������ł��B������ԐړI�ɁA�܂��͕��w�I�t�@���^�W�[�Ƃ��Ĉ��������A�����ł��傤�B���̏�Łu�����v�ɋ����������҂ɂ́A���̋����ɉ�����A�Ƃ������j�ɂ��Ă��܂��B�d���ɂ��Ēm���Ă��邱�Ƃ�����������A�d���̑��݂�M���邩�Ƃ����A���P�[�g���Ƃ���������Ă��܂��B�t�@���^�W�[�Ƃ��ĂȂ�����w���͑����ł��B���݂ƂȂ�ƁA�P�����炢�ł��B���̐����������̂����Ȃ��̂��́A��r���鎑�����Ȃ��̂ŕ�����܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�X�X�X�N�R���Q�T��
���Ȃ��A��z�Ƒz���̋�ʂɂ��ẮA�u�V���^�C�i�[����̔w�i�����v�̒��́u �A���g���|�]�t�B�[�ɂ�����t�@���^�W�[ �v�ł��q�ׂĂ��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�W�`���ɖ߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڎ��y�[�W�ɖ߂� �@