シュタイナー教育の背景
2回目
アントロポゾフィーにおけるファンタジー(1987年5月7日)
皆さんは、今日、直線や曲線、角張った動き、同心円の動きなどのフォルメンを、子安さんと共に 体験して下さったと思います。そうした動きが、精神世界の法則に沿おうとしたものであるというお話も、あったことと思います。今日私は、そのフォルメンと も関連のある、「アントロポゾフィーにおけるファンタジー」のテーマで、お話いたします。
もっとも、フォルメンの実際や、その説明は、子安さんにすっかりお任せしまして、私は、その原理となっているアントロポゾフィーのファンタジーについて、 その特質を述べさせていただきます。
それも、どちらかというと、ややアントロポゾフィーの外側から、その輪郭を見ていく、という方法をと ろうと思います。前回は、アントロポゾフィーに、三つの柱があると申し上げました。一つの柱は、<善なるものへ 向かう意志>でした(板書)。前回も申し上げましたように、こうしたストレートな表現に、なにか抵抗を感ずる方もおられるかもしれませんね。しかし<太陽 的なもの>へ向かうその意志の背後には、深い英知が秘められています。その英知は、太古においては日常的な事実だったのですが、ある時を境にして、一般の 人からは見失われてしまったものです。その後、それは宗教の中で一種のあこがれに転化して続いてきました。シュタイナーは、その見失われた英知、あこがれ の形でぼんやり望まれるしかないものを、再び精神世界の中に、明確な事実として発見したと主張するので す。その詳細が精神科学となったわけです。その再発見の手段は、厳密な方法に基づいた認識の道ですが、これについては、最終回にお話するつもりです。シュ タイナーは、善なるもの、<太陽的なもの>の本質を、超感覚的に認識したのです。
アントロポゾフィーの二つめの柱は、<明確な認識>でしたね(板書)。それは、今述べました超 感覚的な認識の際にも当てはまります。しかし、その実際は、最終日にお話することにいたします。今は、<明確な認識>を、感覚世界に限ってみましょう。日 常的な感覚世界においても、明確な思考と認識が求められるのです。
前回は、この柱を、学問、あるいは科学と訳せるWissenschaftに置き換えてみましたね。し かし、科学というなら、自然科学も、明確な認識を目指しています。自然科学は、物質世界の仕組みを、どこまでも追求していく学問ですね。
ところが、明確な認識といっても、たとえば、原爆を落とされた惨状を前に爆弾の威力を数式で計算する ような、魂を欠いた認識もありえるわけです。明確な認識に、もし善なる方向づけがなかったら、冷酷な非人間的なものになることだって、ありえるわけです。 私は一時期、といってもほんの一ヶ月間ですが、理科系の大学の物理学科に籍をおいたこともありまして、自然科学の成果には、今も強い関心があります。シュ タイナーが、ウィーン工科大学に籍をおいた後も、同時代の自然科学の流れとその成果を、常に視野にいれていたことなども、私には違和感なく受けとめられる 気がします。
この自然科学がもっている欠陥は、シュタイナーも言うように、物質がすべてであるという考え方に固執 していることです。この科学の中には、魂も愛も、構造的に入り込めません。魂や愛は、哲学とか宗教の立場から、外から働きかけるしかありませんね。あるい は、自然科学者が専門の科学とは別に、自らの良心に基づいて、たとえば、核兵器保持に反対を唱える、という風になります。遺伝子工学や臓器移植にまつわる 問題でも、同じことです。人間を物質的にしか捉えられない医学自体、自然科学自体が、深い愛の問題や、善なるものを扱うことは、本来無理があるし、矛盾し ていることなのです。
自然科学が、宗教や、哲学、そして芸術などと、全く別個のものになってしまった時代の流れをシュタイ ナーは指摘しています。こうした状況は、その時代の流れに起因しているわけです。精神科学の場合、アントロポゾフィーの場合は、これとは様相を異にします。
二つめの柱<明確な認識>は、一つめの柱<善なるものへ向かう意志>によって貫かれています。それは 善なる方向づけを身におびています。そして、<善なるものへ向かう意志>も、冒頭に述べましたように、シュタイナーによって、超感覚的に認識された英知で あるわけです。それは、単なる情緒に基づくものではなく、明確な認識から生まれているのです。
このように、一つめの柱と、二つめの柱は、別々に立っているのではなく、互いが互いを生み出している わけです。三つめの柱は、<芸術>でした(板書)。この芸術も、やはり<善なるものへ向かう意志>、<太 陽的なもの>に貫かれた芸術です。つまり、アントロポゾフィーの第三の柱<芸術>は、第一の柱<善なるものへ向かう意志>に貫かれています。そしてまた、 シュタイナーは、芸術の本質も、超感覚的に認識するわけです。話がやや抽象的になってきましたから、その内容まで申し上げましょうか。彼によれば、芸術作 品は、感覚世界を越えた精神の光を宿らせているものなのです。それは、精神世界から来る光を帯びています。もっと具体的に申し上げましょうか。芸術は、 シュタイナーによれば、人間のエーテル体という、微妙な、目には見えないけれども実在する生命力の担い手に、働きかけてくるものなのです。芸術は、人間の エーテル体に働きかけるというわけです。彼は、芸術の本質を、そのように認識したのです。ですから、第三の柱<芸術>は、このような超感覚的な形ではあり ますが、第二の柱<明確な認識>によって照らし出されている、ということになります。
このように、アントロポゾフィーの三つの柱は互いに有機的に関連し合っています。ファンタジーの話に入る前に、このように長々と前置きに時間を費やしましたのも、ファンタジー や芸術が、アントロポゾフィーでは、それだけで独立したものではないことを、知っていただきたかったからです。現代は、箇条書き的に並べるだけの教え方、 そして覚え方が蔓延していますので、注意を促そうと思ったまでです。
さて、今、善なる意志に貫かれた芸術と申し上げましたが、現代芸術の多くは、必ずしもこの要件を満た しません。シュタイナーが芸術作品という時、これまでの、伝統の中で、模範となるものが念頭にあるのは、当然ですね。それは、古代ギリシャ・ローマの芸術 や、ルネッサンスの巨匠時代のもの、あるいは古典主義のもの、などです。もちろんシュタイナーの視点は、単に古いものはいいものだとか、昔はよかった、と いうところにあるのではありません。彼はいつも未来に向かっている人です。ただ、人類の文化遺産は、長大な時間と英知を注がれて出来たものでして、そこに とり上げるべきものが多いということなのです。
たとえば、ホメロスの詩に、シュタイナーは精神世界の秘密を見いだします。ミケランジェロの彫刻に も、精神世界を直観しえる者だけが刻み込める英知をみいだします。巨匠時代の画家が描く天使は、空間の秘密の力を知る者だけがなしうる配置で、宙に浮かん でいます。これが後代の画家の手にかかると、天使は今にも落ちてしまいそうに見えると、シュタイナーは言 います。もちろん偉大な芸術家たちが、超感覚的な認識を行うための修業の道を歩んだというのではなく、当時の芸術家たちの精神には、自然にそのような直 観、ひらめきの訪れがあったということです。当時の芸術作品は、精神世界の光を、特に明確な形で地上へもたらしていたと、シュタイナーは考えるのです。
そして、シュタイナーによれば、現代、「芸術」として通用しているものの多くは、芸術の価値をもたな いことになります。一九〇〇年以降、つまり二〇世紀に入ってから、芸術家は、自分のファンタジーが作品を生み出しているのだという自意識をもつだけになっ てしまった。精神世界のことは念頭になくなってしまったと、シュタイナーは言います。たとえば、目に映る事物の表面だけを描こうとする自然主義は、彼に よって、唯物的であるとの烙印を捺されています。奥深い精神の秘密を作品に込めることのできた芸術家のみが、模範となるわけです。その観点で、音楽では ワーグナーが、後代のものではありますが、高く評価されています。
それは、言葉の芸術家であるゲーテについても言えることです。シュタイナーは、ゲーテから多くのもの を吸収しました。といっても、ふつうの意味で、ゲーテから影響を受けた、という風には言えないと思います。たとえば、ニーチェが、初期にショーペンハウエ ルから影響を受けたとか、そのショーペンハウエルが、東洋的な思想の影響を受けているとかいうのと、同じようには言えないと思います。
影響を受けるという場合には、ものの感じ方に近しいものがあり、その上、自分がぼんやり感じていた方 向性をはっきり示されたような時のことをいうのでしょう。しかし、シュタイナーの場合は、単純に、そうは言えないのです。それは、シュタイナーが、超感覚 的にゲーテ自身や、ゲーテの作品を洞察し、認識したという点で、違うのです。いわば、感情的なものを介した影響関係だけではなく、事実認識がそれに加味さ れている、ということなのです。ゲーテの素質が、一体どのような過去に由来しているのか、といったことをシュタイナーは知ってしまうのです。それは再生と か、秘儀参入とかいう言葉と関連のあることなのですが、これはまた、別の機会にお話しましょう。とにかくシュタイナーはゲーテの作品の内には、宇宙の摂理 や秘密の多くを見てとるのです。たとえば、『メールヒェン、「緑の蛇と百合姫のメールヒェン」に開示されたゲーテの精神』(R・シュタイナー著、人智学出 版社刊)(板書)などに、その一端が示されています。さて、しかし、ドイツ文学の世界では、ア ンチ・ゲーテというか、ゲーテ嫌いの流れがあります。これは別に、一つの文学的な流派になっているわけではなく、漠然としたものです。一番簡単に言えば、 権威に対する反発です(聴衆、笑い)。しかし、権威と言ってしまうと、ゲーテに対するマイナスのイメージも加わりますが、そのイメージを取って言えば、偉 大な光に対する反発、という風に言えましょう。偉大な太陽の、明るい健全さを厭う屈折です。こうした感じ方というものは、ドイツ文学に限らず、現代の世界 には、いろいろな形で存在していますね。実は、私にも、かつてはそのような感じ方に染まっていた一時期がありました。
この辺の話になりますと、アントロポゾフィーを外側から見る立場も導入することになります。一つの考 えの中に埋没していては見えない輪郭が、これではっきりするかもしれませんので、敢えて述べることにします。シュタイナーも、若い頃、アンチ・ゲーテの芸術グループに加わってみて、彼らの感じ方をつかも うとした時代がありました。そのような柔軟な時代がありました。デレ・グラツィエ家で行われた反ゲーテ主義者たちの集まりが、それです。デレ・グラツィエ を評して、シュタイナーは自伝の中で、次のように言っています。なお、デレ・グラツィエは女性です。「彼女は自作を朗読し、確固たる言葉使いで彼女の人生 観を語り、この世界観によって人間生活を照らし出した。」 − いいですか、この後に注意して下さい − 「それは太陽の光による照明ではなかった。そこ にあったのは、陰欝な月光であり、不穏な曇天であった。しかし、その下に生きる人間たちの住処からは、人間を焼き尽くす情熱と幻想の炎が、闇に向かって高 く燃え上がっていた。」
これは、翻訳で出ている『シュタイナー自伝』の上巻の一二四ページにあります。
私の知っている、日本人のドイツ文学研究者や、詩人や、芸術家の中にも、ゲーテ嫌いの人はいま す。どんな人たちかと言いますと、カフカやムシルが好きだったり、神秘思想に密かな興味を抱き続けるような人たちです。あるいは、強い自我意識をもってい て、神のような存在が自分の上にあることに我慢ができない人たちです。ニヒリズムの感覚に親しい人たちです。こうした人たちの、ゲーテに対する反発は、単 に権威に対する反発というよりは、<太陽的なもの>に対する反発と言えましょう。それは、シュタイナー自身が、いみじくもグラツィエを評して述べたよう に、「陰欝な月光」で象徴されうるあり方です。月の光なんですね。ここに、太陽と月という対立が出てきているわけです。「人間を焼き尽くす情念と幻想の 炎」という形容と合わせ考えれば、ここでシュタイナーが、ルツィファー的な力を思い浮かべていたことは確かです。ルツィファーというのは、ルシファーと か、ルシフェルとか言うこともあります。このルツィファーについては、今日、またあとで述べようと思います。ここでは比喩的に、<太陽的なもの>に対する アナーキーな反発、というにとどめておきます。比喩を用いるなら、人間の上に位置する神は、天にあって、人間の上から光を注ぐ太陽にたとえられますね。
さて、アンチ・ゲーテの彼らは、いわば人間自我を、一つの秩序の拘束の下におこうとする力に対 し反発する、精神的アナーキストであるとも言えます。彼らはアントロポゾフィーの<太陽的>な性質にも反発することでしょう。太陽に反発する月、という風 に比喩できる対立です。こうした感覚が、特に現代の芸術運動の中に存在していることを、はっきり捉えておかないと、アントロポゾフィーの芸術の輪郭は分か らないと思います。<太陽的なもの>の外側には闇の力や、屈折や、ニヒリズムや、幻想や夢想の世界が、あるのです。アントロポゾフィーの芸術は、少なくと も、それらを、肯定する形では含んでいないのです。先ほど申し上げました、善なる意志に貫かれた芸術とは、こういうことを意味しているのです。
さて、芸術活動にはファンタジーが必要とされます。このファンタジーも、シュタイナー、そして アントロポゾフィーにあっては、幻想的なものは排除されています。特に最近フアンタジーという言葉が氾濫していますね。現代にファンタジーと言うとSF ファンタジーのような、幻想的なものも含めて考えられていますが、アントロポゾフィーで言うファンタジーは、勝手気ままに現実を逸脱する夢想の力とは、全 く違うのです。特に、認識との関連で言うなら、アントロポゾフィーのファンタジーは、まずは、この地上の感覚世界を十全に感じとり、認識することを目指し ます。まずは、です。もちろん、フォルメンの練習や、オイリュトミーでは、感覚世界を越えた精神世界との結びつきが考えられています。しかし、その結びつ きが、幻想的なものとならないためにも、感覚世界をはっきり認識する必要があるわけです。
その感覚は、ふつう五感、すなわち、眼で見る視覚、耳で聞く聴覚、鼻でかぐ嗅覚、舌で味わう味覚、肌 で触れる触覚の五つに区分されていますね(板書)。しかし、シュタイナーは、彼の洞察力によって、感覚を十二に分けました。今ここに挙げました五感の他 に、温度感覚、自我感知感覚、思想感知感覚、言語感覚、平衡感覚、運動感覚、生命感覚の七つで、計十二です(板書)。なお、この訳語は新田義之さんに従い ました。これらは、『教育の基礎としての一般人間学』に出ています。これらの感覚のうち、一見して分からないもの、あるいは分かりにくいものもあります ね。触覚と温度感覚の区別は分かりますね。温度感覚は熱を感ずるのであって、触るのとは違います。自我感知感覚というのが、分かりにくいですね。これは、 自分の自我を感ずるのではありません。目の前に人間が立ったとき、その相手の自我を感ずる感覚です。こういう感覚が特別にあるわけです。相手に対して、意 識はされませんが、好感―反感―好感、という風に目まぐるしく反応しつつ、その自我を感知しているのです。これは『一般人間学』にある通りです。思想感知 感覚は、考えが、身振りでも捉えられることに表れています。言葉がなくとも、身振りでも考えが通じますね。それを捉えているのが、思想感知感覚です。言語 感覚というのが、言葉を捉える感覚です。運動感覚は、自分の体が静止しているのか、動いているのかを感知します。生命感覚は、自分の肉体の状態を感知する 感覚です。十二の感覚の、十二という数にも、実は意味があります。人は、これらの感覚を用いて、夢想的な逸脱をせずに、現実のあり方を十全に感じとってい くべきなのです。さて私たちは、現代にあって、様々な幻想的なファンタジーに取り巻かれています。特に子供を取 り巻く環境には、すさまじいものがあります。子供が、ファミコン、テレビゲームの類の展開する、擬似的な現実にすっかり捉われてしまうような事態は、ぜひ 避けたいところです。特に、周囲の現実を模倣によって写しとっている第一・七年期の子供の場合には、ぜひとも避けるべきです。以前、新聞で読んだのです が、赤坊の時から子守り代わりにテレビを見せ続けていたために、テレビの世界と、現実の世界の区別がつかなくなるという障害が、外国で報告されていたこと がありました。
もっとも、大人の場合は、またちょっと異なります。大人は、別に考えなくてはなりません。自我 がすっかり一人歩きし始めた大人の場合は、自分で選択すべきです。そしてまた、ある種の大人たちは、現実と非現実の混淆を目指すことまでします。現実逃避 に暗い喜びを感じ、幻想的なものを愛好する、その種の人達にとっては、現実と非現実の混淆は、一種の理想郷でしょう。私もかつては、破滅型の人間だったこ とがあるので、その辺の機微は分かっているつもりです。彼らの価値観からすれば、それも世界の拡大なのかもしれません。しかし、それは、アントロポゾ フィーの第一の柱である、<善なるものへ向かう意志>と抵触します。この第一の柱は、シュタイナーにとっては、宇宙の進化と結びついた、大きな展望、大き なパースペクティブのもとに捉らえられています。それは初めにお話した、英知でもあります。その展望は、『神秘学概論』の「宇宙と人間の進化」で述べられ ています。これについても、また日を改めて述べるつもりです。その展望の下で、非現実的な力、幻想的な力は、<太陽的なもの>に対抗する、一種の影の力と して捉えられています。ここで、やはり単純な善と悪の二元論を思い浮かべるべきではないでしょう。シュタイナーにあっては、<影の力>も、宇宙進化に必要 な力なのです。それは元々、<太陽的なもの>の根源から生まれ出たものでして、絶対的な対立を作っているのではないのです。影の力は、乗り越こえられるた めに存在しているのです。そうした力を、シュタイナーはルツィファー(Luzifer)と、アーリマン(Ahriman)という名で呼んでいます。これら の名は、教育関係の訳書にも出て来るので、ちょっと触れるべきでしょう。しかしごく簡単に説明します。ルツィファーとは、人を陶酔させる力、何事かに夢中 にさせる力、夢想的にさせる力のことです。アーリマンとは、人の心を冷たくさせる力、唯物主義やテクノロジーをめぐって働く、非生命的な力のことです。こ の問題は、秘教的な内容にまで入り込むことになってしまいますので、ちょっとこのくらいにしておきます。
さて、ファンタジーの問題に戻ります。先程、現代ではファンタジーの名の下に、現実を逸脱する 幻想的なファンタジーも混じり込んでいると申し上げました。そして、現実をしっかり捉えるファンタジーの存在を、アントロポゾフィーのファンタジーとの関 わりで、紹介しました。この二つのファンタジーは、一人の芸術家の中で、はっきり分けられないこともあります。しかし、ファンタジーの動き方を注意深くみ ていると、二つの方向が、見えてきます。それを、私流に図示すると、こんな風になるでしょう。これはシュタイナーのではなくて、私の考えです。物質的現実 を白で書きます。ファンタジーの力を黄色で表します(このページでは人と地面が現実、その他がファンタジーの力)。すると、二つのファンタジーは、このように画き分けられます。
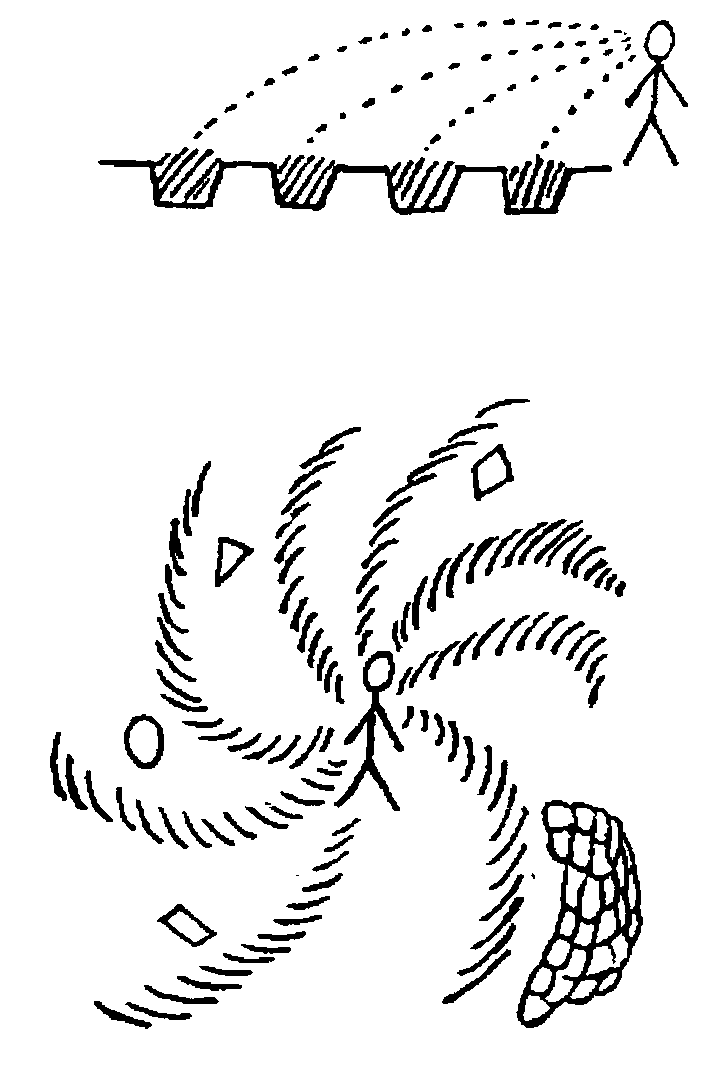
上の図の凹凸は現実を表します。存在するのだけれど、目には見えていない現実が凹の空洞の部分 です。右端に立っている人は、ファンタジーを働かして、その見えない部分を補っています。
下の図では、中心になっている人から、ファンタジーが渦状に湧き起こっています。現実の記憶などの断 片が、その渦の所々に散在しています。土台となる現実を失って、このような端切れとなったものを、勝手気ままなファンタジーの渦からひょいと口に出せば、 それは突飛な思い付きとなります。ファンシイ、ドイツ語ならファンタステライです。右下の所で固まっているものがありますね。記憶の断片、現実の断片が、 再構成されて、第二の現実となったものです。ファンタジーの渦の中で、遊びのルールに基づいて、再構成されたものです。トールキンなどは、こうした第二の 現実を、高く評価しますね。彼は、こういった意味でのファンタジーを、強く推奨しています。現実を写実しようとするリアリズムが、この上の方で、人間の内から湧き出てくるものを重視する ロマンティシズムが、下の方のファンタジーだ、という風にも言えるかもしれませんね。リアリズムの後に来るシュールリアリズムは、デフォルメやシンボルを 通じて、再び、こちらの下の、混沌の中へ入り込んだと考えられます。また、ちょっと異なる対比ですが、推理小説は上の方ですね。事実の間を想像力で埋めて いくのが、推理小説の読み方ですから。SF小説は、ホジソンあたりのは、下の方ですね。しかし、上の図が、こうなる場合もあります。
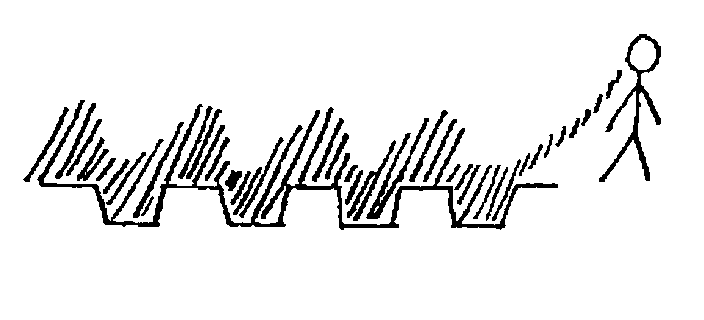
つまり、現実をファンタジーが豊かにしているケースです。現実を豊かに捉えるポエジーが呼び起 こされれば、そのファンタジーは、現実に生命を吹き込んでいることにならないでしょうか。それは、現実を本来の姿で捉えているのかもしれません。たとえ ば、たわわに実った稲の穂に風が吹き付けて、稲田が波状にうねっているとします。その金色のうねりをながら、夕焼けに輝きつつ、うねっている金色の海を想 像するとします。
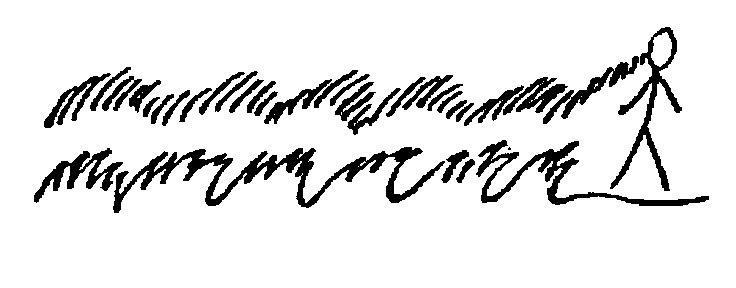
稲田
そして、その壮大なイメージの中で、この世を存在せしめているものに対する驚異の念が湧き起こる と同時に、豊かな実りの実感が迫ってくるような時、このファンタジーが働いているといえましょう。私は、こういうファンタジーを<想像力>と呼ぶことにし ています。一方、現実を逸脱する渦の方は、<空想力>という風に区別しています。そして私は、アントロポゾフィーのファンタジーは、<想像力>であると考えます。その<想像 力>は、今述べたような、感覚世界を十全に感じとることだけに用いられるのではありません。それは、感覚の背後にある、超感覚的な世界とも、健全な関わり をもつことになります。健全に関わるというのは、精神世界に存在する法則に沿って、体や思いを働かせるということです。その働きも<想像力>です。なぜな ら、目には見えなくとも実在すると考えられている現実を、その働きは目指しているのですから。
最終回にお話する行の場合とは違って、はっきり意識に昇らないのですが、ファンタジーを働かす 時、芸術活動をする時、フォルメンやオイリュトミーをする時、精神世界との健やかな、太陽的なつながりが出来ているという風にアントロポゾフィーでは考え ているのです。
具体的に言うなら、オイリュトミストの上松恵津子さんは、オイリュトミーで皆がフォルメンを描 いたあと、こう言ってました。今の皆さんの動きは宇宙のエーテルに永遠に刻み込まれましたと。エーテル界というものが物質界と重なって考えられているので すが、これについては、五月二一日に、人間の構成要素、エーテル体やアストラル体についてお話する時に、説明しようと思います。
しかし、ここまでは一方的に超感覚的な認識とか、認識事実とか申し上げてきましたが、これらは 感覚には捉えられないものです。目に見えないものを扱っているというなら、それは<空想>と、どう区別できるのかとお考えになる方もおられるでしょう。そ れも、ひょっとしたら、下の図の渦の中にある事柄なのではないかと。これは、今後のお話とも関連する重大な問題です。その問題は、今後繰り返し吟味しなく てはならないと思います。とりあえず今、申し上げられることは、空想の渦の中で作られるものの中には、太陽の輝きではなく、おぼろ月の光が込められてい る、ということです。それは特に精神世界に対しては、怪奇的なイメージ、あるいは逆にことさら美的なイメージをこしらえ上げるでしょう。アントロポゾ フィーが精神世界についてもっている認識を今後展開して行く中で、皆さん御自身が、その辺を吟味していっていただきたいと思います。それはやはり、こうで ある、と押し付けられるのではなく、御自身で判断していただきたいことなのです。
これで今日の主要な話は、おしまいです。これは余談としてお話しますが、ミヒャエル・エンデの ファンタジーは、<想像力>、<空想力>のどちらだと思いますか。彼のファンタジーは、はっきりどちらともいえない包括的なものですね。しかし作品を見る と『はてしない物語』は、第二の現実、ファンタージェン国が主な舞台になっているという意味で<空想>的ですね。しかし『モモ』はどうでしょうか。『モ モ』は上の図の方、<想像>的な要素が強いのではないでしょうか(聴衆の中に、うなずく顔あり)。我々が あまりに忙しく、いらいらして人間性を失っているという現実を、ハッと気付かせてくれるという意味で、<想像>的だと思います。彼は<空想力>、<想像 力>、ともに兼ね備えた作家だと思います。しかし、彼のインタビュー記事を読んだり、実際に会って話を聞いてみると、どうも<空想力>の方が、<想像力> よりも優勢のような気がしますね。この辺から、エンデが正統なアントロポゾフィーから外れていると言う向きも出てくるのですが、そういうことは、あまり杓 子定規に考えなくでもいいことでしょう。
なお、次回はいよいよ、「子供の発達 ― 人の一生」のテーマでお話いたします。その後に続く 話のテーマをざっと申し上げますと、五月二一日は「人間の構成要素」です。子供の発達の話で出てくるエーテル体とかアストラル体の説明を致します。五月二 八日は「覚醒と睡眠、そして夢」、六月四日は「生と死」です。このあたりからは『テオゾフィー』の内容が加わってきます。十一日は「再生」、十八日は「第 五文化期の課題(歴史的展望)」、二五日の最終日は「認識の小道」の予定です。
*空想と想像の違いに基づいて論じたものに当HPの「妖 精論」があります。