音の体験
第3講演
ドルナハ、1923年3月16日
先日私は、人間が入眠と目覚めの間に行なう営みは、目覚めと入眠の間に行なう営みとまったく同 様、明確に描写できるものであるということに繰り返し注意を促しました。人間は目覚めと入眠の間に体験することのすべては、物質体とエーテル体を通して体 験しています。人間は物質体とエーテル体に、それなりに形成した感覚器官を備えているがゆえに、彼の周囲にあって物質体・エーテル体と結びつきのある世 界、いわば自分と同質の世界を意識できます。人間は進化の現段階では、自我やアストラル体の内に霊的・魂的器官を、感覚器官のようには形成していません。 霊的・魂的器官は、いわば
もし矛盾した表現を用いることを許していただけるなら超 感覚的な感覚器官といえるでしょう。この器官をいまだ形成していないために、人間は入眠と目覚めの間に体験することを意識にのぼらせることができないので す。こうして、霊視能力のみが、いわばこの自我とアストラル体の経歴が秘めているものを、その物質体やエーテル体を介して成立する表向きの経歴とは別に大 観できるのです。さて、目覚めと入眠の間に人間が行なう体験についてお話する場合、その体験というのは必然的 に、物質的・エーテル的環境の中にある人間が身のまわりに見、体験する現象とか、その中で引き起こした現象ということになります。ですからその場合、話は 人間が目覚めと入眠の間に存在する物質的・エーテル的環境、すなわち物質・エーテル界についてのものに限られます。しかし人間は入眠と目覚めの間にも、同 様、ひとつの世界に存在します。ただし、その世界は、物質・エーテル界とは全く異なった様態で存在する世界です。そして、超感覚的な霊視を用いるならば、 この世界について語ることも可能なのです。我々が目覚めている時の環境は物質界ですが、それと全く同様に、我々が眠っている時の環境としてその別世界が存 在するのです。我々はこの講演の中で、その世界が明かしてくれることを、いくつか心に描いてみようと思います。その要点は私の『神秘学概論』に書かれてい る内容をご覧になれば、そこに出ています。そこでは、簡単にしか触れていませんが、物質・エーテル界を構成する鉱物界、植物界、動物界の諸領界の上に、さ らに高次のヒエラルキーの諸領界が続いている様子をご覧になれると思います。我々はその様子を今日の講演でちょっと思い浮べてみることにします。
我々が目覚めた状態で眼とか、その他の感覚器官を、我々の物質的・エーテル的環境の内に向けて みるなら、自然の3つの領界ないしは4つの領界、すなわち鉱物界、植物界、動物界、人間界を知覚する、というふうに、まず言ってみましょう。ここでさら に、超感覚的にしか接することができない高次の領界に上がってみるなら、我々は、いわばその続きとして天使、大天使、権天使、能天使、力天使、主天使など の諸領界を見出します(図を参照せよ)。
つまり互いに浸透しあっている2つの世界、物質的・エーテル的世界と超感覚的世界があるわけで す。そして我々は、既に述べたように、入眠と覚醒の間、実際、この超感覚的世界の内にあって、その世界を体験しているのです。もっとも、この体験は霊的・ 魂的器官が欠けているため、目覚めた後の通常の意識の内に上って来ることはありません。
ここで大切なのは、この超感覚的世界の内で人間が行なう体験をもっとよく理解するためには、い わば或る種の描写の仕方で、つまり、ちょうど物質・エーテル界を自然科学や歴史学が描写する時と同じような方法で、この高次世界を描く必要があるというこ とです。我々が睡眠時に存在している世界の実際の出来事を扱う、そのような、いわば超感覚的科学を実践するためには、もちろん、さしあたり、個々の事例か ら始めるべきでしょう。そこで私は、今日はさしあたり、或る出来事を選びました。その出来事はここ千年間の人類の歩みの全体にとって、重大な意味をもつも のです。
一つの側から、つまり物質・エーテル界とその歴史の側から、既にこの出来事はしばしば論じられ ています。今日我々は、これをいわば別の側から、つまり観点を物質・エーテル界にではなく、超感覚界においた場合に現われる地平から論じてみましょう。今 とり上げようとしている出来事は、今まで私が何度も超感覚的観点から描写したことのあるものでして、紀元4世紀に起こった出来事です。
実際私は、西洋における人間の魂の状態の全体が、その紀元4世紀にどのように別の状態に変わっ たかを話したことがありますし、紀元4世紀以前の時代に生きた人間がどのような感情をもち、どのような感覚をしていたかは、ことを精神科(霊)学的に扱わ ない限り、もはや決して分からないものになっている、事実、そうなってしまっているということを話したことがあります。私たちは、精神(霊)科学に則っ て、その時代の人間の感覚の仕方や、心の状態を何度も描写しました。別の言い方をすれば、我々が描写したのは、この紀元4世紀ごろの時代の経過の内に人間 が何を経験したかということです。今日はこれから、超感覚的領界に属している諸存在がその時代に経験したことに、すこし注意を向けてみることにしましょ う。いわば生の別の側面を見てみようというのであり、観点を超感覚界にとってみようというわけです。
人間の思念が頭部の内にしか存在しないという考えは、現代のいわゆる啓蒙された人間たちがもつ 偏見です。もし思念が人間の頭部の内にしかなかったら、我々はその思念を用いては、物事を何ひとつ知ることができないでしょう。思念はもっぱら人間の頭部 の内にしか存在しないと信ずる者は、逆説的に聞こえるでしょうが、喉の渇きを癒した一杯の水は舌の上で忽然と現われたのであって、水差しから口の中に流れ 込んだものではないと信ずる人の場合と同様な誤った思い込みに陥っているのです。思念は人間頭部に生ずるという主張が馬鹿らしいのは、ちょうど私が、この 水差しの中にある水を一杯飲んで渇きを癒しておきながら、その水が私の口中に湧き出たと言うことが馬鹿らしいのと同じことです。思念は世界中に広がってい るのです。思念は事物の中に働いている諸力そのものです。そして我々の思考器官は、思念諸力を貯えた宇宙の貯蔵庫から汲み出し、その思念を受け入れる器官 でしかないのです。ですから我々は、思念について、それが、もっぱら人間だけが所有するものであるかのようにいう必要はないのです。我々は、思念について は、それが宇宙に遍在し、世界を統べている諸力であるという意識をもって語るべきなのです。しかし、そのため、こうした思念は自由気ままに飛び回るのでは なく、それはいつも何らかの高次存在に担われ、手を加えられるものであるのです。そして、最も重要なことは、思念はいつも同じものたちに担われているので はない、同じ存在に担われているのではないということです。
超感覚的世界に向きあい、超感覚的探求を通して明らかになることは、人間が世界を理解するのに 用いている思考は、外部の宇宙の内にそれを担うものが存在する
いうならば思考を放射しているものが存在している ということ地上的な表現には、この気高い営みや諸存在を表す適切な言葉はありませんで すから、思考は担われ、放射されていたということが明らかになりますが、それは、紀元4世紀までは我々が能天使とか形態存在と名づけているヒエラルキーに ある諸存在(図を参照せよ)に任せられていました。古代ギリシャ人は、自分の思念の源が本来どこにあるかについて、参入している密儀の知に基づい て自らに説明しようとした場合、そのやり方は、必然的に次のようにならざるをえませんでした。すなわち、彼は、「密儀学によって形態の霊的存在、形態の諸 力、つまり形態の諸存在として私に明かされる、あの高次の存在に、私は自分の霊的な眼を向けているのだ」と自らに語ったのです。この存在は宇宙の叡知の担 い手です。宇宙の思念の担い手です。この存在は、世界の出来事のすべてに思念を流し込みます。そして、この人間的な思念を魂に与え、魂はこの思念を受けと めることによって存在するのです。
ギリシャ人たちが生きたあの古代の時代に、特別な秘儀参入によって超感覚的世界 の内に入り込み、この形態の諸存在を体験できる高みまで昇った者は、この諸存在を見たのです。そして、そのような参入者は、この諸存在の適切なイメージを 得るために、つまりこの諸存在を正しくイメージするために、世界を貫き流れる輝く思念といったイメージを、その諸存在のひとつの属性として、描いたので す。この古代ギリシャの参入者の目に映った形態の諸存在の姿は、自らの霊的肢体から思念を放射させつつ輝く諸力のようなものであり、その思念の諸力は、次 いで、世界事象のプロセスの内に入り込み、そのプロセス内で、世界を創造する叡知の諸力として、さらに作用し続けるというふうに見えたのです。秘儀参入者 は、たとえば次のように言いました: 形態の諸力、つまり能天使が世界の中で、宇宙の中でもつ使命は、世界事象の内に思念を流し貫くことであると。そして感覚的科学が人間の行為を描写する場合、人間が個々に、あるいは共に行なう行為のあれこれを報告するのと同様、超感覚的科学 も、形態の諸力の、特定の時代の活動を見据えようとする場合、この超感覚的諸存在が相互に思念の諸力を注ぎ合い、受け取り合う様子を描写したり、さらにま た、この思念の注ぎ合い、受け取り合いのやりとりの内に世界事象が組み込まれ、それがその後顕在化し、自然現象として人間の前に現れる様子を描写するはず なのです。さて人類の歩みのうちに、他ならぬあの紀元四世紀がやってきます。そしてこの世紀は今述べた超感覚的世界に非常に重要な出来事をもたらします。 それは能天使あの諸力、つまり形態の諸存在がその思念の諸力を権天使たち に、すなわち原初力ないし始源たちに譲り渡したのです(図表参照)。
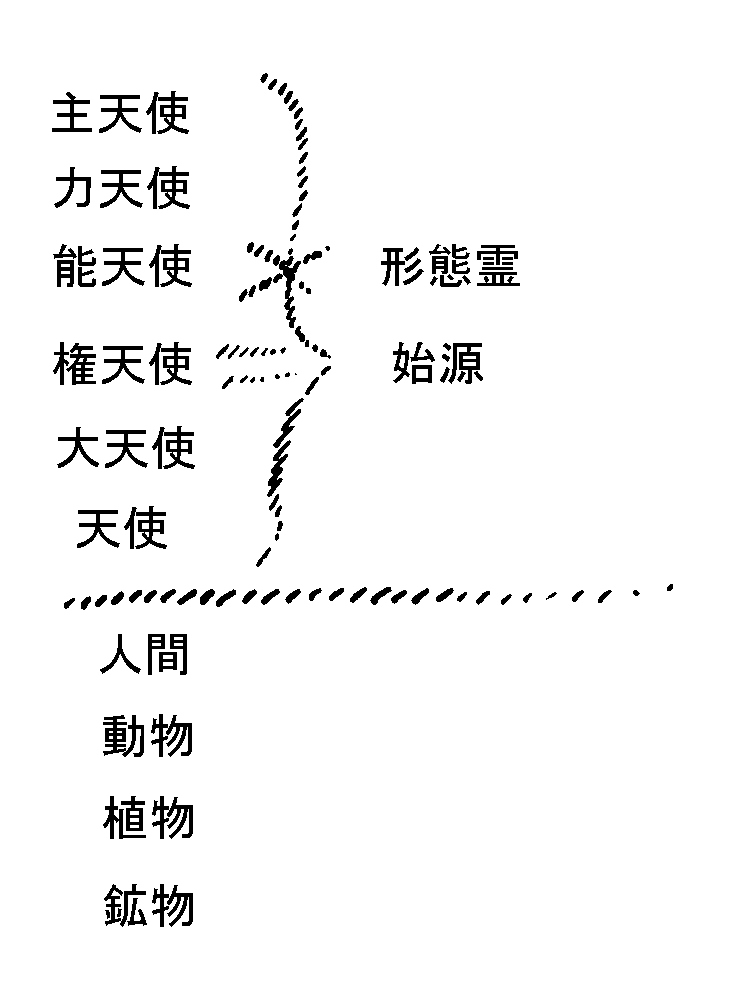
当時、始源つまり権天使たちが、それまで能天使たちが担っていた使命を引き継いだのです。その ような出来事が超感覚的世界では起こりえるのです。この役割の交替は実に特筆すべき重要な宇宙的出来事でした。能天使、形態の諸存在はその時以来、もっぱ らその使命を、外界の感覚知覚の統御、すなわち特別な宇宙の諸力でもって、色彩、音色等の感覚世界に顕れるすべてを司ることに限定したのです。こうしてこ の出来事を霊視する者は、紀元4世紀の後にやって来た時代について、次のように言わざるをえないのです: 私には、世界を統治する思念が権天使、つまり始 源たちに委譲される様子が見える。そしてまた、眼が見、耳が聞く世界は、この世に多種多様な形姿を生み出し、絶え間なく変容するが、この世界のすべてが能 天使の織り出す織物であるのが見える。人間に思念を与えていたのは、以前はこの能天使であったが、今では感覚内容を与えており、一方、人間に思念を与える のは、今では始源になっていると。
そしてこの超感覚的世界の事実が、地上の感覚世界に反映し、例えばギリシャ人が生きていた古代 には、思念は、事物の内に客観的な存在として知覚されていたのです。こんにち我々が事物に赤や青を知覚していると思うように、ギリシャ人は或る思念を頭で 理解するだけでなく、ちょうど赤や青の色彩が眼を射るように、その思念が事物から輝き出で、放射するのを見たのです。
このことは私の本『哲学の謎』の中でとりあげていますが、そこで述べてあることは、事柄のもう 一方の面、いわば人間的な面であるのです。みなさんは、この超感覚的世界の重要な出来事が物理的・感覚的世界に反映する様子を私の本『哲学の謎』の中の叙 述に見て取ることができます。本書中では、この反映の仕方を表すのに哲学的表現が用いられました。なぜなら哲学者の言葉はあくまで物質界向けの言葉だから です。もし物質界向けの言葉を用いず、超感覚的な見方を叙述すると、まさに能天使の使命が権天使に委譲されたという超感覚的な事実についても語らなければ ならないのです。
こうした出来事の反映は人類の内で、その歴史の全時期を通じて次第に兆してくるものです。それ は人類の魂の根本的大変革と結びついています。この超感覚的事実は紀元四世紀に生じたとはいうものの、その年代は、おおよその話でしかありません。なぜな ら、それはいわば、中心になる時点にすぎないからです。使命の委譲は実にいくつもの時代にわたって続きました。それは紀元前の時代から既に準備され、紀元 後12、13、14世紀になって初めて完結したのです。4世紀というのは、いわば人類の歴史上の変化を特定しようとして、挙げた中心の時点であるわけで す。
さて、このようにして挙げた時点は同時に、人類進化の中で、人間の超感覚的世界を見る視野が すっかり暗くなり始める時点でもあります。人間の魂の意識は地上世界にだけ向かい、超感覚的に見たり知覚することを止めるようになります。このことは、別 の側面から光をあてると、皆さんにはもっとはっきりしたものになるかもしれません。
私がこのようにはっきり指摘しておこうと思うことは、煎じつめると、いったいどんなことになる でしょうか。それは、人間が自らの個別性をますます強く感じるようになることだといえます。思念の世界が形態の諸存在から始源へ、つまり能天使から権天使 へと委譲されることによって、人間は自己存在の思いを今まで以上に強く感ずるようになるのです。なぜなら権天使の存在は、能天使より一段階人間に近いから です。そして超感覚的に霊視し始めると、人間は次のような印象をもちます。その場合、彼はこのように言います: やあ、あそこに私が感覚世界として眺めて いた世界があると。黄色(図を参照)は私の感覚の方に向いた側、赤は感覚に背を向けた、既に隠れてしまった側です。
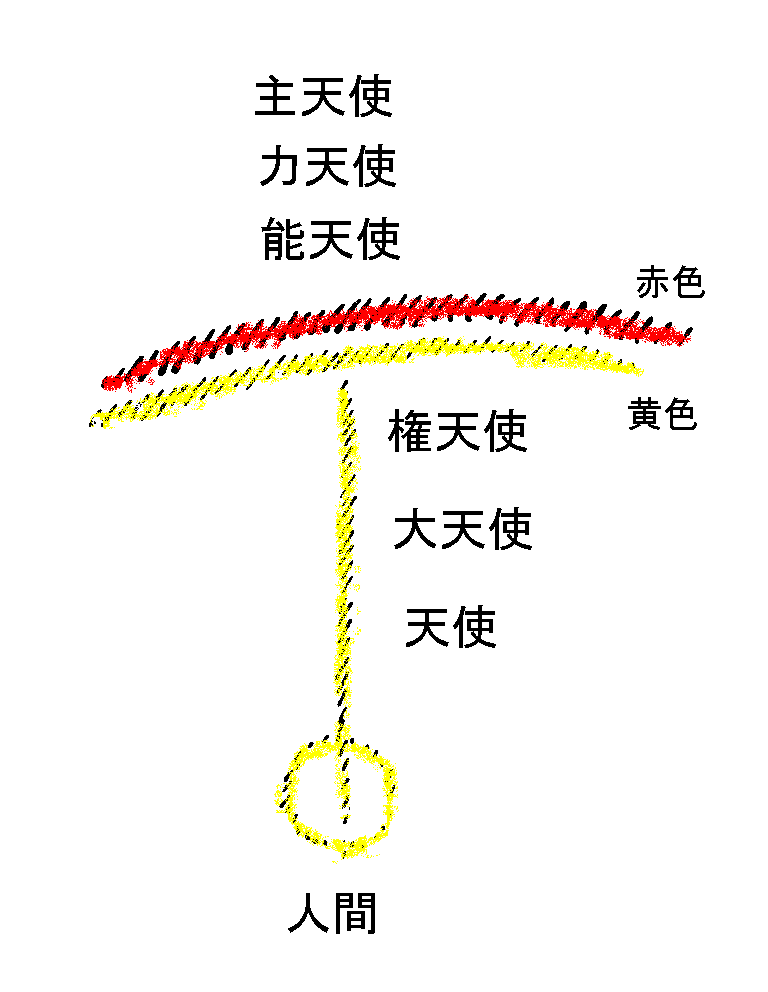
通常の意識では今考察している諸関連を知ることは全くできません。しかし、超感覚的意識では、 まさに次のように感じとれるのです。「ここに人間がいるとすると(図で示す)、人間と感覚的印象の間に、天使、大天使、権天使がいる。これらの存在は本 来、感覚世界の側にいるのだ」と。彼らは通常の肉眼には見えないだけで、本来人間と感覚界のとばりの間に存在しているのです。そして、能天使、力天使、主 天使は元々、その向こう側にいます。彼らの姿は感覚界のとばりによって覆われているのです。こうして超感覚的意識をもった人間は、思念が権天使に委譲され たあと、それが身近かになったように感じました。人間は思念が今やそれまで以上に人間界に近づいたように感じたのです。思念は今までは、事物の表面に浮か ぶ赤や青といった色彩の背後に内在していて、いわば赤や青を介して、あるいは Cis や G を介して人間のもとに届いたのでしたが。人間はその委譲が行なわれてからは、思念世界とそれまで以上に自由に交じわえるように感じているのです。このこと はまた一方で、人間にまるで自ら思念を作り出しているかのような幻想を呼び起こしてもいます。
かつては客観的な外界から顕現してきたものを、いわば自らの内に取り入れるようになるほど進化 するには、人間はまだ時の経過を必要としています。そのような段階は、人間進化の歩みの中で徐々にやってきます。我々がここで、人間進化の歩みを思いっき り遡ってみるなら、つまりアトランティスの破局を越えて、それ以前の古代アトランティス時代にまで遡ってみるなら、その場合、古代アトランティス時代の人 間像として思い浮べていただきたい姿は、私が『神秘学概論』や『アーカーシャ年代記より』の諸論考の中で述べたようなものです。この頃の人間は実際、今と は全く異なる作りをしていました。彼らの体を構成する素材は、のちのアトランティス期以後のものより、ずっと精妙でした。そのためまた、魂の、世界に対す る関わり方も全く異なるものでした
このこともすべて、先の著作に述べてあります。このような体と魂をもったアト ランティス人たちは世界を全く異なる仕方で体験したのです。私はこの特別な体験の中からほんの一例を挙げようと思います。アトランティス人は、たとえば3 度を体験できませんでした。5度すら体験できませんでした。彼らの音楽体験は、そもそも7度を感ずることから始まったのです。彼らは他に、さらにそれより 広い諸音程も感じていました。その中で一番狭いものが7度であるわけです。3度や5度は彼らには聞こえなかったのです。それらの音程は彼らにとって存在し なかったのです。しかし、そのため音の体験は今とは全く異なるものでした。魂の、音に対する関係が全く異なって いたのです。中間の音程とは関わりなく7度の内にだけ音楽が体験されるなら、そしてアトランティス人のもとでそうであったように、7度の内に自然に音楽が 体験されるなら、その場合、音楽は身近に生じる現象とか、身内で生じる現象としては知覚されません。人は音楽を知覚したとたん、自分の身体の外に出ている のです。外部の世界の中に息づくのです。アトランティス人のもとではそんなふうだったのです。アトランティス人のもとでは、音楽体験はそのまま宗教体験で もありました。7度体験が彼らに顕れた様子は、彼ら自身が七度音程の発生に関わっていると言えるようなふうにではなく、世界に隈なく遍在している神々が7 度の内に顕現するというように感じられたのです。彼らは「私は神々によって作り出された音楽の内にいる」と感じている時に、「私が音楽を作っている」とい うような観念に意味を見いだすことはできなかったことでしょう。 さて、この種の音楽体験は、その後、本質的には弱まっていったものの、5度音程が十分味 わわれている時代には、まだなお存続していました。皆さんはこの5度体験を、人間を介して行なわれる今日の5度の感受と同じようなものと見なしてはいけま せん。こんにち人間が感ずる5度は、自分の外にある虚ろさのような印象を与えるものです。5度は人間にとって言葉の最上の意味での空虚さ
といってもやはり空虚さには違いないのですがをもっているのです。5度が空虚さを帯びたの は、神々が人間のもとから去ってしまったからです。アトランティス期後の時代においても人間はまだ5度音程を聞くと、その5度の内に本来神々が 宿っているのを体験していました。そして後世になって、音楽の内に3度、つまり長3度、短3度が登場した時になって初めて、音楽はいわば、人間の心情の内 に入りこみ、それ以来、音楽的体験をしても人間は、もはや陶然となって体外へ出てしまうようなことはなくなったのです。本当の5度時代には、人間は音楽的 営みをするさい、実際まだ体外へ出ていたのです。ご存じのように、比較的のちの世になってやっと始まった3度時代には、人間は音楽的体験をすると、自分自 身の内に沈潜するのです。人間は音楽を肉体としての自分のもとに引き寄せるのです。人間は音楽を自分の肉体性と結びつけたのです。そのため、長調と短調の 違いが現われ、まさに長調で体験できることを味わい、短調で体験できることを味わうことになったのです。3度の登場とともに、つまり長調、短調が音楽の内 に現われて以来、音楽の体験は物質体とエーテル体の担い手としての人間が体験する、人間の気高さ、喜び、陰欝さ、苦痛、悩みなどの気分と結びついたので す。人間はいわば自分の世界体験を宇宙から取出し、その世界体験と自ら結びつくのです。古代には
それは5度時代に もまだそうであり、7度時代には、こういう表現が許されるならば、もっと高いレベルでそうだったのですが人間が最 も重要な世界体験をする時、その体験は人間を直接体外へ誘い出すものであり、体験中の人間がこう言うことができるような体験でした。「音の世界が、私の自 我とアストラル体を、私の物質体とエーテル体から直接引き離す。私は地上における自分の存在を神的霊的世界と結び合わせる。響き渡る音は、その翼に乗って 神々が世界を隈無く渡る何かであり、私はその音を感じ取りながら、同時に神々が世界を渡るのを体験する」と。こうして皆さんが、この音楽という特別な領域でご覧になるのは、いわば宇宙体験が人間のもとに近 づいてくること、宇宙が人間の内に浸透してくることであり、また古代に遡った場合いわば人間の最も大切な体験を超感覚性の内に求めなければならないこと、 そしてまた、その後、最も重要な世界事象を描写する場合、感覚的・地上的現われとしての人間が、いわば書き加えられるような時代が始まることなどです。
感覚的・地上的要素の登場は、思念が形態の諸存在から始源へと受け渡されたあとに始まったあの 時代に、起こったことです。この変化はまた、古代の5度時代
それは確実に思念の委譲以前の時代でしたがが3度時代へ、長調・短調の体験へ移行するという形でも表されました。さて、この長調・短調の体験を踏まえて、アトランティス時代よりも更にひと昔の時代に遡ってみ ることは実に興味深いことです。つまり人間の地上進化の内で、振り返ってもぼんやりとしか見えない、あのおぼろな遥かな過去に属する時代に遡るのですが、 その時代の様子は超感覚的な霊視を用いると蘇らせることができるのです。我々は霊視を用いると、私の『神秘学概論』の中でレムリア時代と名付けられている 時代にも遡れますが、この時代の人間の音楽の知覚の仕方は、そもそも一オクターヴの内に一音程すら感じられないようなものでして、この時代の人間は、音程 が一オクターヴを越えた時に初めて一音程と感じとれたのです。すなわち、たとえば、

というふうにオクターヴを越えて初めて、人間はこの cーd、すなわち c から次のオクターヴの d までの音程を知覚できたのです。
記録16
ですからレムリア時代の音楽体験は、オクターヴ内の音程を聞き取ることで成り立つようなものとは全然 違うのです。その時代に体験される音程は、オクターヴを越え、次のオクターヴ内の最初の音へまたがるのです。そして次の音程は、さらに一つ先のオクターヴ の2つめの音へまたがるといったふうになります。このような体験は、何とも名づけ難いものですが、次のように言うならば、そのうちの幾分かを思い浮べるこ とができるかもしれません。「人間は次のオクターヴの2度、さらにその次のオクターヴの3度を体験している」と。人間は一種の客観的な3度を体験している のです。その際それなりに2つの3度、すなわち長3度と短3度も体験するのです。ただし当時の人間が体験する3度は、もちろん現代にいう3度とは別もので す。なぜなら、もっぱら3度というのは、同一のオクターヴ内にとった或る音と、2つ先の音との間にできる音程であるからです。しかしその古代の人間は、今 の我々から見ると或るオクターヴの1度、次のオクターヴの2度、3つめのオクターヴの3度というように取られた音程を、直接体験しながら、同時に一種の客 観的な長調、客観的な短調といったものを知覚していたのです。それはもはや自己内部で体験された長調・短調といえるものではなく、神々の顕れを心や魂で体 験したことの表現として感じられる長調・短調であるのです。レムリア時代の人間の音楽体験は、喜びとか苦しみ、高揚感とか陰欝さというような表現で表しえ るものではなく、次のように言うしかない体験でした。「レムリア時代の人間は、音程をこのように知覚しながら、同時に体外に出てしまっているが、音楽をこ のように感じることによって彼が体験しているものは、神々の歓びの調べであり、神々の宇宙に響く嘆きである」と。こうして、こんにちの人間が長調・短調に 接して感じるような体験が、いわば外部の宇宙に投影されていた時代これは実際に人間によって体験された地上時代の 出来事ですがに我々の目を向けてみることができます。こんにち人間が内的に体験していることが、外部の宇宙に投影 されていたのです。こんにち人間の心情の内、感情の内を波打ち渡るものを、この時代の人間は物質体から引き離された状態で、外界で、神々を感受する体験と して味わったのです。こんにち我々が内的な長調体験と名づけるほかないものを、この頃の人間は、体外に引き離された外界で、宇宙の歓喜の歌として知覚した のです。人間はそれを、神々が自らの世界創造に対して表す喜びの表現と言えるような、宇宙に響き渡る神々の歓喜の音楽として知覚したのです。そして我々が こんにち内的な短調体験として感じているものを、このレムリア時代の人間はその昔、神々の大いなる嘆きとして知覚しました。すなわち聖書の中で、神的−霊 的諸力、善なる諸力からの転落、あるいは原罪として描かれている状態に人間が陥る可能性を前にした、神々の大いなる嘆きとして知覚したのです。このことは、自ずと芸術領域にまで行き渡る、あの素晴らしい古代密儀の叡知から、我々のもとに 響いてくる事柄です。その叡知が我々に寄越す響きの語ることは、その昔人間がルチファーとアーリマンの誘惑を受け、これこれのことを知ったというような、 幾分抽象的な描写で表されることばかりでなく、神々が世界創造の喜びから宇宙の中で歓呼しながら楽の音を奏でている様子や、神々が神的−霊的諸力から人間 が転落することを予言的に既に見て取っていて、その洞察を宇宙的な嘆きとして表出した様子を、太古の地球進化期の人間が聞いていたということも含んでいる のです。
このような音楽上の問題の芸術的な把握の仕方は、後に次第に知的な形式を帯びてきますが、元来 は古代密儀に由来するものなのです。そして我々はその密儀の叡知に耳を傾けることによって、それが認識と芸術と宗教の一つの源泉であるという確信を強くも つことができるのです。そして、そこから我々は必然的に次のような確信を持つにいたるのです。「我々は再び、あの時代の魂の状態に戻らなければならない。 その状態を取り戻すには、魂が隅々まで宗教性に満たされ、芸術性に浸されながら、同時に明確に認識する必要がある」と。我々がこの魂の状態を取り戻せば、 ゲーテがつとに次のような言葉で思い描いていた事柄を、再び深く生き生きと理解できることでしょう。「美は、もしその美が顕れなかったら、永遠に隠された ままであったろう秘密の自然法則を開示している。」。地球期内、地球進化期内の人類進化の秘密が我々に自ら明かしてくれることは、まさにこの種の内的な統 一なのです。人間はこの世界と関わりつつ、人間の可能性の全的発現を体験するために、認識的かつ宗教的、芸術的な営為の全てをあげて、この統一に向かわな ければならないのです。
そして既にもう、こうしたことが再び人間の意識に昇るべき時になっています。なぜなら、さもな いと人間の本性はその心や魂の在り方において、衰微していくしかないからです。人間は現在、そして近い将来も、次第に知的になっていく偏向した認識によっ て、心が枯渇していく他ないでしょう。偏向した芸術によって心が鈍磨し、偏向した宗教によって魂を抜き取られた状態にされるのです。そうならないために は、人間は認識・芸術・宗教の三つを内的調和と統一に導くことができる道を見つけだす必要があります。これまで以上に意識的に身体から抜け出、感覚的なも のと並べて、再び超感覚的なものも見、聞くような道を見出す必要があるのです。
精神(霊)科学を用いて、ほかならぬ古代ギリシャ文化生成期に生きた賢者たち、すなわちアイス キュロスや、ヘラクレイトスのような人の先祖であった者たちに目を向けてみましょう。すると、この賢者たちは、秘儀参入していた場合には、自らの認識、自 らの芸術的創造力の源泉から、みな同じ感情を汲み取っていたことが分かります。この芸術的創造力を、彼らはその頃、個人的に自らの内に宿る力と感じたので はなく、「歌っておくれ、女神ミューズよ、ペーレウスの子 アキレウスの怒りについて」と述べたホメロスと同 じく、彼らは、彼らの宗教的な感覚のせいで、その創造力をいまだ霊的世界との交感の中で用いる力のように感じたのです。その力を用いた彼らは、次のように 思うのです。「人間はそもそも、人間にとって最も重要な営み
それは私が、皆さんに示したような古代の音楽上の営み ですが、思念のひらめきも該当しますをしながら、身体から抜け出、神々と体験を共にすることによって初めて、自ら を人間として体験したのだ」と。当時の彼らのこうした体験を、人間は今では失ってしまいました。人類が太古の認識や、芸術上、宗教上の叡知を喪失したという気分が、ギリシャ人の魂の深層に重く わだかまっていました。
近代の人間には、これとは別の事態が起こらなければなりません。近代の人間に起こるべき事態と は、人間が魂の経験をするためにもっている本来の力を発揮して、かつて喪失したものを再び見つけ出すに至る過程です。いうならば、人間がもつべき意識は
実際、我々は意識の時代に生きていますがこんにち内面化しているものが、いかにしたら外界 の、神的・霊的世界へ至る道を再び見出すかということに向かうものなのです。そしてこの意識は、必ずや生まれえるはずなのです私 は、最初のゲーテアヌム自由大学講座で行なわれた或る質問に答える形で、この意識の到来について暗示しておきました。 例えば、その来るべき意識は、或る領域に生まれ出ることでしょう。つまりメロディーの内に体験される諸感覚の内的豊かさが、いつの日か個々の音に移行した 時、すなわち人間が個々の音の秘密を知った時、言葉を換えて言えば、人間が音程を体験するばかりでなく、実際に個々の音を、その味わいの内的豊かさ、内的 多様性と共に、メロディーのように体験することが出来るようになったあかつきに、その意識は生まれ出ることでしょう。このことについては、こんにち、未だ に全くと言っていいほど知られていません。しかし、皆さんは、ことがどのように進捗するか既に知っています。つまり7度から5度、5度か ら3度、3度から1度、次いで個々の音に至るまで、そしてさらにはその先まで続く過程を知っています。この過程を経た結果、もし地上の人類が進歩し続ける ことを目指し、没落を望まなければ、以前の神性の喪失状態が人類進化のために変化を起こさざるをえません。地上の人類のために変化を起こし、神性の再発見 に導くのです。
我々が過去を正しく理解するのは、我々が未来へ向けた我々の進化の正しいありようを捉えること が出来た時にのみ、また、太古のギリシャ時代に生きた賢者が「私は現前していた神々の姿を見失ってしまった」と感じていた気持ちを、うんと深く、震撼する までに深く感じ取ることができた時にのみ、そしてまた、その賢者の気持ちに対して、我々の側が魂を震撼させられ、強く切に希求しつつ、「我々は神々を再び 見出すために、我々の内に胚胎している神性を開花させ、実らせよう」という意志表明が出来た時にのみ可能なのです。
ページ冒頭に戻る
第二講演に戻る
目次ページ に戻る