きょうバウマン氏※が7度の到来として見事に描写して下さったその時点と共に、文明化された人類の音 楽体験の内で、とても大きな変革が起こったことは、おそらくほとんど疑いえないところでしょう。ただ、その時代の音楽体験は今日まだ十分知られていないと 思われます。すなわち、理論的にはすでに知られていますが、この変革の内実が完全に明確に、十分な密度をもって感じ取られるような体験はもはやなされてい ないのです。しかし、その時始まったことは、今日でもまだ本来終わっていないのです。そして、もしかしたら我々は、その変化のただ中 ― もしこんなふうな言い方が許されるなら ― 人間の音楽的欲求の変化のただ中に、いるのかもしれないのです。もちろんこのような事象は、はっきりした線引きを可能にするほど速やかに完結しません。し かし、それでも結局、完結はするのです。そしてこの事象はある意味で、人類の進化の歩みに取り込まれているのです。※ 原注 パウル・バウマン (Paul Baumann , 1887ー1964年): 作曲家。ルードル フ・シュタイナーが創立したヴァルドルフ学校の初代の歌唱教師。「ヴァルドルフ学校の歌」を作り、ゲーテアヌムにおける1920年9月26日から10月 16日までの最初の大学講座において9月26日から29日まで「音楽ならびに、オイリュトミーによる教育芸術」についての3回の講演をした。『芸術と科学 分野における謎』(シュトットガルト、1922年刊、331ページ以降)を見よ。
そして、ここで私はお聞きしたいのですが、先ほど討議した方々は各自、ご自分が音楽の領域で体 験したことを思い出された場合、音楽体験全体の変革といってもいいような事態が起こっていることを、それと指摘することがおできにならないでしょうか。 もっと具体的な形で質問いたしますと、私が申し上げたいことは、こんにち音楽体験をすると、人それぞれが ― 私は今、とりあえず音楽性そのものからは少し離れてお話しますが ― 個々の音を違ったふうに体験しているという感想をおもちになられるのではないか、と いうものです。とにかく、人それぞれが個々の音を違ったふうに体験しているということ自体は、全く疑いをいれないところです。しかし、その体験の違いのあ り方は、その違いが彼らの音楽理解の形成になんらかの形で関わってくるといった性質のものでもあるのです。すなわち、こんにち音楽体験をする人には、いわ ばひとつの音の内にこれまでよりも深く入り込んでいく傾向があることが、明らかに見て取れると思うのです。ひとつの音は、それを表面的に聞くこともできま すし、また、その音の内に深く入り込んで聞くこともできるわけですから。
さてここで私は、先に討論なさった方々にお尋ねしたいのですが、ひとつの音を分割して考えた り、または、ひとつの音がどの程度までそれ自体でひとつのメロディーとなっているか否かを問いながら、いわばその音に耳を澄ませ尋ねてみたりというような 傾向が、現代の音楽体験の趨勢であると私が申し上げた場合、その方々は、私の申し上げていることの何であるかを想像することがおできになるでしょうか。想 像がおつきになるでしょうか。それというのも、音組織の拡張の問題に関しては、或る基盤に立ち、それに基づいて語るのでなければ、そもそも語ることはでき ないからです。
さきほど音(楽音だけでない広義の音、雑音も入る:訳注)、について発言がありました。そのよ うな音に関する議論のすべても、たぶん私が今申し上げたような前提に立って初めて、答えを出せるのかもしれません。この壇上でかなり長いこと話していた方 は、その種の音について多くの言葉を費やしておられたわけですが、ひとつの音の内にメロディーは知覚され得るかという問い ― こんにち、このようなことがすでに十分自らの実感をもって体験され得るかどうか、私には分かりませんが ― に対し、その方が、たとえばこんにちの段階ですでに他ならぬ、躊躇なく肯定する気になれるような人であるとするなら、その場合には、私は彼のいうことに納 得します。その場合には、彼がいかに個々の音の内に入り込んでいるか、他の人にはただの雑音にしか聞こえない個々の音の内深くに分け入っているかが、すっ かり納得できます。また、彼が音の深みに沈潜することによって、耳にした雑音を構成している音の内に、何物かを見つけだし、音の深みに達し得ない者には分 かちあえない何物かがそこで音楽的に成立していることを、感じ取っているのだということも、了解できます。
今朝の講演でフーゼマン博士は、その他、現代人がお互い同志、徐々にその個性の分裂を増幅させ ているということを指摘してくれました。そしてまた現代、すでに数多くの人たちが、個々の音の響きに関し、特定の専門的な修業を積んでいる音楽家とは全く 異なる音体験をしているようです。そして、これらの現象は、すでに出されているもうひとつの問い、すなわち精神(霊)科学はこの問題全体にどのように対処 することができるのか、という問いと関連しています。
※ 原注 フリードリヒ・フーゼマン博士( Dr.Friedrich Husemann 1887ー 1959年): 医者。フライブルク近郊のヴィースネック、ブーヘンバッハのサナトリウムを創設し、指導した。1920年9月26日から10月16日まで 行なわれたゲーテアヌムにおける最初の人智学的大学講座で、9月27日から29日にかけて「人智学的観点から見た精神医学的問題」について3度の講演を行 なった。『芸術と科学における謎』(1922年刊、シュトットガルト)の231〜330ページに掲載。
さて私はここで、はっきりと次のように質問したいと思います。個々の音は、状況次第でそれぞれ ひとつのメロディーとして感じ取ることができるということ、それを感じ取るには、自らの深みに沈潜し、音の内から部分を、いわば部分的な音を取り出すのだ ということ、するとその部分的な音同士の割合、その調和が、そのまま既に一種のメロディーとして感じられるのだと言った場合、その言っていることの何であ るかをまともに想像することがおできになるでしょうか。
パウル・バウマン:私の講演からお分りいただけたと思いますが、私はその中でまさ に音(楽音だけでない広義の音:訳注)をハーモニー性、すなわち統合されたメロディー性と結びつけています。音を統合されたメロディー、我々が音楽的に感 ずることもあるハーモニィーというふうに理解することができるでしょうか。実際、音がすべて音楽的なものであることは疑えないところです。ただ、それを音 楽芸術とみなす必要は必ずしもないのです。我々はそれを区別することはできません。しかしその音色の中に非常にはっきりと感ぜられることですが、そこには また特別に音楽的なものと、物の振動性の何かが絡み合っています。それ自体は聞こえない純粋に音楽的な音は明らかに、その音の動きを伝えている振動とは区 別することができます。
シュタイナー:私が申し上げているのは、そのことではありません。今私は、音の体験の可 能性そのものを拡張することを専ら念頭に置いているのです。すなわち、いわば音を体験する際、音の深みへ入り込み、そしてまた、その音の中から何かを取り 出して、その結果、音そのものの内に、何かがすでに感じ取られるようになるということなのです。
パウル・バウマン:私は音楽芸術に不可欠なもの、すなわち響きの内に現われるものと、音 楽的な作用を感じ取らせるための媒体との区別のことを、言っています。
シュタイナー:私が今申し上げているのは、そのことではないのです。客観性を帯びた仕方 で行なわれる作用とは関係なく、ひとつの音の内部で体験されることなのです。人は音を勝手に分析したり、それを再び統合したりしがちです。私が申し上げて いるのは、純然たる体験のことなのです。昔から音は、音の霊が作り出しているとされていました。民衆の表現でいえば、1250年のパッサウの(中略)で行 なわれた史劇の上演の際、その劇が始まる前、冒頭からすぐ悪魔が誘惑者として登場しますが、この場面の効果を出すため、悪魔は火の角笛を吹くことになりま す。それは凄い音を出し、観衆は皆びっくりします。このことは、私が述べている音の霊を考えるための、確かな拠り所になります。
(いくつか意見が出される)
シュタイナー:今出た意見はすべて、私が考えていることと違います。私が考えてい るのは、ひとつの音から得られる体験、メロディーとして感じられる体験のことです。ひとつの音が打ち出されると、実際、その音からメロディーが響きだすの です。
シュタイン博士:音の知覚と音の感受が区別されるべきだと思われます。私は音の知 覚においては何か特に深く感ずるものがあります。しかるに、感受的なものは、私が痛みや驚きを感じたときに起こるのでありまして(後略)。
シュタイナー:私は、すでにもう存在しているものを、ここでわざわざ定義すべきで あるとは思いません。私が言いたいのは、我々が音の体験に関して過渡期にあるのだろうか、そしてこの先、音の体験は実際にこれまでと異なるものになるのだ ろうかということです。実際、こんにち、音楽的な音の体験として捉えられている音は、いまだ、他の音と関連付けられるような音、いくつか集まってひとつの メロディーになるような音などなど、でしかないと思います。しかし、私は、音には、我々がその深みに入り込む可能性、さらにはまた、おそらく、その背後に 何かを探しだす可能性を秘めていると思うのです。そして、このことに目を向けるときに初めて、実りある議論が可能となるのです。
(さらに意見が述べられる)
シュタイナー:ひとつの音が長く持続するのを聞きますと、たとえば『魔弾の射手』 の序曲などがその例ですが、人は或る感じを抱くことがありまして、私はその感じを絵で視覚化することができるのではないかと思います。その音は、いわば半 分の弧の形になるだろうと思うのです ― これは図で表す必要がありますね ― 。この弧に小さな神経のようなものを、弧から伸びていくように描き加えてみましょう。そうして人が、この半分の弧を伝って音を感受するとします。音はこの 端から入り込むような具合に伝わり、そのあと底から上向きの弧へ渡り、次いでこちらの端の神経や静脈から抜け出ていきます。こうして或る種の内的運動が、 ある時は半分の弧の一方の側にあり、またある時はもう一方の側にあることになります。かなり大きな密度の力が一方から流し込まれ、それがまた戻るわけです から、この運動を力動的と表現することもできるかもしれません。
(意見が述べられる)
シュタイナー:この長い持続は、もっぱら、人がよりよく銘記するためにだけ起こる のです。状況次第では、この長い持続が、音の変化に気づく可能性を与えてくれるかもしれません。今私が説明に用いたいと思うのは、こんな具合に描ける視覚 的曲線、こんなふうに曲がっていく曲線よりも、今はここに、黒板に描き加えた垂直なものの方です。
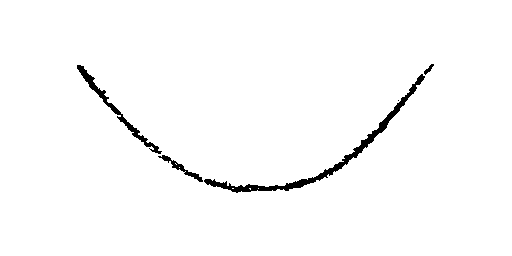
(さらに意見が述べられ)(前略)それはその大きな密度の力のせいなんですか。
シュタイナー:そうだからこそ、私はこう強調しておきたい:音の中へもっと深くお 入りなさいと。
(或る参加者のかなり長い論述)
ヴァン・デル・パルス氏がある種の音に関する自分の経験を語る。それはヤコボフスキーの詩の話に 移るための序章。詩自体が、詩の内容が告げる音。その音から離れられなくなった。その音はそこにあった。同じく、そこにあり続けることだってできただろ う。それ自体でひとつのメロディーだった。 ― 私がその場を離れたのは、半時間もそれを朗読し続けることはできないと言われたからだ。
この問題をここまで話しあったところで、ひとつ指摘しておきたいことがあります。それは進化し つつある事柄は、その初期の段階では往々にして非常に不完全な姿をとって現われるということです。たとえば現在、表現主義の芸術と称するものが、明らかに 実に多くの問題点を抱えたまま、多数登場していることが挙げられます ― しかしこれは表現主義芸術全体に対する批判なのではなく、表現の底に潜む多くのものに対する批判なのです。しかしその中には明らかに、将来非常に多くの意 味を帯びることになるものの端緒があります。
そして私が言いたいのは、音楽の進化にとっても、 ― 我々が絵画創作において色彩の中に沈潜し、色彩の内から創造しようと試みるのとちょうど同じように ― 音の内に沈潜することが今日、進化の始まりとして何らかの意味をもっているということなのです。そして、その端緒があちこちで現われてきた時に、その現わ れ方に人が共感できないという場合、そのことも私には十分理解できることなのです。共感できないことは問題ではないのです。しかし、ドビッシイのような音 楽家たちは、音楽進化の流れに沿った、何らかの来るべき事象の、非常に漠とした先駆けなのではないだろうかと考える以外に、どのような理解の仕方があるの でしょうか、あれば知りたいものです。ここで私たちが、そうした音楽家は先駆者なのだと認めることができれば、その場合には私たちの前に、特定の可能性、 つまり現在行なわれているのとは異なるやり方で作曲される可能性が現われてくるはずです。その作曲のやり方とは、作曲家と再生産する芸術家との間の関係が これまでよりも、はるかに自由なものになるようなやり方であり、また、演奏家の、すなわち再生産する芸術家の価値が限られてしまうようなことがずっと少な くなるようなやり方であり、演奏家がこれまでよりもずっと生産的になりえるようなやり方であり、演奏家がはるかに多くの裁量の余地をもつようなやり方であ ります。しかしこうしたことが音楽の内で可能になるためには、音体系が拡張されることが必要でして、拡張のために必須であるところの変奏が実際にできるこ と、本当に自由な変奏ができることが必要なのです。そして私が思いつく例を挙げるなら、たとえば作曲家が作り出す作品が将来はるかに暗示に富んだものにな るかもしれません。しかしはるかに暗示に富むからこそ、再生産する芸術家はその作品を表現するために、ずっと多くの変奏、ずっと多くの音を必要とするので す。そして或る音の奥深くに沈潜してみるならば、その音を、その後深みから引き上げ、隣り合ったいくつかの音と並べて聞くことによって、実にさまざまに分 割できるのです。このようにすれば、ダイナミックな音楽の営みが生まれることでしょう。私はこの問題は今簡略に述べるにとどめます。一晩中だって語り続け られるでしょうから。しかし、そんなことはよしましょう。私たちは明日また集まるのですから。ともかく現在のものより、はるかにダイナミックな音楽の営み が生まれることになるのです。そして、こんにち実際、このはるかにダイナミックな音楽体験の時はすでに、すぐ目前に迫っているのです。
さてこの問題は、再三提示されるもうひとつの問い、すなわち精神(霊)科学は音楽についてどの ような態度をとるべきかという問いと、ある種の関連をもっています。このもうひとつの問いは、私が共感できないものを常にはらんでいます。どうかご理解い ただきたいのですが、私は今申し上げていることで、特定の人を非難するつもりはありません。しかしこの問いには私には実際共感できないものが含まれている のです。すなわちその問いの提示の仕方がそもそも非芸術的なのです。質問している当事者はそのつもりではなくても、その質問の仕方は結局のところ、本来常 に理論的であり、非芸術的なのです。そしてそもそも芸術についての議論を行なうときには、いつでも実に容易に本来の芸術性から逸脱してしまい、不毛な理論 化の道に入り込んでしまうように、私には感じられるのです。精神(霊)科学は主知主義的なものではないし、人間の本質を成すただひとつの部分だけを捉えよ うとするものでもなく、一人の人間の全体を捉えようとするものですので、その人間の全体、思考、感情、意志に本質的な影響を及ぼすことになることは全く疑 いえないところです。現代の唯物的・主知的科学は結局、思考、すなわち人間の知的要素にだけ影響するものですが。精神(霊)科学は人間をその全体で捉える ことになります。そして、その結果、人間は自らの中の、内的なダイナミズムを増し、自らの部分的体験をこれまでよりもずっと変化に富んだものにし、それと 同時にその部分的体験を調和させようとする欲求もこれまでより強くなることでしょう。そしてそうなれば、それは本質的に、音楽の作用、音楽の体験全体が豊 かになることを意味するのです。そして精神(霊)科学によっていわば浸透し尽くされ、余すところなく貫かれ、活力を与えられているような人たちのもとで は、精神(霊)科学によって音楽分野で可能になる事柄が、実際に生じるのです。このことについては理論化することができません。理論化すべきではありませ ん。そうではなくて、むしろ今は感じ取るべきなのです。精神(霊)科学がいかに実際に人間を内的にダイナミックにさせるものか、また、人間がそのことを通 していかにこれまでよりも密度が高く、ニュアンスに富んだ音楽体験をするようになれるものかということを感じとるのです。
以上の事柄は、重大な諸問題と関連づけることができます。ご存じのように、精神(霊)科学運動 に対してはさまざまな非難がなされています。いわく、いつも関心をもつのは主に婦人ばかりだ。男の姿は人智学の集まりには見かけられないと。 ― 私はこの話が統計的にどこまで合っているか、いないかの判断を今するつもりはありません。そのような新聞記事を、現場を見る前にもう書き上げているような 人たちが、かなりいるのです。彼らはその後、自分が書いた記事と反対の事実を見ても、いったん公にしてしまった意見をもはや変えることはできないのです。 しかし総じて私たちは、次のように言うことができます ― 今から申し上げることは本当にそんなに悪い意味は込めてないことをお断わりしておきますが ― 男性の世界は教養をつけること、つまりここ数世紀ま すます学問化しつつある教養をつけることに、より多くの力を注いだため、男性のあり方の内に、何らかの仕方で脳の固定化、脳の硬化と名づけえる現象が起 こったのです。女性の脳は男性のものより動的で、柔軟さを多く保っています。このような表現は、もちろんこうした現象を表わすものとしてはラジカルです。 しかし現象が存在していること自体には、変わりありません。そして私は、不公平にならないように、次のように言っておきます:男性の脳は固定化している。 そのため男性は論理を取り扱うことに、より優れている。女性の脳はより動的な特性、より軽やかな特性を保っている。しかし女性は確固とした論理を内包する ここ数世紀の教養に関与しなかった。そのため女性は表面的とか何とか言われることになったと。― 同意いただけると思いますが、ことは一面的にのみ描写 すべきではないのです。